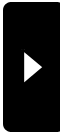2013年10月31日
日水協「全国会議の研究発表会」について(1)
昼食の後、研究発表会の始まる時間まで
水道工業団体連合会主催の水道展を見てきました。

(写真:水道展には多くの企業の出展ブースが)
上は通路のようでしたが、確認していません
残念、行けばよかった。

(写真:開会のテープカットの準備完了)
災害時に役立つ機器や最新の技術を使用した製品が
展示・紹介されていました。

(写真:緊急時に水を止める「緊急遮断弁」)

(写真:水槽内を掃除する「水底清掃ロボット」)

(写真:最新の水質測定器)
研究発表会は、事務部門、計画部門、水質部門等々
内容ごとに7会場に分けて開催されました。
会場が多く分かれており、すべての研究発表を
聞くことはできませんので、あらかじめ講演集を読んでおき
興味のあるジャンルを聞くことになります。
私たちは、東日本大震災部門とリスク管理・災害対策部門
の研究発表会に参加しました。

(写真:研究発表会の様子)
会場に入りきれずに立ち見の方も多く
また発表や質疑の時間が足りないほどでした。

(写真:仙台市からは震災における被害の研究発表)
今回は、東日本大震災における
被害や復旧についてのセッションが設けられています。

(写真:大震災部門でも多くの貴重な発表がなされました)
続きます。
水道工業団体連合会主催の水道展を見てきました。
(写真:水道展には多くの企業の出展ブースが)
上は通路のようでしたが、確認していません
残念、行けばよかった。
(写真:開会のテープカットの準備完了)
災害時に役立つ機器や最新の技術を使用した製品が
展示・紹介されていました。

(写真:緊急時に水を止める「緊急遮断弁」)

(写真:水槽内を掃除する「水底清掃ロボット」)

(写真:最新の水質測定器)
研究発表会は、事務部門、計画部門、水質部門等々
内容ごとに7会場に分けて開催されました。
会場が多く分かれており、すべての研究発表を
聞くことはできませんので、あらかじめ講演集を読んでおき
興味のあるジャンルを聞くことになります。
私たちは、東日本大震災部門とリスク管理・災害対策部門
の研究発表会に参加しました。
(写真:研究発表会の様子)
会場に入りきれずに立ち見の方も多く
また発表や質疑の時間が足りないほどでした。
(写真:仙台市からは震災における被害の研究発表)
今回は、東日本大震災における
被害や復旧についてのセッションが設けられています。
(写真:大震災部門でも多くの貴重な発表がなされました)
続きます。
2013年10月30日
日水協「第一回全国会議(福島県郡山市)」
日本水道協会の全国会議が、福島県郡山市で
平成25年10月23日~25日の日程で開催されました。
これまで「全国総会」と「水道研究発表会」が
別々の日程で開催されていましたが、今回から同時開催。
職員から参加してきましたとの報告がありましたので
数回に分けてご紹介します。
-------------------------------

(写真:JR郡山駅、まだ夕方の四時半ですが暗くなり始めています)
台風27号の影響か、そらは薄曇り
日が暮れるのも早いようです。
人口は約34万人、福島県の中央に位置する中核市
東北地方の一宿場町だった郡山は、明治になって政府の
国営事業第一号として安積野(あさかの)に猪苗代湖から水を引く
安積疎水により大きく発展してきました。
今でも市内の至るところに豊かな湖や水路が多く残されており
市民の憩いの場となっているようです。

(写真:研究発表会講演資料の表紙にもなっているビッグアイ)
20階から23階の郡山ふれあい科学館には
ギネス認定の世界一高い場所にあるプラネタリウムも。

(写真:会場となったビッグパレットふくしま)
正式名称は福島県産業交流館という県の施設
東日本大震災の折には、福島県最大の避難施設として
2,500人の方が入所されていたそうです。

(写真:すぐ隣には多くの仮設住宅が)
復興はまだまだ進んでおらず
今でも仮設住宅には多くの方が住んでおられます。

(写真:ビッグパレット福島の大きさにただビックリ)
郡山市水道局の皆さんが暖かく迎えてくださいました
また、市内の案内等(食事場所)についても
快く相談に応じてくださいました、ありがとうございました。

(写真:全国会議の看板や案内板が随所に)

(写真:会議は、2,500名の参加でした)
日常業務を行いながら、これだけの準備をされるのは
とても大変なことだったろうと感じたところです。
当企業団でも、全国企業団の総会を
担当したことがありますが、規模が全然違います。

(写真:超大型のディスプレイ)

(写真:開催地代表挨拶は品川郡山市長さん)
この後、日水協会長である猪瀬東京都知事の挨拶があり
水道事業功労者に対する表彰式で午前の部が終了。
続きます。
平成25年10月23日~25日の日程で開催されました。
これまで「全国総会」と「水道研究発表会」が
別々の日程で開催されていましたが、今回から同時開催。
職員から参加してきましたとの報告がありましたので
数回に分けてご紹介します。
-------------------------------
(写真:JR郡山駅、まだ夕方の四時半ですが暗くなり始めています)
台風27号の影響か、そらは薄曇り
日が暮れるのも早いようです。
人口は約34万人、福島県の中央に位置する中核市
東北地方の一宿場町だった郡山は、明治になって政府の
国営事業第一号として安積野(あさかの)に猪苗代湖から水を引く
安積疎水により大きく発展してきました。
今でも市内の至るところに豊かな湖や水路が多く残されており
市民の憩いの場となっているようです。
(写真:研究発表会講演資料の表紙にもなっているビッグアイ)
20階から23階の郡山ふれあい科学館には
ギネス認定の世界一高い場所にあるプラネタリウムも。
(写真:会場となったビッグパレットふくしま)
正式名称は福島県産業交流館という県の施設
東日本大震災の折には、福島県最大の避難施設として
2,500人の方が入所されていたそうです。
(写真:すぐ隣には多くの仮設住宅が)
復興はまだまだ進んでおらず
今でも仮設住宅には多くの方が住んでおられます。
(写真:ビッグパレット福島の大きさにただビックリ)
郡山市水道局の皆さんが暖かく迎えてくださいました
また、市内の案内等(食事場所)についても
快く相談に応じてくださいました、ありがとうございました。
(写真:全国会議の看板や案内板が随所に)
(写真:会議は、2,500名の参加でした)
日常業務を行いながら、これだけの準備をされるのは
とても大変なことだったろうと感じたところです。
当企業団でも、全国企業団の総会を
担当したことがありますが、規模が全然違います。
(写真:超大型のディスプレイ)
(写真:開催地代表挨拶は品川郡山市長さん)
この後、日水協会長である猪瀬東京都知事の挨拶があり
水道事業功労者に対する表彰式で午前の部が終了。
続きます。
2013年10月29日
「技術継承」の委員会終了
マスコミ等でご承知だと思いますが
団塊の世代の大量退職に伴う弊害が取りざたされています。
当企業団でも、その例にもれず
職員数73人の内50歳以上の職員が32人
そのうち55歳以上の職員が21人と
今後5年余りで
企業団の創設期を経験した職員はいなくなってしまいます。

(グラフ:東部水道企業団の年齢別職員構成)
この解消には
次の世代にスムーズにバトンを受け渡すことが大事で
5月から職員による委員会で議論をしてもらっていました
その議論の結果と要点の議事録の報告を受けました
月1回のペースで精力的にやってくれました。
組織の弱点は
一見してわかる職員の年齢構成の「いびつさ」
長年、新規の職員採用を控えてきた結果です
が、これには訳があり、それを理由にはできません。
委員会の結論は「お互いが疑問を持つ」でした
私もこの結論に納得です。
マニュアル化と電算化それに日頃の繁忙感で
「流される仕事」では、利用者の皆さまの期待には添えません。
具体的なシナリオやスケジュールも示されていますが
要は「水道のプロ」として
各々がこの地域の「けん引者になって欲しい」
その気持ちだけです。
団塊の世代の大量退職に伴う弊害が取りざたされています。
当企業団でも、その例にもれず
職員数73人の内50歳以上の職員が32人
そのうち55歳以上の職員が21人と
今後5年余りで
企業団の創設期を経験した職員はいなくなってしまいます。

(グラフ:東部水道企業団の年齢別職員構成)
この解消には
次の世代にスムーズにバトンを受け渡すことが大事で
5月から職員による委員会で議論をしてもらっていました
その議論の結果と要点の議事録の報告を受けました
月1回のペースで精力的にやってくれました。
組織の弱点は
一見してわかる職員の年齢構成の「いびつさ」
長年、新規の職員採用を控えてきた結果です
が、これには訳があり、それを理由にはできません。
委員会の結論は「お互いが疑問を持つ」でした
私もこの結論に納得です。
マニュアル化と電算化それに日頃の繁忙感で
「流される仕事」では、利用者の皆さまの期待には添えません。
具体的なシナリオやスケジュールも示されていますが
要は「水道のプロ」として
各々がこの地域の「けん引者になって欲しい」
その気持ちだけです。
2013年10月28日
人口減少時代を迎える水道(2)
前回からの続きです。
今までは国の指導で良かったものが、自分自身で想像して投資する
その投資結果は、その時がくれば必ず分かる
だから「自己責任で投資し、結果責任を負う」
という難しい運営が待っているようにも思います。
さて、その具体的なシナリオです
新しい水道のビジョンでも、概略が示されているが
要は、国の指導一辺倒から、企業団自身で想像して投資する
「自己責任で投資し、結果責任を負う」
まず一般論ですが
施設の更新時には、実給水量に即したスリム化や施設の統廃合。
ここでの視点は
東部水道企業団の場合、現状で日最大が水利権の8割
次の更新期に、これをどう捉えるのか?
「水利権は確保し、将来の必要量にそった設備とする」が常識。

(写真:稼働からまもなく30年を迎える「北茂安浄水場」)
しかし、不安もつきまとう
この不安解消策が、広域連携や統廃合
あわせて、余剰水利権の新たな需要開拓か
一朝一夕には、当然いかない
だからこそ、日頃からのお互いの議論と小さな連携議論が重要。
誰でもが経験したことがない時代が必ず来ると思います
それに対して、水道の関係者が共有して備える。
並行して、東部水道企業団も大いに議論して知恵を出す
50年後、100年後を目指して「公共の使命」と「企業の経営」を考える。
いずれにしても「生き残り」を賭けた競争の時代が
「やがてやってくる」ということでしょう。
今までは国の指導で良かったものが、自分自身で想像して投資する
その投資結果は、その時がくれば必ず分かる
だから「自己責任で投資し、結果責任を負う」
という難しい運営が待っているようにも思います。
さて、その具体的なシナリオです
新しい水道のビジョンでも、概略が示されているが
要は、国の指導一辺倒から、企業団自身で想像して投資する
「自己責任で投資し、結果責任を負う」
まず一般論ですが
施設の更新時には、実給水量に即したスリム化や施設の統廃合。
ここでの視点は
東部水道企業団の場合、現状で日最大が水利権の8割
次の更新期に、これをどう捉えるのか?
「水利権は確保し、将来の必要量にそった設備とする」が常識。

(写真:稼働からまもなく30年を迎える「北茂安浄水場」)
しかし、不安もつきまとう
この不安解消策が、広域連携や統廃合
あわせて、余剰水利権の新たな需要開拓か
一朝一夕には、当然いかない
だからこそ、日頃からのお互いの議論と小さな連携議論が重要。
誰でもが経験したことがない時代が必ず来ると思います
それに対して、水道の関係者が共有して備える。
並行して、東部水道企業団も大いに議論して知恵を出す
50年後、100年後を目指して「公共の使命」と「企業の経営」を考える。
いずれにしても「生き残り」を賭けた競争の時代が
「やがてやってくる」ということでしょう。
2013年10月25日
人口減少時代を迎える水道(1)
今の人口は、約125百万人
50年後は7割の88百万人、100年後は50百万人の予想
逆に50年前は85百万人、100年前は50百万人
50年後は50年前と、100年後は100年前に戻る
そんな推計がされています。
そんな中での水道事業の未来は
「人口が少なくなる」ことは水道の収入が少なくなる
これにつきます
それで水道事業は運営できるか?
まず、水道は「未来永劫無くならない」でしょう
だから、事業は続きます
しかし、今と同じようにはいきません
単純計算では、50年後は人口減の分、7割の収入で運営をする
単純には、こんなことでしょう。
「出来るのか?」料金を上げれば可能でしょう
しかし、そんな考えでいたら水道以外の公共施設も五十歩百歩
全てが値上がりしては、普通の生活は出来ません。
水道等の施設は「長く使うもの」です
このことは、造る時に十分将来を考えて造る必要があります
これも、当然といえば当然のことです。
さて、50年後には今の7割の人口
100年後は、4割程度の人口
その時代の町や地域はどうなっているのか?
これを考えないで「水道の将来を考えて造る」はないでしょう。
だから、水道の未来予想図は、町の未来予想図でもあるはずです
水道に携わる職員は
東部水道企業団の受け持ち地域の50年後、100年後の
町の姿を想像する仕事さえも必要です。
次回へ続きます。
50年後は7割の88百万人、100年後は50百万人の予想
逆に50年前は85百万人、100年前は50百万人
50年後は50年前と、100年後は100年前に戻る
そんな推計がされています。
そんな中での水道事業の未来は
「人口が少なくなる」ことは水道の収入が少なくなる
これにつきます
それで水道事業は運営できるか?
まず、水道は「未来永劫無くならない」でしょう
だから、事業は続きます
しかし、今と同じようにはいきません
単純計算では、50年後は人口減の分、7割の収入で運営をする
単純には、こんなことでしょう。
「出来るのか?」料金を上げれば可能でしょう
しかし、そんな考えでいたら水道以外の公共施設も五十歩百歩
全てが値上がりしては、普通の生活は出来ません。
水道等の施設は「長く使うもの」です
このことは、造る時に十分将来を考えて造る必要があります
これも、当然といえば当然のことです。
さて、50年後には今の7割の人口
100年後は、4割程度の人口
その時代の町や地域はどうなっているのか?
これを考えないで「水道の将来を考えて造る」はないでしょう。
だから、水道の未来予想図は、町の未来予想図でもあるはずです
水道に携わる職員は
東部水道企業団の受け持ち地域の50年後、100年後の
町の姿を想像する仕事さえも必要です。
次回へ続きます。
2013年10月24日
補正ヒア「勉強の場」
10月初旬から約2週間にわたって
今年度予算の「補正のヒアリング」でした
併せて、各部署での今年度の事業等進捗の報告も聞きました。
進捗状況は順調です
各々のポジションで意欲的に取り組んでいることが見てとれます。
補正の案件は、大小ありますが
目に付いたところを紹介します。
工務系では、水道管の布設工事における
延長や方法の変更等での予算の増減以外にはありません。
ここでの今後の課題は「維持管理」です
出来るだけ設備を「長もち」させる
そのためには、日常的に何をするか?
来年の重点として、組織をあげて考えていきます。
浄水場は、取水ポンプの修繕が必要です
筑後川の原水を浄水場に送るポンプの故障です。
予備まで含めて4台のポンプがありますので
取水に問題はありません
通常、ポンプの耐用年数は15年
通水開始後28年が経過、長期計画では30年持たせる
と、しています。
倍の寿命を目標にするには
当然日頃からのメンテナンスが重要です
このポンプが故障した
そこに、どんな因果関係があるのか、調査もあわせて行ないます。

(写真:筑後川から水を取水するためのポンプ
予備を含めて大小4台のポンプを設置しています)
また、浄化のための薬品も
筑後川の水質で使用量は大きく変わります
近年の異常気象でしょう、薬品(活性炭)の使用量が増えています。

(写真:北茂安浄水場に設置している「活性炭注入設備」
「活性炭注入設備」は、基山浄水場にも設置しています)
この活性炭
東日本大震災での需要の増加によって
単価がアップしていました。
それの単価が、予算時に比べて安く契約ができ
減額できる結果になりました
単価を見てみると震災前に戻ったようです。
これらは、12月議会で承認をうけた後執行します
このヒアリングは
予算に直接関係がないことも知ることが出来ます
私にとっては、この上ない勉強の場です。
今年度予算の「補正のヒアリング」でした
併せて、各部署での今年度の事業等進捗の報告も聞きました。
進捗状況は順調です
各々のポジションで意欲的に取り組んでいることが見てとれます。
補正の案件は、大小ありますが
目に付いたところを紹介します。
工務系では、水道管の布設工事における
延長や方法の変更等での予算の増減以外にはありません。
ここでの今後の課題は「維持管理」です
出来るだけ設備を「長もち」させる
そのためには、日常的に何をするか?
来年の重点として、組織をあげて考えていきます。
浄水場は、取水ポンプの修繕が必要です
筑後川の原水を浄水場に送るポンプの故障です。
予備まで含めて4台のポンプがありますので
取水に問題はありません
通常、ポンプの耐用年数は15年
通水開始後28年が経過、長期計画では30年持たせる
と、しています。
倍の寿命を目標にするには
当然日頃からのメンテナンスが重要です
このポンプが故障した
そこに、どんな因果関係があるのか、調査もあわせて行ないます。
(写真:筑後川から水を取水するためのポンプ
予備を含めて大小4台のポンプを設置しています)
また、浄化のための薬品も
筑後川の水質で使用量は大きく変わります
近年の異常気象でしょう、薬品(活性炭)の使用量が増えています。

(写真:北茂安浄水場に設置している「活性炭注入設備」
「活性炭注入設備」は、基山浄水場にも設置しています)
この活性炭
東日本大震災での需要の増加によって
単価がアップしていました。
それの単価が、予算時に比べて安く契約ができ
減額できる結果になりました
単価を見てみると震災前に戻ったようです。
これらは、12月議会で承認をうけた後執行します
このヒアリングは
予算に直接関係がないことも知ることが出来ます
私にとっては、この上ない勉強の場です。
2013年10月23日
財務講習会(宮崎市)に参加して
東部水道企業団では、職員のレベルアップのために
必要に応じて、各種講習会・研修会に職員を参加させています。
今回、宮崎市で行われた「地方公営企業財務会計講習会」に
参加した職員から報告がありましたので、紹介します。
------------------------------
先日、(財)地方財務協会の主催で開催された
財務講習会に参加しました。
宮崎県外から72名、宮崎県内から50名の参加があり
総務省の方や会計士の方を講師に
公営企業財務の基礎を学びました。

(写真:講習会の様子)
地方公営企業法に基づき業務を行っている私は
企業としての合理的、能率的な経営をもとめられていると共に
住民の福祉の増進も求められ、予算化されていることを再認識。
少しでも住民の方へ安く水道水を届けられるよう、
日々の努力が更に必要だと思いを新たにし、講習を受けました。
その頃、佐賀には台風24号の接近、築40年の我が家では
家族が台風対策、幸い県内に大きな被害がなかったので
ほっとしました。
講師の方々も、飛行機がダメではと陸路で宮崎入りされたり
1日遅らせて帰ろうかと心配されていました。
宮崎市でも、台風当日は雨・風がありましたが
翌日は、晴天
宮崎市の方曰く、この晴天が本来の南国宮崎です。

(写真:台風一過の青空となった宮崎市内)
宮崎市では、平成19年3月に「宮崎市ごみのぽい捨ての防止及び
公共の場所における喫煙の制限に関する条例」が制定されています。

(写真:歩道に設置された灰皿)
そのためか、市内道路の各所に灰皿が設置され
店舗やホテル入口にも
町ぐるみで取り組まれていました。
ごみの無い綺麗なストリートを
散歩やホテルとの往復に利用しました
お世話になりました。
講習会でお世話いただいた方々
ありがとうございました。
必要に応じて、各種講習会・研修会に職員を参加させています。
今回、宮崎市で行われた「地方公営企業財務会計講習会」に
参加した職員から報告がありましたので、紹介します。
------------------------------
先日、(財)地方財務協会の主催で開催された
財務講習会に参加しました。
宮崎県外から72名、宮崎県内から50名の参加があり
総務省の方や会計士の方を講師に
公営企業財務の基礎を学びました。

(写真:講習会の様子)
地方公営企業法に基づき業務を行っている私は
企業としての合理的、能率的な経営をもとめられていると共に
住民の福祉の増進も求められ、予算化されていることを再認識。
少しでも住民の方へ安く水道水を届けられるよう、
日々の努力が更に必要だと思いを新たにし、講習を受けました。
その頃、佐賀には台風24号の接近、築40年の我が家では
家族が台風対策、幸い県内に大きな被害がなかったので
ほっとしました。
講師の方々も、飛行機がダメではと陸路で宮崎入りされたり
1日遅らせて帰ろうかと心配されていました。
宮崎市でも、台風当日は雨・風がありましたが
翌日は、晴天
宮崎市の方曰く、この晴天が本来の南国宮崎です。

(写真:台風一過の青空となった宮崎市内)
宮崎市では、平成19年3月に「宮崎市ごみのぽい捨ての防止及び
公共の場所における喫煙の制限に関する条例」が制定されています。

(写真:歩道に設置された灰皿)
そのためか、市内道路の各所に灰皿が設置され
店舗やホテル入口にも
町ぐるみで取り組まれていました。
ごみの無い綺麗なストリートを
散歩やホテルとの往復に利用しました
お世話になりました。
講習会でお世話いただいた方々
ありがとうございました。
2013年10月22日
佐賀市長が決まりました
4人の方が立候補されての選挙戦
それぞれが立派な方、巷の予想通りの激戦でした
現職の秀島氏が、多くの市民の支持を得て3選をされました。
ここ東部水道企業団は、佐賀市を含む構成市町の水道を担っています
なかでも、佐賀市長は企業団議会の議長職
無関心ではいられません。
東部水道企業団の大きな課題は「将来の水道のあり方」
将来の人口減少を見越して計画を立案する
その場合「連携」がキーワード、このブログでも常々紹介しています。
市長候補の各人のマニュフェトを見せていただきましたが
水道のあり方に言及されていました
過去2期8年の佐賀市との意思疎通と今後の方針の一致
継続して、水道のより良い未来像を目指します。
今後も佐賀市を始め構成団体の首長さんや関係する皆さんと
「利用者の皆さん」にとっての水道の将来像を目指していきます。
それぞれが立派な方、巷の予想通りの激戦でした
現職の秀島氏が、多くの市民の支持を得て3選をされました。
ここ東部水道企業団は、佐賀市を含む構成市町の水道を担っています
なかでも、佐賀市長は企業団議会の議長職
無関心ではいられません。
東部水道企業団の大きな課題は「将来の水道のあり方」
将来の人口減少を見越して計画を立案する
その場合「連携」がキーワード、このブログでも常々紹介しています。
市長候補の各人のマニュフェトを見せていただきましたが
水道のあり方に言及されていました
過去2期8年の佐賀市との意思疎通と今後の方針の一致
継続して、水道のより良い未来像を目指します。
今後も佐賀市を始め構成団体の首長さんや関係する皆さんと
「利用者の皆さん」にとっての水道の将来像を目指していきます。
2013年10月21日
平成25年度防災訓練について(その3)
訓練を予定していた日が、台風24号の来襲で延期
日を改めての訓練でした。
今回は「佐賀市からの給水連携」が主な目的
具体的な仕組みや方法は図面上では聞いていました。

(写真:今回の訓練資料「佐賀市から応援給水を受けた場合」)
訓練の内容は、先日までのブログで紹介しましたが
私自身が、ポイントとなる現場の位置や作業の状態を知りたい
また、応援給水を受ける場合の「水道水の流れ」も
実際に見て体感したい、そんな思いで「現場視察」を行いました。
実際に見て、作業の流れ、ポイント部分
また「水道水の流れを変える」ことへの種々の対応等
納得しました。
また、私なりの課題も気づきました。
途中から雨の中での訓練となりましたが
今回の想定エリアでは、本管に事故があっても
「利用者の方には迷惑をかけない」ということを
実感することができました。
また、この訓練が
「単なる訓練のための訓練」にはなっていないことも実感しました
私にとっても良い機会でした。
日を改めての訓練でした。
今回は「佐賀市からの給水連携」が主な目的
具体的な仕組みや方法は図面上では聞いていました。
(写真:今回の訓練資料「佐賀市から応援給水を受けた場合」)
訓練の内容は、先日までのブログで紹介しましたが
私自身が、ポイントとなる現場の位置や作業の状態を知りたい
また、応援給水を受ける場合の「水道水の流れ」も
実際に見て体感したい、そんな思いで「現場視察」を行いました。
実際に見て、作業の流れ、ポイント部分
また「水道水の流れを変える」ことへの種々の対応等
納得しました。
また、私なりの課題も気づきました。
途中から雨の中での訓練となりましたが
今回の想定エリアでは、本管に事故があっても
「利用者の方には迷惑をかけない」ということを
実感することができました。
また、この訓練が
「単なる訓練のための訓練」にはなっていないことも実感しました
私にとっても良い機会でした。
2013年10月18日
平成25年度防災訓練について(その2)
昨日からの続きです。
参加者ばかりでなく、技術系職員には
訓練内容の事前学習会も開催され
分水地点や分岐バルブでの操作に対する理解度や認知度は
例年より浸透していたと思われます。

(写真:佐賀市北川副の減圧弁室及び分水地点)
日常業務の職員にも訓練内容を実感できればと
本部との無線交信を館内放送しました
効果は意見集約の結果待ちという状態です。

(写真:本庁会議室に設置した対策本部)

(写真:道路上に設置されたバルブの操作も行います)
防災訓練というのは
繰り返すことが大事であり
繰り返しながら少しでも改善していくこと
いつ起きるかわからない災害に対して
油断しないで訓練を重ねることで
被害を少しでも小さくして
水道水をお届けすることが訓練の目標です。
次回に続きます。
参加者ばかりでなく、技術系職員には
訓練内容の事前学習会も開催され
分水地点や分岐バルブでの操作に対する理解度や認知度は
例年より浸透していたと思われます。
(写真:佐賀市北川副の減圧弁室及び分水地点)
日常業務の職員にも訓練内容を実感できればと
本部との無線交信を館内放送しました
効果は意見集約の結果待ちという状態です。
(写真:本庁会議室に設置した対策本部)
(写真:道路上に設置されたバルブの操作も行います)
防災訓練というのは
繰り返すことが大事であり
繰り返しながら少しでも改善していくこと
いつ起きるかわからない災害に対して
油断しないで訓練を重ねることで
被害を少しでも小さくして
水道水をお届けすることが訓練の目標です。
次回に続きます。
2013年10月17日
平成25年度防災訓練について(その1)
今年度の防災訓練は、「応急給水での住民への説明訓練」と
「事故現場での復旧訓練」の2種類に分けての実施でした。
------------------------------
事務系職員を対象とした説明訓練は
今年から実施、今後も続けることが大事なことです。
(平成25年10月9日のブログで紹介しています)

(写真:「応急給水での住民への説明訓練」の様子)
------------------------------
今年の復旧訓練は
減圧弁室での漏水事故と想定した訓練でした。
浄水場から送られる水道水は、送水施設の都合上
高い圧力がかかっており、お客様へ供給する際には
圧力を下げる必要があります。
圧力を下げる機器を「減圧弁」といい
その機器類を設置している施設を「減圧弁室」と呼んでいます。

(写真:減圧弁室に設置された計器で水の圧力を確認します)
事故があった際には
佐賀市上下水道局から応援を受けることとなりますので
佐賀市東与賀町及び北川副町地点での応援受水に関する
協議やバルブ操作訓練
送水管の緊急断水及び復旧訓練
事故発生から復旧完了までの本部協議並びに情報伝達
の訓練を実施しました。

(写真:北茂安浄水場との無線連絡の様子)

(写真:佐賀市川副の減圧弁室)
今回の訓練は、近日中に減圧弁の更新工事が予定されており
実際に実施する現場作業のシミュレーション
を兼ねた訓練となっていました。
明日に続きます。
「事故現場での復旧訓練」の2種類に分けての実施でした。
------------------------------
事務系職員を対象とした説明訓練は
今年から実施、今後も続けることが大事なことです。
(平成25年10月9日のブログで紹介しています)
(写真:「応急給水での住民への説明訓練」の様子)
------------------------------
今年の復旧訓練は
減圧弁室での漏水事故と想定した訓練でした。
浄水場から送られる水道水は、送水施設の都合上
高い圧力がかかっており、お客様へ供給する際には
圧力を下げる必要があります。
圧力を下げる機器を「減圧弁」といい
その機器類を設置している施設を「減圧弁室」と呼んでいます。
(写真:減圧弁室に設置された計器で水の圧力を確認します)
事故があった際には
佐賀市上下水道局から応援を受けることとなりますので
佐賀市東与賀町及び北川副町地点での応援受水に関する
協議やバルブ操作訓練
送水管の緊急断水及び復旧訓練
事故発生から復旧完了までの本部協議並びに情報伝達
の訓練を実施しました。

(写真:北茂安浄水場との無線連絡の様子)

(写真:佐賀市川副の減圧弁室)
今回の訓練は、近日中に減圧弁の更新工事が予定されており
実際に実施する現場作業のシミュレーション
を兼ねた訓練となっていました。
明日に続きます。
2013年10月16日
親睦ボーリング大会
先日は、恒例の職場のボーリング大会
大勢の参加者が集まり、開催されました。

(写真:職場のボーリング大会)
参加者の大部分は
年1回このボーリング大会のみの経験だろう
それでもトップは、2ゲームで351点。
職場の福利厚生の一環
当然、貸切状態の場内は、和気あいあい
最初に、私が代表で「金色のボール」での始球式。
投球のたびに一喜一憂
ストライクやスペアがとれれば、その都度ハイタッチ
小腹を満たすハンバーガーとジュースを頂きながら
楽しい時間を過ごしました。

(写真:久しぶりにプレイしました)

(写真:なかなかストライクとなりません)
私の結果は、1ゲーム目は90点台
「こんなにも下手だったのか」と少々不満
2ゲーム目は170点台
「昔は・・・」と言いたくなる心境でした。
さて、優勝者はY君
コメントは「始めての優勝、しかし賞品は拍手だけ」と不満げ
そうだろう、やはり何かがないとつまらない
来年は、トップには優勝杯でも寄付するとしよう。
大勢の参加者が集まり、開催されました。

(写真:職場のボーリング大会)
参加者の大部分は
年1回このボーリング大会のみの経験だろう
それでもトップは、2ゲームで351点。
職場の福利厚生の一環
当然、貸切状態の場内は、和気あいあい
最初に、私が代表で「金色のボール」での始球式。
投球のたびに一喜一憂
ストライクやスペアがとれれば、その都度ハイタッチ
小腹を満たすハンバーガーとジュースを頂きながら
楽しい時間を過ごしました。

(写真:久しぶりにプレイしました)

(写真:なかなかストライクとなりません)
私の結果は、1ゲーム目は90点台
「こんなにも下手だったのか」と少々不満
2ゲーム目は170点台
「昔は・・・」と言いたくなる心境でした。
さて、優勝者はY君
コメントは「始めての優勝、しかし賞品は拍手だけ」と不満げ
そうだろう、やはり何かがないとつまらない
来年は、トップには優勝杯でも寄付するとしよう。
2013年10月15日
「長期財政計画」の検討報告
先だって「長期事業計画検討会」の報告書が
私の手元に届いたと書きました。
20年後の姿を見据えた検討が主目的
だが、40年後も想定した内容まで盛り込まれている。
今後、これをどう活かして進めていくかが
企業団の評価と信頼につながるはず。
今年は、財政計画の見直しを行う予定で
現在策定中。(前回は平成22年度)
各部署からのヒアリングには、当然「長期事業計画検討会」の
内容が盛り込まれているはずです。

(写真:各課ヒアリングの様子)
財政計画見直しを進めるなかで
きちんと策定すべきは、次の3項目
この3項目は密接な関係が深い
また、水道料金値下げについても検討課題として提案。
水道事業の主な収入は水道料金
使用水量が増えれば、料金収入は増える
しかし、日本の人口は減少傾向の予測
企業団もこの流れには逆らえない。
事業については、古い水道管を新しく入れ替える工事
災害に備えた施設補強や耐震管路に変更していく工事
コンクリート構造物の老朽化による更新工事など継続的にあります。
人員については、目の前に迫った
来年からの大量退職の現実と再雇用との調整。
現在、財政係でこれらを基本とした
9年間(平成26~34年度)の財政計画見直しの作業中です。
10月末の幹事会で構成団体へ提案説明を行い
12月の議会へ正式に提案、この日程で調整中との中間報告あり。
私の手元に届いたと書きました。
20年後の姿を見据えた検討が主目的
だが、40年後も想定した内容まで盛り込まれている。
今後、これをどう活かして進めていくかが
企業団の評価と信頼につながるはず。
今年は、財政計画の見直しを行う予定で
現在策定中。(前回は平成22年度)
各部署からのヒアリングには、当然「長期事業計画検討会」の
内容が盛り込まれているはずです。
(写真:各課ヒアリングの様子)
財政計画見直しを進めるなかで
きちんと策定すべきは、次の3項目
この3項目は密接な関係が深い
また、水道料金値下げについても検討課題として提案。
水道事業の主な収入は水道料金
使用水量が増えれば、料金収入は増える
しかし、日本の人口は減少傾向の予測
企業団もこの流れには逆らえない。
事業については、古い水道管を新しく入れ替える工事
災害に備えた施設補強や耐震管路に変更していく工事
コンクリート構造物の老朽化による更新工事など継続的にあります。
人員については、目の前に迫った
来年からの大量退職の現実と再雇用との調整。
現在、財政係でこれらを基本とした
9年間(平成26~34年度)の財政計画見直しの作業中です。
10月末の幹事会で構成団体へ提案説明を行い
12月の議会へ正式に提案、この日程で調整中との中間報告あり。
2013年10月11日
会計制度変更後の東部水道企業団の姿
昨日からの続きです。
地方公営企業の会計制度が変更され
平成26年度の予算・決算から適用になる予定です。
だから、現在
会計システムの更新や移行による資産の整理等を
急ピッチで整えています。
この変更で、東部水道企業団として「何がわかるか?」
これが重要です。
変更点としては、会計基準の見直しで
大まかに、下記にまとめてみます。
・借入資本金の表示区分変更
(資本→負債)
・補助金等により取得した資産の償却制度の変更
(みなし償却の廃止等含む)
・引当金の計上義務付け
(貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金等)
・繰延勘定の原則廃止
(研究開発費等の繰延費用化はしない)
・たな卸資産への低価法の適用
(短期間で出庫するものは対象外)
・リース会計の導入
(中小の企業体はしないことも可)
・減損会計の導入
(遊休資産の整理等)
・セグメント情報の開示
(複数の事業を行っている事業体では事業毎に情報開示)
・キャッシュフロー計算書の作成
(資金計画書は廃止)
・勘定科目の見直し
(基準見直しにより新たな科目が発生)
・組入資本金制度の廃止
(減債積立金等の使用後は、利益剰余金へ移る)等
少々難しい内容ですが
要は、比較のルールが統一され
他の事業体等との比較が容易となることが期待されます。
地方公営企業の会計制度が変更され
平成26年度の予算・決算から適用になる予定です。
だから、現在
会計システムの更新や移行による資産の整理等を
急ピッチで整えています。
この変更で、東部水道企業団として「何がわかるか?」
これが重要です。
変更点としては、会計基準の見直しで
大まかに、下記にまとめてみます。
・借入資本金の表示区分変更
(資本→負債)
・補助金等により取得した資産の償却制度の変更
(みなし償却の廃止等含む)
・引当金の計上義務付け
(貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金等)
・繰延勘定の原則廃止
(研究開発費等の繰延費用化はしない)
・たな卸資産への低価法の適用
(短期間で出庫するものは対象外)
・リース会計の導入
(中小の企業体はしないことも可)
・減損会計の導入
(遊休資産の整理等)
・セグメント情報の開示
(複数の事業を行っている事業体では事業毎に情報開示)
・キャッシュフロー計算書の作成
(資金計画書は廃止)
・勘定科目の見直し
(基準見直しにより新たな科目が発生)
・組入資本金制度の廃止
(減債積立金等の使用後は、利益剰余金へ移る)等
少々難しい内容ですが
要は、比較のルールが統一され
他の事業体等との比較が容易となることが期待されます。
2013年10月10日
会計制度の変更
地方公営企業の会計制度が見直され
46年ぶりに大幅に改正されます。
現在、財務諸表の作成義務があるのが
水道、病院、軌道、自動車、鉄道、電気、ガス、工業用水の
8事業で、全国に約9,000ある公営企業の約3割
まずは、その3割の公営企業の会計制度を
民間企業と同じ仕組みにするという改正です。

(写真:「企業団の本庁舎」
東部水道企業団も、佐賀県の東部に位置する13市町村(当時)
によって、共同で水道事業を行うために設立されました)
【地方公営企業とは】
地方公共団体が経営する地方公営企業法の適用を受ける事業。
都道府県および市町村が経営し、一般会計(行政予算)とは
切り離された 特別会計での独立採算制を採る。
地方公共団体が政令で指定された事業(給水事業・電気事業・
交通事業・ガス事業など)を行う場合は、この経営形式を
取らなければならない。
ここまでを、私の主観で簡単に言えば
市役所等の一般会計は単式簿記、水道等は複式簿記
今回の改正は、さらに民間企業並みに変える
民間企業会計との大きな違いは、起債(借金)の捉え方
民間では借金、今までの水道会計では収入
乱暴な言い草ですが、こんなことでしょう。
ところで、財務諸表とは企業が利害の関係者に対して
一定期間の経営成績や財務の状況を明らかにするために
複式簿記に基づき作成する決算書類
もっと簡単に言えば「企業の健康診断書」のようなものです。
今回の改正は、経営の透明化を図るのが目的で
「民間並み」のイメージは、公営企業の資産や負債の変動
資金の流れといった経営状況がより把握しやすくなります。
このことは、全国横並びで「経営の健全化」の状況がわかる
ということでもあります。
つまり、住民の方や議会によるチェック機能が
強化されることになります。
我々、公営企業側も
経営計画や老朽施設の更新計画を作りやすくなる効果も見込まれます。
今後は、より一層経営判断に基づいた会計方針のもとで
会計処理を行なっていくことになるでしょう
要するに、より「自己責任」を負うことになるはずです。
46年ぶりに大幅に改正されます。
現在、財務諸表の作成義務があるのが
水道、病院、軌道、自動車、鉄道、電気、ガス、工業用水の
8事業で、全国に約9,000ある公営企業の約3割
まずは、その3割の公営企業の会計制度を
民間企業と同じ仕組みにするという改正です。
(写真:「企業団の本庁舎」
東部水道企業団も、佐賀県の東部に位置する13市町村(当時)
によって、共同で水道事業を行うために設立されました)
【地方公営企業とは】
地方公共団体が経営する地方公営企業法の適用を受ける事業。
都道府県および市町村が経営し、一般会計(行政予算)とは
切り離された 特別会計での独立採算制を採る。
地方公共団体が政令で指定された事業(給水事業・電気事業・
交通事業・ガス事業など)を行う場合は、この経営形式を
取らなければならない。
ここまでを、私の主観で簡単に言えば
市役所等の一般会計は単式簿記、水道等は複式簿記
今回の改正は、さらに民間企業並みに変える
民間企業会計との大きな違いは、起債(借金)の捉え方
民間では借金、今までの水道会計では収入
乱暴な言い草ですが、こんなことでしょう。
ところで、財務諸表とは企業が利害の関係者に対して
一定期間の経営成績や財務の状況を明らかにするために
複式簿記に基づき作成する決算書類
もっと簡単に言えば「企業の健康診断書」のようなものです。
今回の改正は、経営の透明化を図るのが目的で
「民間並み」のイメージは、公営企業の資産や負債の変動
資金の流れといった経営状況がより把握しやすくなります。
このことは、全国横並びで「経営の健全化」の状況がわかる
ということでもあります。
つまり、住民の方や議会によるチェック機能が
強化されることになります。
我々、公営企業側も
経営計画や老朽施設の更新計画を作りやすくなる効果も見込まれます。
今後は、より一層経営判断に基づいた会計方針のもとで
会計処理を行なっていくことになるでしょう
要するに、より「自己責任」を負うことになるはずです。
2013年10月09日
「応急給水」の職員研修
災害時、水道が使えなくなった際には
水を運んでの応急給水が必要となります。
そうした事態を想定し、企業団でも毎年
住民の方にも参加をお願いした防災訓練を行っています。
昨年までは、工務系の職員を主体としていましたが
実際に災害が発生した場合、工務系職員は
被災状況調査や漏水修繕対応に追われることとなり
実際に応急給水に従事するのは
事務系の職員となることが想定されます。
そのため今年度から
応急給水の企業団内部研修を実施しました
全職員が応急給水作業に慣れることが目的です。

(写真:「応急給水」内部研修の様子)
初めて「給水袋」や「応急給水に使用する機器」を
扱う職員もいることから、作業に慣れた職員を講師に
研修を行いました。

(写真:「6リットルの給水袋」の使い方について)

(写真:「1m3の給水タンク」の搬送について)

(写真:「仮設給水栓」等の設置について)

(写真:「発電機」の使い方について)

(写真:「加圧ポンプ」の使い方について)
応急給水作業を問題無く行えるように
今後も研修を続けていきます。
水を運んでの応急給水が必要となります。
そうした事態を想定し、企業団でも毎年
住民の方にも参加をお願いした防災訓練を行っています。
昨年までは、工務系の職員を主体としていましたが
実際に災害が発生した場合、工務系職員は
被災状況調査や漏水修繕対応に追われることとなり
実際に応急給水に従事するのは
事務系の職員となることが想定されます。
そのため今年度から
応急給水の企業団内部研修を実施しました
全職員が応急給水作業に慣れることが目的です。
(写真:「応急給水」内部研修の様子)
初めて「給水袋」や「応急給水に使用する機器」を
扱う職員もいることから、作業に慣れた職員を講師に
研修を行いました。
(写真:「6リットルの給水袋」の使い方について)
(写真:「1m3の給水タンク」の搬送について)
(写真:「仮設給水栓」等の設置について)
(写真:「発電機」の使い方について)
(写真:「加圧ポンプ」の使い方について)
応急給水作業を問題無く行えるように
今後も研修を続けていきます。
2013年10月08日
年度の半分が終了「課題の状況」
年度の半分が終わりました
今年の課題の整理と現在の状況の報告です。
今年の、企業団として取り組んでいることは2点
1点目は、長期財政計画
このことは、将来の「東部水道企業団としてのあり方」を描き
それに対する課題と準備を行なうとの側面と
中期的な財政計画の見通しをたてるの二つが主な主旨です
その都度ご報告しているように、作業は順調です。
2点目は、「技術の継承」
団塊の世代に引き続き
企業団設立時の経験豊富な職員の退職が今後も続きます
この「技術力」「経験力」それに「経営力」の継承が必須です。
もちろん、あとを引き継ぐ職員も育っています
特にお願いしたいのは
「経験力」の継承は「過去の失敗事例に学ぶ」
「経営力」の継承は「将来に対する想像力」
「技術力」の継承は「新設時の技術的な思想」
これらは、専門書では学べません
しかし、全職員で取り組んでいく姿勢が見えています。
この他にも課題や問題はありますが
「一事が万事」
難しい課題に真に取り組めば
日常的な課題の解決方法は自然に見えてくると思っています。
今年の課題の整理と現在の状況の報告です。
今年の、企業団として取り組んでいることは2点
1点目は、長期財政計画
このことは、将来の「東部水道企業団としてのあり方」を描き
それに対する課題と準備を行なうとの側面と
中期的な財政計画の見通しをたてるの二つが主な主旨です
その都度ご報告しているように、作業は順調です。
2点目は、「技術の継承」
団塊の世代に引き続き
企業団設立時の経験豊富な職員の退職が今後も続きます
この「技術力」「経験力」それに「経営力」の継承が必須です。
もちろん、あとを引き継ぐ職員も育っています
特にお願いしたいのは
「経験力」の継承は「過去の失敗事例に学ぶ」
「経営力」の継承は「将来に対する想像力」
「技術力」の継承は「新設時の技術的な思想」
これらは、専門書では学べません
しかし、全職員で取り組んでいく姿勢が見えています。
この他にも課題や問題はありますが
「一事が万事」
難しい課題に真に取り組めば
日常的な課題の解決方法は自然に見えてくると思っています。
2013年10月07日
無線機の点検
現在、携帯電話が普及し、業務においても
通常の連絡には携帯電話を利用しています。
しかし、災害等の緊急時には
携帯電話がつながり難くなることが懸念されていますので
東部水道企業団では、無線機を設置しています。
使用頻度が低いことから、故障に気付かず
いざ使おうとした際に使えなかったという恐れもあります。
1か月に1度
車両点検の際に簡単な動作確認を行っていますが
それとは別に、年に1回全ての無線機を対象として
正常に作動するかの一斉点検を行っています。
先日、東部水道企業団の防災訓練を前に
その点検作業を行いました。

(写真:本庁舎に設置した固定局からの交信点検)

(写真:車載型の移動局からの交信点検)

(写真:持ち運びが可能な携帯型も設置しています)
幸いなことに、今回は故障した無線機はありませんでした。
しかし、機器の中には長年使用してきているものが多く
点検で故障を発見できたケースも多かったことから
今後も安心して利用できるように、定期的な点検を心がけます。
通常の連絡には携帯電話を利用しています。
しかし、災害等の緊急時には
携帯電話がつながり難くなることが懸念されていますので
東部水道企業団では、無線機を設置しています。
使用頻度が低いことから、故障に気付かず
いざ使おうとした際に使えなかったという恐れもあります。
1か月に1度
車両点検の際に簡単な動作確認を行っていますが
それとは別に、年に1回全ての無線機を対象として
正常に作動するかの一斉点検を行っています。
先日、東部水道企業団の防災訓練を前に
その点検作業を行いました。
(写真:本庁舎に設置した固定局からの交信点検)
(写真:車載型の移動局からの交信点検)
(写真:持ち運びが可能な携帯型も設置しています)
幸いなことに、今回は故障した無線機はありませんでした。
しかし、機器の中には長年使用してきているものが多く
点検で故障を発見できたケースも多かったことから
今後も安心して利用できるように、定期的な点検を心がけます。
2013年10月04日
電算のシステム
会計制度が大幅に変わることや
複数の電算システムが更新の時期がすでに過ぎている状態にある。
もちろん大事に、少々我慢して使用してきた結果ですが
「大事に使う」も重要だが
「危ない状況」では利用者の方々に迷惑をかける。

(写真:現在の電算システム)
この際、電算システムを「見直そう」
との主旨で委員会を立ち上げ議論中と以前報告していました
その電算システム更新の検討委員会の報告です。
具体的に、しかも専門的に議論がなされました
職員の中には、専門的な知識・技能を持った人も多く
濃密な議論となったようです。
蛇足ですが、私は電算・しかもシステムは「からきし駄目」
ネコに小判状態です
だから、なおさら
専門的な知識を有する職員がまぶしく見えます。
さて、議論の末に出された結論は
1)独自でシステムを作ると、特定の職員が将来にわたり関わりが生じ
また、責任を負うことになるため、市販のパッケージを導入する。
2)本庁舎、営業所、浄水場をつなぎ
最新のソフトを使用できるネットワークを構築する。
3)省スペース化とパソコンの二重投資を防ぐよう
現在使っているパソコンを利用したシステムとする。
4)個人情報を取り扱うため、セキュリティーを強化する。
5)お客様の大事な情報を取扱う水道料金システムは
基幹システムとして、別のシステムを構築する。
ということです
良くやってくれました。
複数の電算システムが更新の時期がすでに過ぎている状態にある。
もちろん大事に、少々我慢して使用してきた結果ですが
「大事に使う」も重要だが
「危ない状況」では利用者の方々に迷惑をかける。
(写真:現在の電算システム)
この際、電算システムを「見直そう」
との主旨で委員会を立ち上げ議論中と以前報告していました
その電算システム更新の検討委員会の報告です。
具体的に、しかも専門的に議論がなされました
職員の中には、専門的な知識・技能を持った人も多く
濃密な議論となったようです。
蛇足ですが、私は電算・しかもシステムは「からきし駄目」
ネコに小判状態です
だから、なおさら
専門的な知識を有する職員がまぶしく見えます。
さて、議論の末に出された結論は
1)独自でシステムを作ると、特定の職員が将来にわたり関わりが生じ
また、責任を負うことになるため、市販のパッケージを導入する。
2)本庁舎、営業所、浄水場をつなぎ
最新のソフトを使用できるネットワークを構築する。
3)省スペース化とパソコンの二重投資を防ぐよう
現在使っているパソコンを利用したシステムとする。
4)個人情報を取り扱うため、セキュリティーを強化する。
5)お客様の大事な情報を取扱う水道料金システムは
基幹システムとして、別のシステムを構築する。
ということです
良くやってくれました。
2013年10月03日
石巻市と周辺の現状
石巻の朝一番、隣町の女川港へ
「街がない」
声が出ません。

(写真:「女川港」の現状)
見えるものは 当時のすさまじさを想像させる物のみ
コンクリートの建物が横倒し、その方向がバラバラ
押し波と引き波の仕業だそうです。
その日の天気は快晴
天高くどこまでも青い空と海
海はナギで、カモメは羽を休めている、一見のどかな風景

(写真:津波の引き波により転倒した鉄筋コンクリート4階建ての建物
建物内部に乗用車が残されていました)
しかし、この落差が現実
頭を下げ、祈るほかに所作がない
伝える言葉も、これ以上浮かびません。
その後は石巻に戻り、震災を伝えるボランティアさんの案内
その方は、観光協会の専務理事の浅野さん
地震当日は、職場(石巻駅前)
3・11 14時46分 地震
「揺れた 四つん這い状態 長い長い揺れ(実際は3分)
これは津波が来る」と直感
3日間は、職場の2階から出られない状態で過ごす
4日後に親戚を探すために避難所まわり
歩く所はガレキの山
片づけるには「1年かかる」と思った
しかし、ボランティアの力を頂き、3か月で片付き
その頃コンビニ1軒が店開き
ボランティアセンター把握が30万人
実際は「その倍以上の方が全国から駆けつけてくださった」

(写真:震災を伝えるボランティアさんの案内)
石巻の被害の規模は大きい
東北3県のガレキ量の半分は石巻と聞いた。
15万人の市民の8割が被災され、車の流失6万台
亡くなった方4千人。

(写真:見渡す限りの住宅地が無くなり、更地となっていました)
ただし「地震 そく津波 そく逃げろ」の訓練は徹底していた
だから被害の割には「助かった人が多い」とも。
助からなかった人の原因は大まかに二つ
ひとつは、車の大渋滞で被災
ふたつめは、家に戻って被災。
犠牲になったニュースはよく流れる
しかし、助かったニュースがない
「助かるには理由がある」と強調された。
ある保育園では、月に1回の訓練を数十年続け、全員助かった
あとで聞けば「見事な行動だった」とのお話も。
最後に「津波はテンデン」
まずは、自分が逃げろ。
次には逃げる場所を決めておけ
その場所を家族で共有、探すのが簡単
このことは、東北地方では日頃から共有されているとのことでした。
1~2年後に再度行きたい
復興の姿を見に行きたい。
「街がない」
声が出ません。
(写真:「女川港」の現状)
見えるものは 当時のすさまじさを想像させる物のみ
コンクリートの建物が横倒し、その方向がバラバラ
押し波と引き波の仕業だそうです。
その日の天気は快晴
天高くどこまでも青い空と海
海はナギで、カモメは羽を休めている、一見のどかな風景
(写真:津波の引き波により転倒した鉄筋コンクリート4階建ての建物
建物内部に乗用車が残されていました)
しかし、この落差が現実
頭を下げ、祈るほかに所作がない
伝える言葉も、これ以上浮かびません。
その後は石巻に戻り、震災を伝えるボランティアさんの案内
その方は、観光協会の専務理事の浅野さん
地震当日は、職場(石巻駅前)
3・11 14時46分 地震
「揺れた 四つん這い状態 長い長い揺れ(実際は3分)
これは津波が来る」と直感
3日間は、職場の2階から出られない状態で過ごす
4日後に親戚を探すために避難所まわり
歩く所はガレキの山
片づけるには「1年かかる」と思った
しかし、ボランティアの力を頂き、3か月で片付き
その頃コンビニ1軒が店開き
ボランティアセンター把握が30万人
実際は「その倍以上の方が全国から駆けつけてくださった」
(写真:震災を伝えるボランティアさんの案内)
石巻の被害の規模は大きい
東北3県のガレキ量の半分は石巻と聞いた。
15万人の市民の8割が被災され、車の流失6万台
亡くなった方4千人。
(写真:見渡す限りの住宅地が無くなり、更地となっていました)
ただし「地震 そく津波 そく逃げろ」の訓練は徹底していた
だから被害の割には「助かった人が多い」とも。
助からなかった人の原因は大まかに二つ
ひとつは、車の大渋滞で被災
ふたつめは、家に戻って被災。
犠牲になったニュースはよく流れる
しかし、助かったニュースがない
「助かるには理由がある」と強調された。
ある保育園では、月に1回の訓練を数十年続け、全員助かった
あとで聞けば「見事な行動だった」とのお話も。
最後に「津波はテンデン」
まずは、自分が逃げろ。
次には逃げる場所を決めておけ
その場所を家族で共有、探すのが簡単
このことは、東北地方では日頃から共有されているとのことでした。
1~2年後に再度行きたい
復興の姿を見に行きたい。