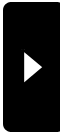2012年10月31日
浮羽上流の袋野堰
それまで筑後川の水を使うことができないと思われていた土地でも、
大石長野水道の成功により、
水田を広げようとする機運が高まってきました。
近郊浮羽の中・下流域では、豊かな筑後川の水が
利用できるようになったものの、
その上流、大石堰の近くの大石、三春あたりでは依然として
水不足に悩まされていました。
そこで、地元の庄屋田代親子は、
より上流の豊前と筑後の国境あたりから水を引く計画を立てました。
しかし、一帯は、筑後川最大の難所と言われた場所であり、
両側に山肌が迫り、水路といっても、山の中の岩盤を
二キロもトンネルを掘り進む必要がありました。
もちろん当時は土木機械もありませんから、
ノミとツルハシで掘り進むしかありません。
その上、山田堰や大石堰は、
地元農民からの強い請願はあったものの
藩の事業でしたが、この袋野堰については、
藩が庄屋に金を貸すだけという、
いわば庄屋の個人事業でした。
この事業は、難工事ではありましたが、
約三か月でトンネルを掘りあげ、堰を設けることで、
下流の台地に水を潤すことができるようになりました。

(写真:トンネルの出口)
その袋野堰も、今では夜明ダムの湖面の下に沈んでいますが、
当時のトンネルと用水路は
今でも立派に現役で周辺の田畑を潤しています。

(写真:満々と水を湛えた夜明ダム)

(写真:堰は沈んで見えませんが、取水口があります)

(写真:夜明ダムは、九州電力の発電専用ダム)

(写真:ダムのすぐ下流には大雨の時は水没する橋)
その後ろには久留米市と大分市を結ぶ九大本線
九大本線が「筑後川」を渡るのはこの場所だけです。
(日田市から上流は玖珠川と呼ばれているため)

(写真:「道の駅うきは」からみた豊かな実りの大地)
撮影に訪れたのは10月上旬
一部では稲刈りも始まっている季節でした。
大石長野水道の成功により、
水田を広げようとする機運が高まってきました。
近郊浮羽の中・下流域では、豊かな筑後川の水が
利用できるようになったものの、
その上流、大石堰の近くの大石、三春あたりでは依然として
水不足に悩まされていました。
そこで、地元の庄屋田代親子は、
より上流の豊前と筑後の国境あたりから水を引く計画を立てました。
しかし、一帯は、筑後川最大の難所と言われた場所であり、
両側に山肌が迫り、水路といっても、山の中の岩盤を
二キロもトンネルを掘り進む必要がありました。
もちろん当時は土木機械もありませんから、
ノミとツルハシで掘り進むしかありません。
その上、山田堰や大石堰は、
地元農民からの強い請願はあったものの
藩の事業でしたが、この袋野堰については、
藩が庄屋に金を貸すだけという、
いわば庄屋の個人事業でした。
この事業は、難工事ではありましたが、
約三か月でトンネルを掘りあげ、堰を設けることで、
下流の台地に水を潤すことができるようになりました。
(写真:トンネルの出口)
その袋野堰も、今では夜明ダムの湖面の下に沈んでいますが、
当時のトンネルと用水路は
今でも立派に現役で周辺の田畑を潤しています。
(写真:満々と水を湛えた夜明ダム)
(写真:堰は沈んで見えませんが、取水口があります)
(写真:夜明ダムは、九州電力の発電専用ダム)
(写真:ダムのすぐ下流には大雨の時は水没する橋)
その後ろには久留米市と大分市を結ぶ九大本線
九大本線が「筑後川」を渡るのはこの場所だけです。
(日田市から上流は玖珠川と呼ばれているため)
(写真:「道の駅うきは」からみた豊かな実りの大地)
撮影に訪れたのは10月上旬
一部では稲刈りも始まっている季節でした。
2012年10月30日
浮羽地方の大石堰
最初の山田堰の翌年1664年に作られたのが大石堰です。
筑後川の左岸側にある浮羽地方も目の前に筑後川は流れるものの、
水利的に上にある田畑に水を潤すことができないことから、
当時、五人の庄屋が、上流に堰を作って水を田畑に引くことを計画し、
久留米藩に請願しました。
これが五庄屋物語と言われるもので、
藩営事業として取り組むこととなったものの、
工事が失敗したら責任をとって磔獄門に処されることになり、
工事現場には五本の磔柱が立てられました。

(写真:磔柱が立てられた場所に五庄屋遺跡があります)
工事は60日間程で見事に完成し、
多くの田畑が筑後川の豊かな水で潤されることとなり、
うきは市の江南小学校では、今でも
五庄屋を讃える歌が校歌とされているほどです。

(写真:現在の大石堰 水量が少ない時は穏やかな流れ)
江戸時代の大石堰は、山田堰同様の斜めの石畳堰であり、
約300年間、多くの水害に耐えて地域の農業を支えてきましたが、
昭和28年の大水害により破壊され流出してしまい、
現在では固定式のコンクリート堰に作り替えられています。

(写真:取水口あたり その右側が五庄屋遺跡)

(写真:取水口のある道路の下流側)
見て頂ければおわかりでしょうが、かなりの高低差があり、
隣接する農地に水を届けることは難しい状況でした。
なので、堰のある地域では水が使えない・・・
そんな記事は次回になります。

(写真:水路は豊かな水を運んでいました)
また、大石水道は、途中隈上川を横断することになり
当時は、別に長野堰を作って水利を有効活用していたそうです。
しかし、現在では川の下を通るサイフォンが作られています。
そのサイフォンの出口に長野水神社がありました。

(写真:隈上川と長野水神社 この下に水路があります)

(写真:水路の出口 10月に撮影したので水量もそこまでありません)
この大石堰から水を引く大石長野水道の水運により、
吉井町は農業だけでなく、酒、油、櫨蝋(はぜろう)等の
商品作物の集積地となり大きく発展し、
今でも白壁の町として当時のたたずまいを残しています。

(写真:国道210号線沿いにある白壁の建物)
筑後川の左岸側にある浮羽地方も目の前に筑後川は流れるものの、
水利的に上にある田畑に水を潤すことができないことから、
当時、五人の庄屋が、上流に堰を作って水を田畑に引くことを計画し、
久留米藩に請願しました。
これが五庄屋物語と言われるもので、
藩営事業として取り組むこととなったものの、
工事が失敗したら責任をとって磔獄門に処されることになり、
工事現場には五本の磔柱が立てられました。
(写真:磔柱が立てられた場所に五庄屋遺跡があります)
工事は60日間程で見事に完成し、
多くの田畑が筑後川の豊かな水で潤されることとなり、
うきは市の江南小学校では、今でも
五庄屋を讃える歌が校歌とされているほどです。
(写真:現在の大石堰 水量が少ない時は穏やかな流れ)
江戸時代の大石堰は、山田堰同様の斜めの石畳堰であり、
約300年間、多くの水害に耐えて地域の農業を支えてきましたが、
昭和28年の大水害により破壊され流出してしまい、
現在では固定式のコンクリート堰に作り替えられています。
(写真:取水口あたり その右側が五庄屋遺跡)
(写真:取水口のある道路の下流側)
見て頂ければおわかりでしょうが、かなりの高低差があり、
隣接する農地に水を届けることは難しい状況でした。
なので、堰のある地域では水が使えない・・・
そんな記事は次回になります。
(写真:水路は豊かな水を運んでいました)
また、大石水道は、途中隈上川を横断することになり
当時は、別に長野堰を作って水利を有効活用していたそうです。
しかし、現在では川の下を通るサイフォンが作られています。
そのサイフォンの出口に長野水神社がありました。
(写真:隈上川と長野水神社 この下に水路があります)
(写真:水路の出口 10月に撮影したので水量もそこまでありません)
この大石堰から水を引く大石長野水道の水運により、
吉井町は農業だけでなく、酒、油、櫨蝋(はぜろう)等の
商品作物の集積地となり大きく発展し、
今でも白壁の町として当時のたたずまいを残しています。

(写真:国道210号線沿いにある白壁の建物)
2012年10月29日
朝倉の山田堰について
筑後川中流域に位置する朝倉町では、江戸時代初めまでは、
谷間から湧き出る小川からの水を利用したわずかな水田を除くと、
石ころまじりの砂地だけだったそうです。
1663年に恵蘇八幡宮のすぐ前を流れる筑後川右岸に水門を設け、
最初の堰と堀川用水が開かれ、田畑を潤すことが出来るようになりました。
その後、たび重なる水害で水路に土砂が堆積し干ばつも起き、
また、水田化が進むにつれより多くの水が必要とされてきました。
そこで、1790年堀川の恩人「古賀百工」により堰の大改修が行われ
筑後川を斜めに堰止める石張りの山田堰が誕生しました。

(写真:山田堰の上流部 後には恵蘇八幡宮と木の丸公園)

(写真:堰の中央部、中央奥の青い所は取水口)

(写真:向いには水神社と大楠、土地改良区もここにあります)

(写真:水神社側から撮影 石畳の上を水が流れて行きます)
また、取水口についても、岩盤を切り開き、より広い
切貫水門(トンネル)とし、十分な水量を得ることができるようになり、
新掘川用水と併せて多くの新田が開発されました。
山田堰は、昭和28年の大水害においても流出しませんでしたが、
その後昭和55年の水害で多くが被災したため、
在石使用、総張石コンクリート造りによる原形復旧工事として
大改修がなされています。
筑後川の水量が少ない時は、水は船通しや水吐通しを流れ、
多い時は堰の上をさざ波を立てて水が流れており、
今でもその美しいたたずまいを残しています。

(写真:神社側から雨上がりに撮影)
朝倉と言えば三連水車ですが、今でも、江戸時代同様に
この堀川用水によって導かれた豊かな水を水車で
田畑に汲み上げています。

(写真:堀川用水の説明パネル)
全国的には水車からポンプに切り替わる中、
朝倉の水車群については、貴重な歴史的農業遺産を守ろうと
農家の理解により220年間存続しているとのことです。

(写真:有名な朝倉の三連水車 高速山田SAのすぐ近く)
水車は農地に水が必要な5月から10月までの間だけ
実際に動いています。

(写真:二連水車でも勢いよく水が汲み上げられていました)
道の駅三連水車の里では、電動にはなりますが、
一年中動いている三連水車があり
山田堰にまつわる歴史、現在でも手作りされている三連水車の
様子等をビデオで見ることができます。
谷間から湧き出る小川からの水を利用したわずかな水田を除くと、
石ころまじりの砂地だけだったそうです。
1663年に恵蘇八幡宮のすぐ前を流れる筑後川右岸に水門を設け、
最初の堰と堀川用水が開かれ、田畑を潤すことが出来るようになりました。
その後、たび重なる水害で水路に土砂が堆積し干ばつも起き、
また、水田化が進むにつれより多くの水が必要とされてきました。
そこで、1790年堀川の恩人「古賀百工」により堰の大改修が行われ
筑後川を斜めに堰止める石張りの山田堰が誕生しました。
(写真:山田堰の上流部 後には恵蘇八幡宮と木の丸公園)
(写真:堰の中央部、中央奥の青い所は取水口)
(写真:向いには水神社と大楠、土地改良区もここにあります)
(写真:水神社側から撮影 石畳の上を水が流れて行きます)
また、取水口についても、岩盤を切り開き、より広い
切貫水門(トンネル)とし、十分な水量を得ることができるようになり、
新掘川用水と併せて多くの新田が開発されました。
山田堰は、昭和28年の大水害においても流出しませんでしたが、
その後昭和55年の水害で多くが被災したため、
在石使用、総張石コンクリート造りによる原形復旧工事として
大改修がなされています。
筑後川の水量が少ない時は、水は船通しや水吐通しを流れ、
多い時は堰の上をさざ波を立てて水が流れており、
今でもその美しいたたずまいを残しています。

(写真:神社側から雨上がりに撮影)
朝倉と言えば三連水車ですが、今でも、江戸時代同様に
この堀川用水によって導かれた豊かな水を水車で
田畑に汲み上げています。
(写真:堀川用水の説明パネル)
全国的には水車からポンプに切り替わる中、
朝倉の水車群については、貴重な歴史的農業遺産を守ろうと
農家の理解により220年間存続しているとのことです。
(写真:有名な朝倉の三連水車 高速山田SAのすぐ近く)
水車は農地に水が必要な5月から10月までの間だけ
実際に動いています。
(写真:二連水車でも勢いよく水が汲み上げられていました)
道の駅三連水車の里では、電動にはなりますが、
一年中動いている三連水車があり
山田堰にまつわる歴史、現在でも手作りされている三連水車の
様子等をビデオで見ることができます。
2012年10月26日
両筑平野用水事業と佐賀東部水道企業団
両筑平野用水事業といっても、関係者以外の方には
なかなか分かりにくいかと思います。
両筑平野とは二つの平野を併せて呼んでいるわけではなく、
ひとつの平野の地名だそうです。
福岡県の耳納山麓北側、その両側に筑後川が流れる一帯が、
筑前黒田藩と筑後有馬藩の両方にまたがることから、
そう呼ばれてきたのかもしれません。

(写真:筑後川の中流、山の向こうは大分県日田市)
「両筑」については、大正から昭和初期にかけて、
田主丸と甘木、朝倉を結ぶ鉄道路線、両筑軌道があり、
バス事業としては、最近まで西鉄バス両筑の名称が残っていました。
また、筑後川にかかる両筑橋としては今でも名前が残っていますし、
筑後川も以前は両筑川と呼ばれた時代があるそうです。
その両筑平野用水事業は、朝倉市、筑前町、小郡市、太刀洗町へ
農業用水を送るとともに、
佐賀・福岡両県に都市用水を確保するための事業です。
その基幹施設が江川ダムであり、農業用水と都市用水の共同施設ですから、
当企業団では、江川ダム及びその関連施設について費用を負担しています。

(写真:江川ダムを上空から撮影)
東部水道企業団と両筑平野用水事業の関わりについてご紹介する前に、
筑後川中流域の農業用水確保の歴史について、
これから何回かに分けて簡単にご紹介していきたいと思います。
今回のシリーズ記事はブログ事務局の総務課が担当しています。
----------------------------------
筑後川は阿蘇外輪山に源を発し、
熊本県、大分県、福岡県、佐賀県にまたがる九州随一の河川ですが、
豊富な水量ゆえに何度も氾濫を繰り返す「暴れ川」であり、
その周辺の土地は田畑としての利用が難しく、
葦や柳が茂る貧しい農地でした。
そのような状況の中、戦国時代の築城などにより土木技術も発展、
1600年代半ばからは、堰や水路、堤防の整備が進んできました。
筑後川中流域には、筑後川四堰と呼ばれる
江戸時代からの堰があります。(うち袋野堰はダムに水没)
建設された順に、山田堰、大石堰、袋野堰、恵利堰(床島堰)で、
上流から言えば袋野堰、大石堰、山田堰、恵利堰となります。

(写真:朝倉市杷木町の高台から望む実りの大地と筑後川)
これらの堰や水路は、今でも現役として大切に利用され
地域の農業に貢献しています。
次回からは、それぞれの堰についてご紹介していきます。
なお、市町村名については、
合併前の名称でご紹介する場合もありますのでご了解ください。
なかなか分かりにくいかと思います。
両筑平野とは二つの平野を併せて呼んでいるわけではなく、
ひとつの平野の地名だそうです。
福岡県の耳納山麓北側、その両側に筑後川が流れる一帯が、
筑前黒田藩と筑後有馬藩の両方にまたがることから、
そう呼ばれてきたのかもしれません。
(写真:筑後川の中流、山の向こうは大分県日田市)
「両筑」については、大正から昭和初期にかけて、
田主丸と甘木、朝倉を結ぶ鉄道路線、両筑軌道があり、
バス事業としては、最近まで西鉄バス両筑の名称が残っていました。
また、筑後川にかかる両筑橋としては今でも名前が残っていますし、
筑後川も以前は両筑川と呼ばれた時代があるそうです。
その両筑平野用水事業は、朝倉市、筑前町、小郡市、太刀洗町へ
農業用水を送るとともに、
佐賀・福岡両県に都市用水を確保するための事業です。
その基幹施設が江川ダムであり、農業用水と都市用水の共同施設ですから、
当企業団では、江川ダム及びその関連施設について費用を負担しています。

(写真:江川ダムを上空から撮影)
東部水道企業団と両筑平野用水事業の関わりについてご紹介する前に、
筑後川中流域の農業用水確保の歴史について、
これから何回かに分けて簡単にご紹介していきたいと思います。
今回のシリーズ記事はブログ事務局の総務課が担当しています。
----------------------------------
筑後川は阿蘇外輪山に源を発し、
熊本県、大分県、福岡県、佐賀県にまたがる九州随一の河川ですが、
豊富な水量ゆえに何度も氾濫を繰り返す「暴れ川」であり、
その周辺の土地は田畑としての利用が難しく、
葦や柳が茂る貧しい農地でした。
そのような状況の中、戦国時代の築城などにより土木技術も発展、
1600年代半ばからは、堰や水路、堤防の整備が進んできました。
筑後川中流域には、筑後川四堰と呼ばれる
江戸時代からの堰があります。(うち袋野堰はダムに水没)
建設された順に、山田堰、大石堰、袋野堰、恵利堰(床島堰)で、
上流から言えば袋野堰、大石堰、山田堰、恵利堰となります。
(写真:朝倉市杷木町の高台から望む実りの大地と筑後川)
これらの堰や水路は、今でも現役として大切に利用され
地域の農業に貢献しています。
次回からは、それぞれの堰についてご紹介していきます。
なお、市町村名については、
合併前の名称でご紹介する場合もありますのでご了解ください。
2012年10月25日
平成24年度「無線点検」
東部水道企業団では
災害時の連絡に備えて、無線機を設置しています。
先日、所有する無線機が正常に作動するか
一斉点検作業を行いました。
その内容等について、ご紹介します。
---(参加の職員より)------------------
平成16年1月の電波法規制緩和により
それまで毎年行っていた法定点検が
5年に1度の頻度となりました。
災害時や台風による停電等で電話が使用できなくなった時、
無線が活躍します。
しかし、イザという時に作動せず連絡がとれないでは
話になりません。
そこで、1か月に1度行っている車両点検時の
簡単な動作確認とは別に
年に1度、無線のみの一斉点検を行っています。

(写真:本庁舎内に設置した固定局からの交信点検の様子)
東部水道企業団の無線エリア内には山があり
アンテナが高い場所に設置されている固定局どうしの
交信は可能ですが、
車に設置した移動局との交信は、山に遮られたり
建物の陰になったりして通じないときもあります。
そこを考慮した上で、実際に交信を行い
受信・送信の状態を確認します。

(写真:車載型の移動局からの交信点検の様子)
携帯タイプも含め、全部で34台
機器の中にはかなりの年季物があり、大事に使っています。
それでも、使用頻度に応じて故障は起こります
昨年10月、北茂安浄水場に設置している基地局が故障。
重要な施設のため、すぐに修理を実施しました。
今回の点検で不備があった機器は5台
重要度、使用頻度を考慮して修理を検討しますが
形式が古く修理部品がないものは修理不能。
費用対効果、危機管理上などから
今後はどうして行くか?検討を要します。
災害時の連絡に備えて、無線機を設置しています。
先日、所有する無線機が正常に作動するか
一斉点検作業を行いました。
その内容等について、ご紹介します。
---(参加の職員より)------------------
平成16年1月の電波法規制緩和により
それまで毎年行っていた法定点検が
5年に1度の頻度となりました。
災害時や台風による停電等で電話が使用できなくなった時、
無線が活躍します。
しかし、イザという時に作動せず連絡がとれないでは
話になりません。
そこで、1か月に1度行っている車両点検時の
簡単な動作確認とは別に
年に1度、無線のみの一斉点検を行っています。
(写真:本庁舎内に設置した固定局からの交信点検の様子)
東部水道企業団の無線エリア内には山があり
アンテナが高い場所に設置されている固定局どうしの
交信は可能ですが、
車に設置した移動局との交信は、山に遮られたり
建物の陰になったりして通じないときもあります。
そこを考慮した上で、実際に交信を行い
受信・送信の状態を確認します。
(写真:車載型の移動局からの交信点検の様子)
携帯タイプも含め、全部で34台
機器の中にはかなりの年季物があり、大事に使っています。
それでも、使用頻度に応じて故障は起こります
昨年10月、北茂安浄水場に設置している基地局が故障。
重要な施設のため、すぐに修理を実施しました。
今回の点検で不備があった機器は5台
重要度、使用頻度を考慮して修理を検討しますが
形式が古く修理部品がないものは修理不能。
費用対効果、危機管理上などから
今後はどうして行くか?検討を要します。
2012年10月24日
(独)水資源機構より講師を迎えての勉強会
私たちは、筑後川の水を頂いて水道事業を行っています
その筑後川を知ることが仕事の原点です。
「筑後川流域情報共有懇話会」という会議があります
そこでの大きな課題のひとつが
「過去の経緯の確認とその継承」でした。
その会議の折「筑後川総合開発」の現場における
中心的な役割を担ってこられた
独立行政法人水資源機構の恒吉上席審議役の
お話を聞く機会がありました。
私は感銘をうけ
再度、しかも東部水道企業団の全職員に聞かせたいと思い
その場でお願いして、先日それが実現しました。

(写真:講師をお引受いただいた「(独)水資源機構の恒吉上席審議役」)
筑後川利水経緯勉強会「筑後川と筑後川総合開発」
という演題で講演をお願いしました。

(写真:プロジェクタを利用した講演会の様子)
講演は3時間びっしり
通常ならば、一方的に話を聞く時間としては長いです。
しかし、何人かの職員に聞いたところでは好評でした
私自身も新しい発見や示唆をたくさん頂きました。

(写真:講演に聞き入る参加者の面々)
「筑後川の概要や利活用」等は、別の機会に紹介します。
ここでは
「筑後大堰の建設時のいきさつ」をまず紹介します。
この「大堰」は
筑後川の「水管理」の重要な施設
その建設の経過は
建設計画に対し、下流の関係団体は反対表明
理由は、漁場、特に海苔養殖への影響。
ここで、当時の背景で見逃せないことがふたつ
ひとつは福岡市の大渇水
昭和53年のこと
287日間の給水制限、最大19時間断水
45,000世帯が完全断水という状況に見舞われた。
当然、世論は
「福岡都市圏に早く水を」が加速
二つ目は福岡・佐賀の漁連
有明海の海苔養殖を「浮揚の力」としたい
という強い思い。
海苔養殖には、栄養を含んだ河川の水が必須条件
ここで対立
限られた筑後川の水
「流域外の福岡都市圏にやる」なんて論外との主張。
こういう背景の中での筑後大堰計画
簡単なことではなかったことは容易に想像されます。
事業進捗の立場で
本体着工に踏み切った
結果、現地で漁民700名と対立。
夕方「一時工事中止」の決定
それから1年9か月間ストップ状態が続いた。
関係者の度重なる協議の結果
昭和55年
利水活用に関する合意が交わされた。
合意内容は、毎秒40m3の流下量を常時確保
それを実現できない場合には、ダムより放流する。

(写真:熱心に講演していただき、ありがとうございます)
その結果、昭和55年12月に工事再開
昭和59年完成。
このことを踏まえても
下流漁業者や農業者への日常的な情報開示と
「日頃のお付き合い」がいかに大事なことかと再認識しました。
新規都市用水の利水者は、筑後川に毎秒40m3以上の流下量
があれば取水可能、それ以下の場合にはダムより放流し
その上で頂く、のがルール。
だから筑後川には水が満々と流れていても
毎秒40m3を確保できないと「渇水」という事態が起こります
このことは別の機会とします。
恒吉氏の説明主旨は
「下流との話し合いを継続し情報の共有を図る」
そして
「河川や有明海の環境にきめ細かく配慮する」の
一点だったと理解しました。
その筑後川を知ることが仕事の原点です。
「筑後川流域情報共有懇話会」という会議があります
そこでの大きな課題のひとつが
「過去の経緯の確認とその継承」でした。
その会議の折「筑後川総合開発」の現場における
中心的な役割を担ってこられた
独立行政法人水資源機構の恒吉上席審議役の
お話を聞く機会がありました。
私は感銘をうけ
再度、しかも東部水道企業団の全職員に聞かせたいと思い
その場でお願いして、先日それが実現しました。
(写真:講師をお引受いただいた「(独)水資源機構の恒吉上席審議役」)
筑後川利水経緯勉強会「筑後川と筑後川総合開発」
という演題で講演をお願いしました。

(写真:プロジェクタを利用した講演会の様子)
講演は3時間びっしり
通常ならば、一方的に話を聞く時間としては長いです。
しかし、何人かの職員に聞いたところでは好評でした
私自身も新しい発見や示唆をたくさん頂きました。
(写真:講演に聞き入る参加者の面々)
「筑後川の概要や利活用」等は、別の機会に紹介します。
ここでは
「筑後大堰の建設時のいきさつ」をまず紹介します。
この「大堰」は
筑後川の「水管理」の重要な施設
その建設の経過は
建設計画に対し、下流の関係団体は反対表明
理由は、漁場、特に海苔養殖への影響。
ここで、当時の背景で見逃せないことがふたつ
ひとつは福岡市の大渇水
昭和53年のこと
287日間の給水制限、最大19時間断水
45,000世帯が完全断水という状況に見舞われた。
当然、世論は
「福岡都市圏に早く水を」が加速
二つ目は福岡・佐賀の漁連
有明海の海苔養殖を「浮揚の力」としたい
という強い思い。
海苔養殖には、栄養を含んだ河川の水が必須条件
ここで対立
限られた筑後川の水
「流域外の福岡都市圏にやる」なんて論外との主張。
こういう背景の中での筑後大堰計画
簡単なことではなかったことは容易に想像されます。
事業進捗の立場で
本体着工に踏み切った
結果、現地で漁民700名と対立。
夕方「一時工事中止」の決定
それから1年9か月間ストップ状態が続いた。
関係者の度重なる協議の結果
昭和55年
利水活用に関する合意が交わされた。
合意内容は、毎秒40m3の流下量を常時確保
それを実現できない場合には、ダムより放流する。
(写真:熱心に講演していただき、ありがとうございます)
その結果、昭和55年12月に工事再開
昭和59年完成。
このことを踏まえても
下流漁業者や農業者への日常的な情報開示と
「日頃のお付き合い」がいかに大事なことかと再認識しました。
新規都市用水の利水者は、筑後川に毎秒40m3以上の流下量
があれば取水可能、それ以下の場合にはダムより放流し
その上で頂く、のがルール。
だから筑後川には水が満々と流れていても
毎秒40m3を確保できないと「渇水」という事態が起こります
このことは別の機会とします。
恒吉氏の説明主旨は
「下流との話し合いを継続し情報の共有を図る」
そして
「河川や有明海の環境にきめ細かく配慮する」の
一点だったと理解しました。
2012年10月23日
今年の重点目標「危機管理」の中間報告
重点目標のひとつ「危機管理体制の強化」の
中間報告です。
具体的には
仮に危機に遭遇しても「水道水が出ない」を最小限におさえる
その対策をまずは考える、でした。
つい最近「南海巨大地震」の被害想定が発表されました
最大の死者数が32.3万人
もちろん最悪の場合の想定ですが「愕然とします」
佐賀県域に対する被害は少ないようですが
地震の可能性は
南海地震のみでは、もちろんありません。
私たち東部水道企業団で想定している
「震度6強」でも、相当の被害がでることが想定されます。
で、どうする?
中・長期的には、本ブログでの検討シナリオを
皆様にご報告しましたが
そのとおりの考えで整備を進めたいと考えています。
短期的には、例えば「明日」だったらどうする
が、課題のひとつです。
「震度6強」では
被害があり、水道管の破損も生じます。
その場合は「復旧体制」と「応急給水対策」が急務です
具体的な「段取り」を議論中です。

(写真:平成23年度防災訓練「応急給水栓」からの給水状況)
うちの「水道技術管理者」は自信をもって言い切ります
「職員は、全力で対処します」
「そのためにも、訓練は欠かせません」
私もそう思います
が、心配なことがあります。
職員だけでの対応には限度があります
応援体制の構築と
「応急給水対策」に対する給水車の配備は必須です。
この仕事は、私の責任です。
中間報告です。
具体的には
仮に危機に遭遇しても「水道水が出ない」を最小限におさえる
その対策をまずは考える、でした。
つい最近「南海巨大地震」の被害想定が発表されました
最大の死者数が32.3万人
もちろん最悪の場合の想定ですが「愕然とします」
佐賀県域に対する被害は少ないようですが
地震の可能性は
南海地震のみでは、もちろんありません。
私たち東部水道企業団で想定している
「震度6強」でも、相当の被害がでることが想定されます。
で、どうする?
中・長期的には、本ブログでの検討シナリオを
皆様にご報告しましたが
そのとおりの考えで整備を進めたいと考えています。
短期的には、例えば「明日」だったらどうする
が、課題のひとつです。
「震度6強」では
被害があり、水道管の破損も生じます。
その場合は「復旧体制」と「応急給水対策」が急務です
具体的な「段取り」を議論中です。
(写真:平成23年度防災訓練「応急給水栓」からの給水状況)
うちの「水道技術管理者」は自信をもって言い切ります
「職員は、全力で対処します」
「そのためにも、訓練は欠かせません」
私もそう思います
が、心配なことがあります。
職員だけでの対応には限度があります
応援体制の構築と
「応急給水対策」に対する給水車の配備は必須です。
この仕事は、私の責任です。
2012年10月22日
以外に多い「蛇口から飲む」派
水道水と「市販のペットボトルの水」の記事のあと
何人かの方から「水道水」頑張れの
励ましの電話をいただいた。
「お金にしたら 1,000倍違う」
「水質検査も 検査項目の絶対数が違う」
「日本の水道水は 自信を持っていい」
「どこに行っても水が飲める
こんなありがたいことはない」
そんな内容でした
が、問題は「声を出さない」利用者の方々
ここの椅子に座って、事あるごとにたずねている。
やはり「確固たる理由はないが心配」
「あの 塩素の臭いは受け付けない」
と、おっしゃる。
私は日頃から蛇口派、私の感覚では何も感じない
普通に「飲める」
とくに、冷たくして飲んだら「おいしい」

(写真:「健康のため水を飲もう」推進運動の啓蒙ポスター)
私の毎日の生活は
朝、目がさめると冷たい水道水をまず一杯。
歯を磨き、シャワーで髪を洗い、ヒゲを剃り
顔を洗って、から始まります。
皆さんも大体そうでしょう
水(水道水)は、生活には欠かせない
そんなことは百も承知。
しかし、いつの頃からか水道水はまずい
飲んではいけない、飲むものではないといった風潮が生まれ
ペットボトルの飲料水が流通しました
それも、大変なスピードで
もちろん
「市販のペットボトルがいい」方はそれでいいんです
でも、誤解だけは払拭したい。
水道水は
厳しい検査を行なっている安全な水です。
何人かの方から「水道水」頑張れの
励ましの電話をいただいた。
「お金にしたら 1,000倍違う」
「水質検査も 検査項目の絶対数が違う」
「日本の水道水は 自信を持っていい」
「どこに行っても水が飲める
こんなありがたいことはない」
そんな内容でした
が、問題は「声を出さない」利用者の方々
ここの椅子に座って、事あるごとにたずねている。
やはり「確固たる理由はないが心配」
「あの 塩素の臭いは受け付けない」
と、おっしゃる。
私は日頃から蛇口派、私の感覚では何も感じない
普通に「飲める」
とくに、冷たくして飲んだら「おいしい」

(写真:「健康のため水を飲もう」推進運動の啓蒙ポスター)
私の毎日の生活は
朝、目がさめると冷たい水道水をまず一杯。
歯を磨き、シャワーで髪を洗い、ヒゲを剃り
顔を洗って、から始まります。
皆さんも大体そうでしょう
水(水道水)は、生活には欠かせない
そんなことは百も承知。
しかし、いつの頃からか水道水はまずい
飲んではいけない、飲むものではないといった風潮が生まれ
ペットボトルの飲料水が流通しました
それも、大変なスピードで
もちろん
「市販のペットボトルがいい」方はそれでいいんです
でも、誤解だけは払拭したい。
水道水は
厳しい検査を行なっている安全な水です。
2012年10月19日
「吉野ヶ里町」満足度トップは上水道の充実
吉野ヶ里町の町政だよりである
「広報よしのがり」10月号に嬉しい記事がありました。
まちづくりアンケート調査結果の中
「各施策の満足度と重要性」の項目で
満足度の高い項目は?、との問いに対して
第1位が「上水道の充実」でした。
各分野36項目の中でのトップだそうです
素直に「うれしい気持ち」です。
なお、平成18年度の調査資料を見れば
1位は「下水道の整備」、2位は「自然の豊かさ」
3位は「買い物の便利さ」、でした。
吉野ヶ里町は、2006年3月1日に
神埼郡の旧三田川町・旧東脊振村が新設合併して発足しました。
旧三田川町は、昭和36年に
地下水を水源とした簡易水道が始まりました。

(写真:吉野ヶ里町役場「三田川庁舎」)
しかし、地下水の宿命とも言うべき
水質の悪化や水位低下による水量不足が生じ始め
年々増加する水事情に応えるため
灌漑用水を利用しながら凌いだものの、
絶対量の不足から、新たに2本のさく井(井戸)を整備。
しかし、それでも2~3年で揚水量が低下しました。
そのため、昭和52年、急速ろ過機を備えた
第3水源地を建設し、当面の水不足は解消されました。
また、将来的な水の手当として筑後川総合開発に伴う
新規都市用水に水源を求めました。
旧東脊振村は
山間部からの小川の流水及び浅井戸が利用されていたが
ホームポンプの出現により自家用水道として全戸に普及。

(写真:吉野ヶ里役場「東脊振庁舎」)
昭和29年、旧三田川町に陸上自衛隊補給処が誘致され
その際に同村在川地区に水源地を建設。
後年、その影響で
大曲地区の浅井戸が枯渇する事態になり
昭和35年防衛局の補助で大曲地区簡易水道を設置し
これが、最初の村営水道となりました。
昭和39年には小川内簡易水道を設置
昭和50年には中の原簡易水道の設置を進める中で
筑後川総合開発に伴う新規都市用水に水源を求めました。
旧三田川町・旧東脊振村とも
将来的な安定供給のために手当てした水量を持って
昭和50年に発足した東部水道企業団に参画され現在に至っています。
「広報よしのがり」10月号に嬉しい記事がありました。
まちづくりアンケート調査結果の中
「各施策の満足度と重要性」の項目で
満足度の高い項目は?、との問いに対して
第1位が「上水道の充実」でした。
各分野36項目の中でのトップだそうです
素直に「うれしい気持ち」です。
なお、平成18年度の調査資料を見れば
1位は「下水道の整備」、2位は「自然の豊かさ」
3位は「買い物の便利さ」、でした。
吉野ヶ里町は、2006年3月1日に
神埼郡の旧三田川町・旧東脊振村が新設合併して発足しました。
旧三田川町は、昭和36年に
地下水を水源とした簡易水道が始まりました。

(写真:吉野ヶ里町役場「三田川庁舎」)
しかし、地下水の宿命とも言うべき
水質の悪化や水位低下による水量不足が生じ始め
年々増加する水事情に応えるため
灌漑用水を利用しながら凌いだものの、
絶対量の不足から、新たに2本のさく井(井戸)を整備。
しかし、それでも2~3年で揚水量が低下しました。
そのため、昭和52年、急速ろ過機を備えた
第3水源地を建設し、当面の水不足は解消されました。
また、将来的な水の手当として筑後川総合開発に伴う
新規都市用水に水源を求めました。
旧東脊振村は
山間部からの小川の流水及び浅井戸が利用されていたが
ホームポンプの出現により自家用水道として全戸に普及。

(写真:吉野ヶ里役場「東脊振庁舎」)
昭和29年、旧三田川町に陸上自衛隊補給処が誘致され
その際に同村在川地区に水源地を建設。
後年、その影響で
大曲地区の浅井戸が枯渇する事態になり
昭和35年防衛局の補助で大曲地区簡易水道を設置し
これが、最初の村営水道となりました。
昭和39年には小川内簡易水道を設置
昭和50年には中の原簡易水道の設置を進める中で
筑後川総合開発に伴う新規都市用水に水源を求めました。
旧三田川町・旧東脊振村とも
将来的な安定供給のために手当てした水量を持って
昭和50年に発足した東部水道企業団に参画され現在に至っています。
2012年10月18日
「ギンナン」日陰干し中
めっきりと秋めいてきました
見渡す限りの稲も頭を垂れています。
心配した台風も大きな被害はなく
実りの秋を迎えようとしています。
事務所の敷地の植木も
専門の造園業者の手によりさっぱりと剪定され
厳しい冬にそなえる姿に映ります。

(写真:企業団本庁の「イチョウ」の並木)
さて、敷地の境界にはイチョウが植えられています
このイチョウは旧佐賀市の市木
それが関係あるかないかは知りませんが
もう葉の色を変え始めました。
十数本の中で一本だけ毎年実をつけます
今年は たわわに生りすぎたのでしょう
「実が小さい」がもっぱらの評判。
その実を掃除のおばさんが
皮をとり、今、日陰干しの最中です。

(写真:陰干し中のイチョウの実「ギンナン」)
お尋ねしたら
毎年職員が心待ちしている模様。
もうすぐ「秋の香り」と
「おばさんのやさしさ」を頂けそうです。
見渡す限りの稲も頭を垂れています。
心配した台風も大きな被害はなく
実りの秋を迎えようとしています。
事務所の敷地の植木も
専門の造園業者の手によりさっぱりと剪定され
厳しい冬にそなえる姿に映ります。
(写真:企業団本庁の「イチョウ」の並木)
さて、敷地の境界にはイチョウが植えられています
このイチョウは旧佐賀市の市木
それが関係あるかないかは知りませんが
もう葉の色を変え始めました。
十数本の中で一本だけ毎年実をつけます
今年は たわわに生りすぎたのでしょう
「実が小さい」がもっぱらの評判。
その実を掃除のおばさんが
皮をとり、今、日陰干しの最中です。
(写真:陰干し中のイチョウの実「ギンナン」)
お尋ねしたら
毎年職員が心待ちしている模様。
もうすぐ「秋の香り」と
「おばさんのやさしさ」を頂けそうです。
2012年10月17日
全国水道企業団経営会議に出席
先週は
「全国水道企業団協議会企業長・事務局長経営会議」
に出席しました。
場所は北海道の滝川市
今回のお世話役(事務局)は「中空知広域水道企業団」
滝川市・砂川市・歌志内市及び奈井江町の3市1町の
水道事業を行っている企業団です。
ここは石狩平野のど真ん中
札幌から列車で1時間弱、旭川まで30分強
郊外は見渡す限りの畑が広がり
車窓からは北海道らしい風景を楽しみました。
さて、目的は経営会議
今回のテーマは四件、なかでも興味は二つ
「危機時の連絡体制」「施設の更新」

(写真:全国の水道企業団が参集した会議の様子)
「危機時の連絡体制」については
発表の機会があり報告。
それぞれ先進的な取り組みや
同じ悩みでの試行錯誤の状況が共有でき
私にとっては非常に有意義。
個別に話す機会も多く
より具体的なお話しや先進事業体への視察派遣についての
お願いもできた。
会議の最後に「講演」を聞いた
北大の田中教授、テーマは
「少子社会に向けての公共サービスの将来像」
始めに日本のどこにでもある
「水飲み場」の写真を見せられた。
日本人の年配者の100%は飲む
しかし、北大の一年生100人に聞いたら
「飲む」と答えたのは5人で、5%
これを前提に「水道の将来を語るべき」から話は始った。
途中はここでは省略するが
興味をそそられたのが「国際展開」
世界の状況は物の本等で聞いてはいる
それは、大都会の水道のこと
と思っていたが「国際貢献の視点から考えれば」の提案。
講演後、紹介されお話をする機会があり
1、2点確かめた。
「あり得る」「全国の企業団で」
との思いを持った。
同席された八戸の市長(本会の会長)もうなずいておられた
「チャンスがあれば」と思う。
さて、この会議
昨年は我が東部水道企業団が担当だった。
その時のお礼と
それがきっかけでの「お付き合い」で
何かと支援やアドバイスを頂けることも嬉しい。
そんな方々との懇親は
私の「楽しみのひとつ」ともなった。
最後になってしまったが
事務局で奮闘された職員の皆さん方
本当にお疲れ様でした。

(写真:お世話になった事務局の皆さん)
あなた方の気配りと熱心さが
何よりの「お土産」でした
今後共のお付き合いをお願いします。
「全国水道企業団協議会企業長・事務局長経営会議」
に出席しました。
場所は北海道の滝川市
今回のお世話役(事務局)は「中空知広域水道企業団」
滝川市・砂川市・歌志内市及び奈井江町の3市1町の
水道事業を行っている企業団です。
ここは石狩平野のど真ん中
札幌から列車で1時間弱、旭川まで30分強
郊外は見渡す限りの畑が広がり
車窓からは北海道らしい風景を楽しみました。
さて、目的は経営会議
今回のテーマは四件、なかでも興味は二つ
「危機時の連絡体制」「施設の更新」
(写真:全国の水道企業団が参集した会議の様子)
「危機時の連絡体制」については
発表の機会があり報告。
それぞれ先進的な取り組みや
同じ悩みでの試行錯誤の状況が共有でき
私にとっては非常に有意義。
個別に話す機会も多く
より具体的なお話しや先進事業体への視察派遣についての
お願いもできた。
会議の最後に「講演」を聞いた
北大の田中教授、テーマは
「少子社会に向けての公共サービスの将来像」
始めに日本のどこにでもある
「水飲み場」の写真を見せられた。
日本人の年配者の100%は飲む
しかし、北大の一年生100人に聞いたら
「飲む」と答えたのは5人で、5%
これを前提に「水道の将来を語るべき」から話は始った。
途中はここでは省略するが
興味をそそられたのが「国際展開」
世界の状況は物の本等で聞いてはいる
それは、大都会の水道のこと
と思っていたが「国際貢献の視点から考えれば」の提案。
講演後、紹介されお話をする機会があり
1、2点確かめた。
「あり得る」「全国の企業団で」
との思いを持った。
同席された八戸の市長(本会の会長)もうなずいておられた
「チャンスがあれば」と思う。
さて、この会議
昨年は我が東部水道企業団が担当だった。
その時のお礼と
それがきっかけでの「お付き合い」で
何かと支援やアドバイスを頂けることも嬉しい。
そんな方々との懇親は
私の「楽しみのひとつ」ともなった。
最後になってしまったが
事務局で奮闘された職員の皆さん方
本当にお疲れ様でした。
(写真:お世話になった事務局の皆さん)
あなた方の気配りと熱心さが
何よりの「お土産」でした
今後共のお付き合いをお願いします。
2012年10月16日
掃除のおばさん
10月の声を聞き
朝夕はめっきりと涼しくなりました。
昼休みに散歩をしていると
アスファルトの隙間に「けいとう」の花が
咲いているのに気づきました。

(写真:たくましく育つ「けいとう」)
厳しい環境の中で
しっかりと根を張り自然の力強さを感じます。
「けいとう」の花に「がんばれ」と
励まされた気持ちになりました。
さて、「掃除のおばさん」ことTさんには
毎日、企業団の本庁事務所内外と北茂安浄水場の
掃除をして頂いています。
(掃除のおばさんとは失礼な言い方かとも思いますが
親しみを込めて呼ばせて頂きます。)
契約的には、施設の清掃を契約している
「佐賀県ビルメンテナンス協同組合」の中の
昭和メンテの従業員さん。
お名前はTさん
企業団がお世話になって20数年。
そこらへんの若手よりも企業団への関わりが長い
いつも、陰日なたなく働いてもらっている。
時々、掃除の手を休めてもらい話しかける
「職員さんには良くして頂きます」と言われる。
「表づらの誉め言葉」とは思うが「嬉しい」
永いことお世話になって
時々の空気感で「企業団も大変だ」と感じる時もありました、とも聞く。
まだまだ、お世話をおかけします。
朝夕はめっきりと涼しくなりました。
昼休みに散歩をしていると
アスファルトの隙間に「けいとう」の花が
咲いているのに気づきました。
(写真:たくましく育つ「けいとう」)
厳しい環境の中で
しっかりと根を張り自然の力強さを感じます。
「けいとう」の花に「がんばれ」と
励まされた気持ちになりました。
さて、「掃除のおばさん」ことTさんには
毎日、企業団の本庁事務所内外と北茂安浄水場の
掃除をして頂いています。
(掃除のおばさんとは失礼な言い方かとも思いますが
親しみを込めて呼ばせて頂きます。)
契約的には、施設の清掃を契約している
「佐賀県ビルメンテナンス協同組合」の中の
昭和メンテの従業員さん。
お名前はTさん
企業団がお世話になって20数年。
そこらへんの若手よりも企業団への関わりが長い
いつも、陰日なたなく働いてもらっている。
時々、掃除の手を休めてもらい話しかける
「職員さんには良くして頂きます」と言われる。
「表づらの誉め言葉」とは思うが「嬉しい」
永いことお世話になって
時々の空気感で「企業団も大変だ」と感じる時もありました、とも聞く。
まだまだ、お世話をおかけします。
2012年10月15日
水道の歴史と今年の工事「旧千代田町」編
旧千代田町(現神埼市千代田町)では
昭和34年までは、ほとんどの家庭が
川やクリークの水を飲料水として利用されていました。
しかし、保健衛生上の観点から上水道への要望が高まり
随時、地下水による簡易水道が建設され
当面の生活用水は確保されました。
それでも、年々地下水の水質が悪化していき
東部地区では地下水が飲料不適となるにまで至り
町内を流れる田手川からの水利使用を得
それまでの簡易水道を統合して上水道としてスタートしました。
しかし、必ずしも将来的に安定的な水源ではなかったため
筑後川総合開発に伴う新規都市用水に水源を求め
東部水道企業団に参画され現在に至っています。

(写真:神埼市千代田支所の「千代田庁舎」)
さて、千代田町の水道の課題は
「管の老朽化」と「水の出の悪さ」
原因は、古くて管径が小さい
昭和40年代の前半布設の石綿セメント管。
当時は「一家に、蛇口1個」の時代
生活環境が変り、水道使用は飛躍的に増加したが
「管は当時のまま」
水圧の低下により一部ご迷惑をおかけしていますが、
東部水道企業団が事業を引き継いだ後は
段階的ではありますが、積極的に更新事業に取り組んでいます。
今年度終了時点で
千代田町の約5割の地区の水道管が新しくなります
残りの地区の方には申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。
さて、今年の千代田町内の工事は
黒津・詫田西地区が終了し「嘉納地区」を着工します。
既存の管径は5センチ、これを7.5センチに替え
(管の断面積は、約2倍となります)
延長は約500メートルの工事となります。
工事中の通行規制や断水などでご迷惑をおかけしますが
ご協力をお願いします。
昭和34年までは、ほとんどの家庭が
川やクリークの水を飲料水として利用されていました。
しかし、保健衛生上の観点から上水道への要望が高まり
随時、地下水による簡易水道が建設され
当面の生活用水は確保されました。
それでも、年々地下水の水質が悪化していき
東部地区では地下水が飲料不適となるにまで至り
町内を流れる田手川からの水利使用を得
それまでの簡易水道を統合して上水道としてスタートしました。
しかし、必ずしも将来的に安定的な水源ではなかったため
筑後川総合開発に伴う新規都市用水に水源を求め
東部水道企業団に参画され現在に至っています。
(写真:神埼市千代田支所の「千代田庁舎」)
さて、千代田町の水道の課題は
「管の老朽化」と「水の出の悪さ」
原因は、古くて管径が小さい
昭和40年代の前半布設の石綿セメント管。
当時は「一家に、蛇口1個」の時代
生活環境が変り、水道使用は飛躍的に増加したが
「管は当時のまま」
水圧の低下により一部ご迷惑をおかけしていますが、
東部水道企業団が事業を引き継いだ後は
段階的ではありますが、積極的に更新事業に取り組んでいます。
今年度終了時点で
千代田町の約5割の地区の水道管が新しくなります
残りの地区の方には申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。
さて、今年の千代田町内の工事は
黒津・詫田西地区が終了し「嘉納地区」を着工します。
既存の管径は5センチ、これを7.5センチに替え
(管の断面積は、約2倍となります)
延長は約500メートルの工事となります。
工事中の通行規制や断水などでご迷惑をおかけしますが
ご協力をお願いします。
2012年10月12日
水道の歴史
水道の起源は、古代ローマ
水道橋を建設して、水源から水を運び
室内配管によって家庭に水を供給していたことは
良く知られています。
日本では、戦国時代、北条氏康によって
小田原早川上水が建設され小田原城下に供給したのが
最古の記録だそうです。
その後、徳川家康など諸大名により
全国に水道が建設され、当時の江戸の町は
世界で最も進んだ水道設備だったそうです。
しかし、これらは全て川等の水をそのまま取水し
生活用水として利用していました。
明治になると
コレラ、チフス、赤痢などの伝染病が蔓延し
近代水道への整備が求められました。
日本における近代水道は
横浜市に明治20年9月に完成しています。
ここでいう近代水道とは
「有圧送水」「ろ過設備」「常時給水」を
そなえたものと定義されています。
今後
東部水道企業団域内の旧町村ごとに
水道の歴史を工事発注のお知らせとあわせて
順次、かいつまんで紹介していきます。
水道橋を建設して、水源から水を運び
室内配管によって家庭に水を供給していたことは
良く知られています。
日本では、戦国時代、北条氏康によって
小田原早川上水が建設され小田原城下に供給したのが
最古の記録だそうです。
その後、徳川家康など諸大名により
全国に水道が建設され、当時の江戸の町は
世界で最も進んだ水道設備だったそうです。
しかし、これらは全て川等の水をそのまま取水し
生活用水として利用していました。
明治になると
コレラ、チフス、赤痢などの伝染病が蔓延し
近代水道への整備が求められました。
日本における近代水道は
横浜市に明治20年9月に完成しています。
ここでいう近代水道とは
「有圧送水」「ろ過設備」「常時給水」を
そなえたものと定義されています。
今後
東部水道企業団域内の旧町村ごとに
水道の歴史を工事発注のお知らせとあわせて
順次、かいつまんで紹介していきます。
2012年10月11日
職場のボウリング大会
職員の福利厚生の一貫として
職場内のボウリング大会が開催されました。
業務終了後にボウリング場に集合し、2ゲームで結果を競います
一職員から見たボウリング大会の参加レポートです。
---(参加の職員より)--------------------
今年の成績は
1位340点、2位317点、3位309点
最下位は143点でした。(2ゲームの計)
私の得点は208点で、43人の参加者中34番目。

(写真:佐賀市内のボウリング場にて)
皆さん年に1回だけ、この大会でプレーする方がほとんど。
だから、その時の体調や、まぐれ当たりで、順位は大きく変動。
昨年1位の職員は指のケガで棄権、2位の職員は今年7位
3位の職員は今年10位と。
ピンが離れてしまったスプリットの二投目も
年に1回では、ほとんど運まかせ。

(写真:スプリットに挑む職員)
技術がものをいうボウリング
運動音痴な私も、練習に励めば高得点?
毎年思うが、なかなか実行に移せていない。
結果、毎年下から数番目、今年はまだいい方。
ボウリングの歴史を調べると
紀元前5,000年頃の古代エジプトの墓から
木でできたボールとピンが発見された事から
似たようなものがあったとされています。
地域によりピンの数、並べ方がばらばらだったものが
中世ドイツで9本のピンをひし形に並べて倒す型に統一され
これが17世紀にアメリカで現在の
ピン10本で正三角系に並べるようになったそうです。
日本では1861年6月22日に長崎の大浦居留地に
初めてのボウリング場が開設されたとのことで
6月22日はボウリングの日となっています。
1969年(昭和44年)に国内で、女子プロ1期生として
美人で知られる中山律子さんなどが活躍され、
翌年スコアを自動計算する機械が実用化されたことにより、
以降ブームとなったそうです。
ブームの中でマイボールを持って練習に励んだ方は今でも上手。

(写真:結果発表の様子)
投球後に一喜一憂
ストライクやスペアがとれれば、ハイタッチ。
年に1度のレクリエーション
ケガもなく、楽しく盛り上がりました。
職場内のボウリング大会が開催されました。
業務終了後にボウリング場に集合し、2ゲームで結果を競います
一職員から見たボウリング大会の参加レポートです。
---(参加の職員より)--------------------
今年の成績は
1位340点、2位317点、3位309点
最下位は143点でした。(2ゲームの計)
私の得点は208点で、43人の参加者中34番目。
(写真:佐賀市内のボウリング場にて)
皆さん年に1回だけ、この大会でプレーする方がほとんど。
だから、その時の体調や、まぐれ当たりで、順位は大きく変動。
昨年1位の職員は指のケガで棄権、2位の職員は今年7位
3位の職員は今年10位と。
ピンが離れてしまったスプリットの二投目も
年に1回では、ほとんど運まかせ。
(写真:スプリットに挑む職員)
技術がものをいうボウリング
運動音痴な私も、練習に励めば高得点?
毎年思うが、なかなか実行に移せていない。
結果、毎年下から数番目、今年はまだいい方。
ボウリングの歴史を調べると
紀元前5,000年頃の古代エジプトの墓から
木でできたボールとピンが発見された事から
似たようなものがあったとされています。
地域によりピンの数、並べ方がばらばらだったものが
中世ドイツで9本のピンをひし形に並べて倒す型に統一され
これが17世紀にアメリカで現在の
ピン10本で正三角系に並べるようになったそうです。
日本では1861年6月22日に長崎の大浦居留地に
初めてのボウリング場が開設されたとのことで
6月22日はボウリングの日となっています。
1969年(昭和44年)に国内で、女子プロ1期生として
美人で知られる中山律子さんなどが活躍され、
翌年スコアを自動計算する機械が実用化されたことにより、
以降ブームとなったそうです。
ブームの中でマイボールを持って練習に励んだ方は今でも上手。
(写真:結果発表の様子)
投球後に一喜一憂
ストライクやスペアがとれれば、ハイタッチ。
年に1度のレクリエーション
ケガもなく、楽しく盛り上がりました。
2012年10月10日
西部広域水道企業団の新企業長歓迎会
佐賀西部広域水道企業団の企業長が新しく就任されました。
お名前は北島氏。
実は、当企業団の構成団体の
佐賀市に関係する水道組織は4つあります。
旧佐賀市区域と旧諸富町
旧大和町の一部の水道事業を担う「佐賀市上下水道局」
旧諸富町区域は、佐賀市上下水道局より
東部水道企業団が業務を受託しています。
旧久保田町
小城市の一部(旧芦刈町、旧牛津町、旧三日月町)
白石町の一部(旧福富町)の水道事業を担う
「西佐賀水道企業団」
今回、新企業長として就任された
北島氏の「佐賀西部広域水道企業団」

(写真:佐賀西部広域水道企業団の庁舎)
ここは、多久市、武雄市、小城市、嬉野市、大町町
江北町、白石町、西佐賀水道企業団の
4市3町1企業団に用水を供給するのが目的。

(イラスト:「事業模式図」西部広域水道企業団ホームページより)
それに、佐賀市の南部の旧川副町と旧東与賀町
神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町の
水道事業を行うと共に、旧佐賀市への一部用水供給を担う
「佐賀東部水道企業団」
それぞれが水道水の安定供給のために
懸命に努力をしていますが課題も各々にあります。
日本水道協会等の行事参加や
その都度関係する団体同士の接触はありますが
共通の課題の解決やお互いの技術力アップの連携等は
もう少し密度を高めても良いのでは
との思いがありました。
そこで、西部広域水道企業団の企業長の就任という機会を捉えて
各事業体の皆さんに相談したところ
「思いはいっしょ」「是非やりましょう」で実現しました。
まずは顔見知りから、そのためには「お酒の力」も必要
「有意義でした」 「建設的でした」
「定例会としましょう」となりました。
今後、どう発展し
それが各組織の利用者の皆様にどう反映できるか
少しだけ長い目でみて欲しいと思います。
お名前は北島氏。
実は、当企業団の構成団体の
佐賀市に関係する水道組織は4つあります。
旧佐賀市区域と旧諸富町
旧大和町の一部の水道事業を担う「佐賀市上下水道局」
旧諸富町区域は、佐賀市上下水道局より
東部水道企業団が業務を受託しています。
旧久保田町
小城市の一部(旧芦刈町、旧牛津町、旧三日月町)
白石町の一部(旧福富町)の水道事業を担う
「西佐賀水道企業団」
今回、新企業長として就任された
北島氏の「佐賀西部広域水道企業団」
(写真:佐賀西部広域水道企業団の庁舎)
ここは、多久市、武雄市、小城市、嬉野市、大町町
江北町、白石町、西佐賀水道企業団の
4市3町1企業団に用水を供給するのが目的。

(イラスト:「事業模式図」西部広域水道企業団ホームページより)
それに、佐賀市の南部の旧川副町と旧東与賀町
神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町の
水道事業を行うと共に、旧佐賀市への一部用水供給を担う
「佐賀東部水道企業団」
それぞれが水道水の安定供給のために
懸命に努力をしていますが課題も各々にあります。
日本水道協会等の行事参加や
その都度関係する団体同士の接触はありますが
共通の課題の解決やお互いの技術力アップの連携等は
もう少し密度を高めても良いのでは
との思いがありました。
そこで、西部広域水道企業団の企業長の就任という機会を捉えて
各事業体の皆さんに相談したところ
「思いはいっしょ」「是非やりましょう」で実現しました。
まずは顔見知りから、そのためには「お酒の力」も必要
「有意義でした」 「建設的でした」
「定例会としましょう」となりました。
今後、どう発展し
それが各組織の利用者の皆様にどう反映できるか
少しだけ長い目でみて欲しいと思います。
2012年10月09日
佐賀市上下水道局「神野浄水場」見学
先日、筑後川水道三企業団協議会の
事務部会の研修として、佐賀市上下水道局の
「神野(こうの)浄水場」の視察がありました。
筑後川水道三企業団協議会とは
筑後川を水道の水源として利用している
・福岡地区水道企業団
・福岡県南広域水道企業団
・佐賀東部水道企業団
の三つの企業団で組織した協議会です。
東部水道企業団からも3名の職員が参加しましたので
内容等について、ご紹介します。
---(参加の職員より)---------------------
佐賀市の水道の歴史は古く、明治44年の調査から始まり
日本初のさく井式(さくせいしき:井戸)での給水を
大正5年11月から開始されました。
その後、村の合併、需要の増大、水量不足、法改正等により
昭和50年に、現在の神野浄水場50,000m3/日
昭和52年に、神野第2浄水場35,000m3/日が完成し
合計85,000m3/日の処理ができる施設となりました。
平成17年10月の市町村合併で給水地域が広がり
平成21年4月からは市内山間部の簡易水道の管理を開始
平成24年4月1日に下水道部局と合併し
佐賀市上下水道局が発足しました。
東部水道企業団と佐賀市の関係は密接で
平成4年から佐賀市へ水道用水を供給し、佐賀市は大口ユーザーです。
また、市長及び市議2名は、東部水道企業団議会の議員でもあります。
「神野浄水場」は、市街地の中に位置し
近い家は、浄水場の敷地から約10mもはなれていませんので
街中ならではの騒音対策も施されていました。
施設が古いこともあるのでしょうが
費用を極力かけずに改造を行われた形跡が、随所に見られました。

(写真:「沈砂地」ビニールパイプより次亜塩素ナトリウムと
水に溶いた活性炭が注入されている)
最後に、上下水道局の玄関近くの最近設置された、
災害時用臨時水栓及び水飲み場で
おいしい水を直接いただきました。
台の下には、給水車に連結できる給水栓が備わっており
また、臨時水飲み場の排水も再処理されているとのこと。

(写真:災害時用臨時給水栓及び水飲み場)
途中の倉庫で「災害用造水機」を目にしました
災害時、学校のプールの水を飲めるように浄化する機械で
200万円で購入され、現在2台所有されていました。
小型発電機より一回り大きい大きさで
24時間で50m3の水を造ります。

(写真:災害用造水機)
佐賀市上下水道局の職員の方に
現地で詳細に説明してもらい、質問にも丁寧に回答いただきました。
ありがとうございました。
事務部会の研修として、佐賀市上下水道局の
「神野(こうの)浄水場」の視察がありました。
筑後川水道三企業団協議会とは
筑後川を水道の水源として利用している
・福岡地区水道企業団
・福岡県南広域水道企業団
・佐賀東部水道企業団
の三つの企業団で組織した協議会です。
東部水道企業団からも3名の職員が参加しましたので
内容等について、ご紹介します。
---(参加の職員より)---------------------
佐賀市の水道の歴史は古く、明治44年の調査から始まり
日本初のさく井式(さくせいしき:井戸)での給水を
大正5年11月から開始されました。
その後、村の合併、需要の増大、水量不足、法改正等により
昭和50年に、現在の神野浄水場50,000m3/日
昭和52年に、神野第2浄水場35,000m3/日が完成し
合計85,000m3/日の処理ができる施設となりました。
平成17年10月の市町村合併で給水地域が広がり
平成21年4月からは市内山間部の簡易水道の管理を開始
平成24年4月1日に下水道部局と合併し
佐賀市上下水道局が発足しました。
東部水道企業団と佐賀市の関係は密接で
平成4年から佐賀市へ水道用水を供給し、佐賀市は大口ユーザーです。
また、市長及び市議2名は、東部水道企業団議会の議員でもあります。
「神野浄水場」は、市街地の中に位置し
近い家は、浄水場の敷地から約10mもはなれていませんので
街中ならではの騒音対策も施されていました。
施設が古いこともあるのでしょうが
費用を極力かけずに改造を行われた形跡が、随所に見られました。

(写真:「沈砂地」ビニールパイプより次亜塩素ナトリウムと
水に溶いた活性炭が注入されている)
最後に、上下水道局の玄関近くの最近設置された、
災害時用臨時水栓及び水飲み場で
おいしい水を直接いただきました。
台の下には、給水車に連結できる給水栓が備わっており
また、臨時水飲み場の排水も再処理されているとのこと。

(写真:災害時用臨時給水栓及び水飲み場)
途中の倉庫で「災害用造水機」を目にしました
災害時、学校のプールの水を飲めるように浄化する機械で
200万円で購入され、現在2台所有されていました。
小型発電機より一回り大きい大きさで
24時間で50m3の水を造ります。

(写真:災害用造水機)
佐賀市上下水道局の職員の方に
現地で詳細に説明してもらい、質問にも丁寧に回答いただきました。
ありがとうございました。
2012年10月05日
車両の一斉点検
東部水道企業団が所有する車は
本庁21台、北茂安浄水場4台、三養基営業所8台の計33台。
道路交通法の規定で、一定台数以上の自家用自動車を
保有する事業所においては、安全運転管理者をおくように
定められている。
自動車の台数が21台以上の場合は、副安全運転管理者も必要。
東部水道企業団でも、その規定により、本庁に正副の2名
三養基営業所に1名の安全運転管理者を定めている。
毎日の点検と運行日誌の記載が必須
ここまでは、法に従い当然のこと。
東部水道企業団では
重大事故を起さないように常に心がける。
そのための車両の点検であり
朝礼の際には安全運転の啓蒙に勤めてきた。
月の初めには、一斉に点検を行なっている
それは、二人一組で行い徹底している。
ブレーキや計器類はもちろんのこと
車載工具、無線の点検等を行い
安全運転管理者に報告する、が一連の流れになっている。
今朝がその日だった。

(写真:点検の様子1)

(写真:点検の様子2)
東部水道企業団での最近の交通事故状況は
平成23年度が3件、うち人身事故は0件。
過去は
平成22年度が3件、うち人身事故は0件。
平成21年度が8件、うち人身事故は1件。
確実に成果はでている
今後とも継続し、「事故ゼロ」を目標として努力していきたい。
本庁21台、北茂安浄水場4台、三養基営業所8台の計33台。
道路交通法の規定で、一定台数以上の自家用自動車を
保有する事業所においては、安全運転管理者をおくように
定められている。
自動車の台数が21台以上の場合は、副安全運転管理者も必要。
東部水道企業団でも、その規定により、本庁に正副の2名
三養基営業所に1名の安全運転管理者を定めている。
毎日の点検と運行日誌の記載が必須
ここまでは、法に従い当然のこと。
東部水道企業団では
重大事故を起さないように常に心がける。
そのための車両の点検であり
朝礼の際には安全運転の啓蒙に勤めてきた。
月の初めには、一斉に点検を行なっている
それは、二人一組で行い徹底している。
ブレーキや計器類はもちろんのこと
車載工具、無線の点検等を行い
安全運転管理者に報告する、が一連の流れになっている。
今朝がその日だった。
(写真:点検の様子1)
(写真:点検の様子2)
東部水道企業団での最近の交通事故状況は
平成23年度が3件、うち人身事故は0件。
過去は
平成22年度が3件、うち人身事故は0件。
平成21年度が8件、うち人身事故は1件。
確実に成果はでている
今後とも継続し、「事故ゼロ」を目標として努力していきたい。
2012年10月04日
メガソーラー発電開始
台風一過の晴天に恵まれた10月1日
佐賀県内初のメガソーラー(大規模太陽光発電施設)が
発電を開始しました。

(写真:「施設の全景」芝浦特機(株)HPより)
芝浦グループホールディングスが
当企業団の川副浄水場跡地を賃借し
川副発電所として最大30年間操業します。

(写真:リアルタイムの発電状況を示す「稼働案内パネル」)
全国各地で建設中のメガソーラーよりも小規模ですが
立地条件も良好で
平均すると一般家庭「220世帯分」の電気使用量を発電します。
※この日は晴天でしたが、曇りや雨天だと発電量は少なくなります。
パネルの数値はリアルタイムの発電量と本日の累計値。
469戸分とあるのはその日の累計発電量を一般家庭に換算したもの。
雨天時等を考慮すると年間平均で220世帯分になると見込まれています。

(写真:整然と設置された「太陽光発電パネル」)
約17,000m2の川副浄水場跡地にあった建物に代わり
太陽光発電パネルが4,032枚設置され
スッキリした風景になりました。

(写真:設置パネルの枚数確認の様子)
企業団が経営するわけではありませんが
再生可能エネルギーの普及に
少しばかりお役に立てたと思います。
今朝の天気みたいにカラッ
と晴れ上がった気持ちになりました。
佐賀県内初のメガソーラー(大規模太陽光発電施設)が
発電を開始しました。

(写真:「施設の全景」芝浦特機(株)HPより)
芝浦グループホールディングスが
当企業団の川副浄水場跡地を賃借し
川副発電所として最大30年間操業します。
(写真:リアルタイムの発電状況を示す「稼働案内パネル」)
全国各地で建設中のメガソーラーよりも小規模ですが
立地条件も良好で
平均すると一般家庭「220世帯分」の電気使用量を発電します。
※この日は晴天でしたが、曇りや雨天だと発電量は少なくなります。
パネルの数値はリアルタイムの発電量と本日の累計値。
469戸分とあるのはその日の累計発電量を一般家庭に換算したもの。
雨天時等を考慮すると年間平均で220世帯分になると見込まれています。
(写真:整然と設置された「太陽光発電パネル」)
約17,000m2の川副浄水場跡地にあった建物に代わり
太陽光発電パネルが4,032枚設置され
スッキリした風景になりました。
(写真:設置パネルの枚数確認の様子)
企業団が経営するわけではありませんが
再生可能エネルギーの普及に
少しばかりお役に立てたと思います。
今朝の天気みたいにカラッ
と晴れ上がった気持ちになりました。
2012年10月03日
市販のペットボトルの水
「水道水のペットボトル」、「水道水の値段」と
続けたら、市販のペットボトルの水を
無視することはできません。
両方とも「社会に認知された飲料水」ですが
「水道水」とはある面、対立関係
だからと言って批判する訳ではありません。
水道水と「市販のペットボトルの水」の違いは
検査の項目です。
水道水は水道法で規定され、検査項目は50項目
項目毎に検査の頻度が定められており
毎日、毎月、3か月、1年毎に各々検査を実施しています。
一方の「市販のペットボトルの水」は
食品衛生法が適用され
検査項目は、原水18項目、製品は7項目
検査頻度は、原水は年1回以上と規定
製品は規定なしで、賞味期限の表示のみとされています。
価格は500mlで100円程度
水道水の約1,000倍以上。
水道水との違いは
分かって頂けると思います。
また、最近は環境面からも水道水を飲もう
という運動が広がっています。
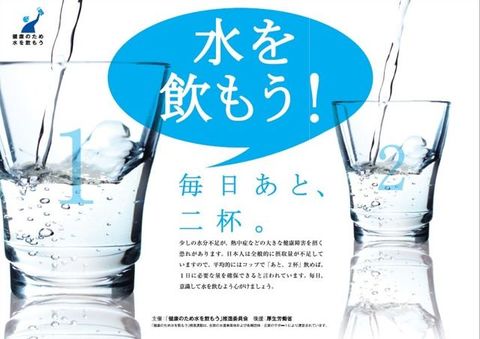
(写真:「健康のため水を飲もう」推進運動の啓蒙ポスター)
トラックで輸送したり、海外で製造し輸入等
製造と輸送に対して多くのエネルギーが消費されます。
ただ、水道水は「安全に対して疑問がある」とか
「塩素が嫌だ」との声があることも事実です。
私たちは水道水に自信を持っていますが
「いやだ」という方に対しては
「そうですか」とお答えする以外・・・、ありません。
続けたら、市販のペットボトルの水を
無視することはできません。
両方とも「社会に認知された飲料水」ですが
「水道水」とはある面、対立関係
だからと言って批判する訳ではありません。
水道水と「市販のペットボトルの水」の違いは
検査の項目です。
水道水は水道法で規定され、検査項目は50項目
項目毎に検査の頻度が定められており
毎日、毎月、3か月、1年毎に各々検査を実施しています。
一方の「市販のペットボトルの水」は
食品衛生法が適用され
検査項目は、原水18項目、製品は7項目
検査頻度は、原水は年1回以上と規定
製品は規定なしで、賞味期限の表示のみとされています。
価格は500mlで100円程度
水道水の約1,000倍以上。
水道水との違いは
分かって頂けると思います。
また、最近は環境面からも水道水を飲もう
という運動が広がっています。
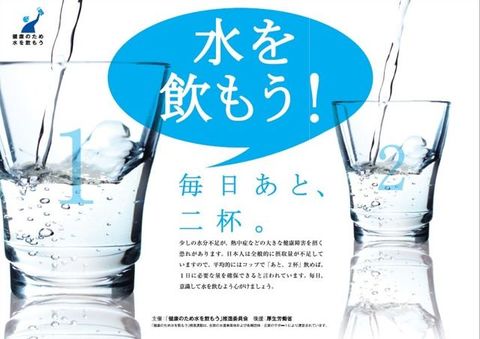
(写真:「健康のため水を飲もう」推進運動の啓蒙ポスター)
トラックで輸送したり、海外で製造し輸入等
製造と輸送に対して多くのエネルギーが消費されます。
ただ、水道水は「安全に対して疑問がある」とか
「塩素が嫌だ」との声があることも事実です。
私たちは水道水に自信を持っていますが
「いやだ」という方に対しては
「そうですか」とお答えする以外・・・、ありません。