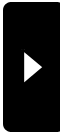2013年05月31日
日本水道協会佐賀県支部総会の報告
日本水道協会佐賀県支部の
第58回総会が伊万里市で行なわれました。

(写真:日本水道協会佐賀県支部総会の様子)
総会に先立ち塚部伊万里市長が歓迎の言葉を
「暑い季節になった、よぎるのは干ばつ
水は大丈夫か?と思う
水は必需、だから普段は出るのが当然
反面、何かあった時に有難さを痛感
伊万里市は、市域が広い
水道普及率100%が難しい土地柄
しかし、重点的に整備中
水道に携わる人は、人間にとって欠くことが出来ない仕事
誇りをもって業務にあたって欲しい」
事務局を担当する金丸佐賀市上下水道局長は
「3・11東日本大震災時
県支部として支援活動を積極的に行なった
今年の4月、厚生大臣から県支部として感謝状を頂いた
水道一家と言われてきた一致団結の結果だと思う
安心・安全を合言葉に
今後も努力をつづけましょう」
審議は順調に終わり、事務局より
九州全体で共同防災訓練を昨年より行なっている
その対応を「佐賀県支部」として取り組みたい
との提案が
連携が重要な中、提案には大賛成
総会後は、懇親会があり
伊万里牛をはじめ美味しくも楽しい時間を過ごしました
塚部市長、内山市議会議長、林部長はじめ
伊万里市の方々、お世話になりました。
第58回総会が伊万里市で行なわれました。
(写真:日本水道協会佐賀県支部総会の様子)
総会に先立ち塚部伊万里市長が歓迎の言葉を
「暑い季節になった、よぎるのは干ばつ
水は大丈夫か?と思う
水は必需、だから普段は出るのが当然
反面、何かあった時に有難さを痛感
伊万里市は、市域が広い
水道普及率100%が難しい土地柄
しかし、重点的に整備中
水道に携わる人は、人間にとって欠くことが出来ない仕事
誇りをもって業務にあたって欲しい」
事務局を担当する金丸佐賀市上下水道局長は
「3・11東日本大震災時
県支部として支援活動を積極的に行なった
今年の4月、厚生大臣から県支部として感謝状を頂いた
水道一家と言われてきた一致団結の結果だと思う
安心・安全を合言葉に
今後も努力をつづけましょう」
審議は順調に終わり、事務局より
九州全体で共同防災訓練を昨年より行なっている
その対応を「佐賀県支部」として取り組みたい
との提案が
連携が重要な中、提案には大賛成
総会後は、懇親会があり
伊万里牛をはじめ美味しくも楽しい時間を過ごしました
塚部市長、内山市議会議長、林部長はじめ
伊万里市の方々、お世話になりました。
2013年05月30日
日本水道協会九州支部の第一回役員会
日本水道協会の九州支部の
第一回役員会が博多で開催されました。
主には、来月宮崎市で開催される総会に提案する議題の審議
だから、内容は予算・決算・事業の報告等。
その一環で国に対しての要望案件を紹介します
大きくは三つのことを要望します。
一つ目「水道事業に対する財政支援」
他の公共事業と比較して財政支援の手薄さを感じます。
二つ目は「水道水源の水質保全対策の強化」
水源地域の生活雑排水の流入や
新規に進出する産業廃棄物処分場の規制強化。
三つ目は「起債融資の条件緩和と繰上償還制度」
特に、繰上償還について。
少し説明をさせて頂きます
水道事業は、起債(借金)を主な財源として
水道施設の整備拡充を行なってきました。
元利償還も大きな負担ですが
特に、過去に借り入れた
高金利既往債が負担をいっそう大きくしています。
過去、5%以上の利息の起債の軽減策が講じられ
東部水道企業団は全体で約20億円が減少しました。
今後、人口減少時代を迎えるにあたり
健全経営を確保するためにも
対象事業の拡大や条件緩和を国に求めるものです。
今後は、全国の総会で議決され
国に対して要望を行い、その実現に向かって
行動を起すことになると思います。
第一回役員会が博多で開催されました。
主には、来月宮崎市で開催される総会に提案する議題の審議
だから、内容は予算・決算・事業の報告等。
その一環で国に対しての要望案件を紹介します
大きくは三つのことを要望します。
一つ目「水道事業に対する財政支援」
他の公共事業と比較して財政支援の手薄さを感じます。
二つ目は「水道水源の水質保全対策の強化」
水源地域の生活雑排水の流入や
新規に進出する産業廃棄物処分場の規制強化。
三つ目は「起債融資の条件緩和と繰上償還制度」
特に、繰上償還について。
少し説明をさせて頂きます
水道事業は、起債(借金)を主な財源として
水道施設の整備拡充を行なってきました。
元利償還も大きな負担ですが
特に、過去に借り入れた
高金利既往債が負担をいっそう大きくしています。
過去、5%以上の利息の起債の軽減策が講じられ
東部水道企業団は全体で約20億円が減少しました。
今後、人口減少時代を迎えるにあたり
健全経営を確保するためにも
対象事業の拡大や条件緩和を国に求めるものです。
今後は、全国の総会で議決され
国に対して要望を行い、その実現に向かって
行動を起すことになると思います。
2013年05月29日
各部署との意見会「浄水課」
引き続き、各部署との「問題・課題の意見会」
目的は、企業団全体で共有すべき問題の把握
今回は浄水課編です。
ここの大きな課題は
設備・機器の更新や将来の浄水場の更新
これらのことは各々準備中
それらとは別の話題を紹介します。

(写真:「北茂安浄水場」の管理本館)
実はここ浄水課に異動希望者が多い
この職場は水質・電気・機械と専門の職種が大半
異動の希望者は水道の技術者の諸君。
その主な仕事は浄水場・ポンプ等の設備の土木部門
現在は、施設の耐震補強中であり普段より忙しい。
「異動したい」主旨は
浄水場等での「水道水をつくる過程を知りたい」
基本的なことを良く理解して
水道管等の計画や工事に携わりたい。
非常に分かりやすい
反面、浄水課としては「勉強のため」に来るのは正直迷惑
即戦力が欲しい、慣れた職員がいい。
こんな思いが双方にあります
両方とももっともな意見です。
しかし、私は浄水場の知識と経験を持った職員が
多くいることが企業団の強みと考えます。
今年の4月には
希望者のうちの一人に異動を発令しました。
目的は、企業団全体で共有すべき問題の把握
今回は浄水課編です。
ここの大きな課題は
設備・機器の更新や将来の浄水場の更新
これらのことは各々準備中
それらとは別の話題を紹介します。
(写真:「北茂安浄水場」の管理本館)
実はここ浄水課に異動希望者が多い
この職場は水質・電気・機械と専門の職種が大半
異動の希望者は水道の技術者の諸君。
その主な仕事は浄水場・ポンプ等の設備の土木部門
現在は、施設の耐震補強中であり普段より忙しい。
「異動したい」主旨は
浄水場等での「水道水をつくる過程を知りたい」
基本的なことを良く理解して
水道管等の計画や工事に携わりたい。
非常に分かりやすい
反面、浄水課としては「勉強のため」に来るのは正直迷惑
即戦力が欲しい、慣れた職員がいい。
こんな思いが双方にあります
両方とももっともな意見です。
しかし、私は浄水場の知識と経験を持った職員が
多くいることが企業団の強みと考えます。
今年の4月には
希望者のうちの一人に異動を発令しました。
2013年05月28日
各部署との意見会「三養基営業所」
引き続き、各部署との「問題・課題の意見会」
今回は、三養基営業所です。
三養基営業所は
みやき町の北茂安支所の一画を借家した事務所。
本庁とは距離があり
日常的に話をする機会はどうしても少ない。

(写真:みやき町北茂安庁舎内にある三養基営業所)
だからではないだろうが
日頃からの他部署との協議等が少ないのが原因と思われる
課題・問題が多く出ました。
そのなかで、企業団の内部的な問題ですが
退職者が今後増えます。
この企業団発足時に
採用された職員の大量退職が始ります。
今後5年間のうちに21名の退職者が予定されており
全体の三分の一弱にあたります。
現在の職員採用は
「行革」によって2年毎に1人の採用が続いています。
このことが内部的には大きな課題です
この職員数の減少、退職者の再雇用問題
将来の経営を見越した採用計画
いま、全職員で「未来像」の検討中ですが
個々の意見も
おおまかには「職員数」に起因するものでした。
ここ一年で未来像を描きます。
今回は、三養基営業所です。
三養基営業所は
みやき町の北茂安支所の一画を借家した事務所。
本庁とは距離があり
日常的に話をする機会はどうしても少ない。

(写真:みやき町北茂安庁舎内にある三養基営業所)
だからではないだろうが
日頃からの他部署との協議等が少ないのが原因と思われる
課題・問題が多く出ました。
そのなかで、企業団の内部的な問題ですが
退職者が今後増えます。
この企業団発足時に
採用された職員の大量退職が始ります。
今後5年間のうちに21名の退職者が予定されており
全体の三分の一弱にあたります。
現在の職員採用は
「行革」によって2年毎に1人の採用が続いています。
このことが内部的には大きな課題です
この職員数の減少、退職者の再雇用問題
将来の経営を見越した採用計画
いま、全職員で「未来像」の検討中ですが
個々の意見も
おおまかには「職員数」に起因するものでした。
ここ一年で未来像を描きます。
2013年05月27日
水道検針員の服装について
2か月に1度、水道メーターの検針を行っています。
検針員が、皆様のお宅へお伺いしていますが
お客様からは、水道の検針員かどうか分かりにくいとの
ご意見も頂いておりました。
そこで、これからは、写真のような
背中に「東部水道検針員」の文字が入った黄色のジャケットか
ベストを着用して、皆様のお宅へ検針に伺います。

(写真:この「ベスト」か「ジャケット」を着て検針作業を行います)
今までどおり「身分証明書」は必ず持っていますので
必要な時はいつでも提示を求めてください。
水道メーターの検針について
皆様のご協力とご理解をお願いします。
検針員が、皆様のお宅へお伺いしていますが
お客様からは、水道の検針員かどうか分かりにくいとの
ご意見も頂いておりました。
そこで、これからは、写真のような
背中に「東部水道検針員」の文字が入った黄色のジャケットか
ベストを着用して、皆様のお宅へ検針に伺います。
(写真:この「ベスト」か「ジャケット」を着て検針作業を行います)
今までどおり「身分証明書」は必ず持っていますので
必要な時はいつでも提示を求めてください。
水道メーターの検針について
皆様のご協力とご理解をお願いします。
2013年05月24日
各部署との意見会「工務2課」
引き続き、各部署との「問題・課題の意見会」
今回は、工務2課編です。

(写真:本庁舎3階の工務1課・工務2課)
ここでの議論も多種多様でした
その中での職員数の議論を紹介します。
現在の職員数は73名、平成6年当時は90名
行政改革で削減してきました。
定年退職者が、今後5年間で21名の予定です。
このことだけでも
今後の企業団経営に大きな支障になることは
容易に想像できます。
当然、現在議論中です
「職員の確保をどうするか?」はその議論に委ねますが
現状での課題は多々あります。
その中で具体的な議論になったことが
継承するにも「受け継ぐべき人がいない」
「現場第一と思うが事務処理にまわされている」
「業者にも高齢化が進んでいる」
「退職者の力も必要」
等の意見が出されました。
私も同感です
業務量の把握、業務量の再考、今後の事業計画
企業団の財政計画等々が必須です。
昨年から進めている長期経営計画を今年中にはまとめます
それと並行しての議論となるはずです。
今回は、工務2課編です。
(写真:本庁舎3階の工務1課・工務2課)
ここでの議論も多種多様でした
その中での職員数の議論を紹介します。
現在の職員数は73名、平成6年当時は90名
行政改革で削減してきました。
定年退職者が、今後5年間で21名の予定です。
このことだけでも
今後の企業団経営に大きな支障になることは
容易に想像できます。
当然、現在議論中です
「職員の確保をどうするか?」はその議論に委ねますが
現状での課題は多々あります。
その中で具体的な議論になったことが
継承するにも「受け継ぐべき人がいない」
「現場第一と思うが事務処理にまわされている」
「業者にも高齢化が進んでいる」
「退職者の力も必要」
等の意見が出されました。
私も同感です
業務量の把握、業務量の再考、今後の事業計画
企業団の財政計画等々が必須です。
昨年から進めている長期経営計画を今年中にはまとめます
それと並行しての議論となるはずです。
2013年05月23日
各部署との意見会「工務1課」
引き続き、各部署との「問題・課題の意見会」
今回は、工務1課編です。

(写真:本庁舎3階の工務1課・工務2課)
大きな地震に備えるためには水道管の耐震化は重要です。
地震に対する備えの最優先は浄水場であり
現在、耐震補強工事の施工中です。
次が、今年から計画する浄水場からのバイパス管と
口径150mm以上の主要な水道管路の耐震化
それに、老朽化している石綿セメント管の更新を
急いでいます。
こうゆう状況の中で
口径150mm以下の管路を耐震化の対象としなくていいのか?
との意見。
今、分かっていることは「やったほうが良い」
「やる」として費用は?、それに対応する人員は?
等の議論が必要。
現実を直視して「是非、議論を続けて欲しい」と要望
現在、策定中の長期計画では
避けられないテーマです。
各市町に水道水を送る送水管
この維持管理は重要です。
現在「用水係」が担当していますが
「人員不足で日常の維持管理ができない」
また「組織が建設中心の機構となっているので
維持管理主体の機構に改めるべき」との意見。
もっともな視点
「私の課題として考えていきたい」と思う。
また、浄水課を経験した職員から
「技術の継承には、浄水場での経験がプラスになる」
との意見が。
「浄水場への異動は人員数が限られる
経験者がそれを伝えて欲しい」とお願いし、その感触も得た。
今回の協議時間は1時間と予め決めていた
若い職員は「議論に飢えている」との
感触を得られたことが最大の収穫でした。
今回は、工務1課編です。
(写真:本庁舎3階の工務1課・工務2課)
大きな地震に備えるためには水道管の耐震化は重要です。
地震に対する備えの最優先は浄水場であり
現在、耐震補強工事の施工中です。
次が、今年から計画する浄水場からのバイパス管と
口径150mm以上の主要な水道管路の耐震化
それに、老朽化している石綿セメント管の更新を
急いでいます。
こうゆう状況の中で
口径150mm以下の管路を耐震化の対象としなくていいのか?
との意見。
今、分かっていることは「やったほうが良い」
「やる」として費用は?、それに対応する人員は?
等の議論が必要。
現実を直視して「是非、議論を続けて欲しい」と要望
現在、策定中の長期計画では
避けられないテーマです。
各市町に水道水を送る送水管
この維持管理は重要です。
現在「用水係」が担当していますが
「人員不足で日常の維持管理ができない」
また「組織が建設中心の機構となっているので
維持管理主体の機構に改めるべき」との意見。
もっともな視点
「私の課題として考えていきたい」と思う。
また、浄水課を経験した職員から
「技術の継承には、浄水場での経験がプラスになる」
との意見が。
「浄水場への異動は人員数が限られる
経験者がそれを伝えて欲しい」とお願いし、その感触も得た。
今回の協議時間は1時間と予め決めていた
若い職員は「議論に飢えている」との
感触を得られたことが最大の収穫でした。
2013年05月22日
各部署との意見会「営業課」
引き続き各部署との「問題・課題の意見会」
今回は、営業課編です。

(写真:本庁舎1階の営業課)
営業課では
「下水使用料の収納事務の受託」が話題になりました
これは「企業団エリアの下水使用料の徴収は受託する」
との方針のもとで、順次行なってきました。
今、協議しているのは神埼市
今年1年かけて詳細を決め、来年度実施を目指します。
ここでの課題は、受託後の仕事量、小規模水道エリアの取扱い
神埼市との協議の責任者等が話題に。
「受託が前提」であり、協議の進捗について課員で共有
を確認し、営業課のみの問題とせず
企業団として対応するように指示を行いました。
また、企業団内全体の電算統合の一環として
料金調定システムの更新作業が進んでいます
別途このブログでもお知らせしました。
具体の協議は関係する部署の代表による
委員会方式で協議がなされています。
その委員会のスピード感に対する不満や
上記の神埼市の下水使用料受託との
同時進行での準備作業の過密度が心配との意見が。
大枠のシナリオが決まれば
即業者を選定し、過密度を解消して欲しい
と委員会に指示。
他にも多くの意見がありました。
企業団は、全員野球が大原則
「みんなで考え みんなでやる」
その実行しかありません。
今回は、営業課編です。
(写真:本庁舎1階の営業課)
営業課では
「下水使用料の収納事務の受託」が話題になりました
これは「企業団エリアの下水使用料の徴収は受託する」
との方針のもとで、順次行なってきました。
今、協議しているのは神埼市
今年1年かけて詳細を決め、来年度実施を目指します。
ここでの課題は、受託後の仕事量、小規模水道エリアの取扱い
神埼市との協議の責任者等が話題に。
「受託が前提」であり、協議の進捗について課員で共有
を確認し、営業課のみの問題とせず
企業団として対応するように指示を行いました。
また、企業団内全体の電算統合の一環として
料金調定システムの更新作業が進んでいます
別途このブログでもお知らせしました。
具体の協議は関係する部署の代表による
委員会方式で協議がなされています。
その委員会のスピード感に対する不満や
上記の神埼市の下水使用料受託との
同時進行での準備作業の過密度が心配との意見が。
大枠のシナリオが決まれば
即業者を選定し、過密度を解消して欲しい
と委員会に指示。
他にも多くの意見がありました。
企業団は、全員野球が大原則
「みんなで考え みんなでやる」
その実行しかありません。
2013年05月21日
各部署との意見会「総務課」
今年度に入り各部署との
「問題・課題事案の意見会」を行ないました。
目的は、企業団全体で共有すべき問題の把握
今回は、総務課編です。

(写真:本庁舎2階の総務課)
日頃から「企業団全体を考える」を徹底していますので
改めての課題はありません。
そのなかで二つの議論を紹介します
ひとつは「長期の事業計画について」
長期の事業計画を見直し中
だから財政計画も変わります
人員計画の変更も生じるでしょう
そこで、どうしても「しなければいけない」との
他人任せ的な議論になりがちです。
しかし、全体を見る総務課は「それでは駄目だ」との
意見もでました。
「どうする」
「どうしていくのか」
を日頃から議論し、共有して「誰が」まで発展させよう
で、この会議は終了。
ふたつめは「技術の継承」について
日頃からこのブログでもお知らせしていますが
「事務の継承も必要」との意見がでました
この意見は他部署でもありました。
技術系の継承も当然だが、真意は「経営の継承」
しかし、そこが伝わっていないことがはっきりしました
言葉の使い方を「丁寧にせんと」
と反省。
「問題・課題事案の意見会」を行ないました。
目的は、企業団全体で共有すべき問題の把握
今回は、総務課編です。
(写真:本庁舎2階の総務課)
日頃から「企業団全体を考える」を徹底していますので
改めての課題はありません。
そのなかで二つの議論を紹介します
ひとつは「長期の事業計画について」
長期の事業計画を見直し中
だから財政計画も変わります
人員計画の変更も生じるでしょう
そこで、どうしても「しなければいけない」との
他人任せ的な議論になりがちです。
しかし、全体を見る総務課は「それでは駄目だ」との
意見もでました。
「どうする」
「どうしていくのか」
を日頃から議論し、共有して「誰が」まで発展させよう
で、この会議は終了。
ふたつめは「技術の継承」について
日頃からこのブログでもお知らせしていますが
「事務の継承も必要」との意見がでました
この意見は他部署でもありました。
技術系の継承も当然だが、真意は「経営の継承」
しかし、そこが伝わっていないことがはっきりしました
言葉の使い方を「丁寧にせんと」
と反省。
2013年05月20日
野球大会のレポート
先日、野球の試合があり「大差で勝った」
と聞きました。
当日、私は地域のお祭りで応援には行けず
試合のリポートをレフトで7番バッターのM君に頼んでいました
余談ですが、彼はスキーの国体選手です。
さて、今大会は国体の佐賀市選考会
佐賀市のブルースタジアムでの試合でした
以下、彼のレポート文です。
-----------------------------
我がチームは抽選に恵まれシード扱い
相手は、過去に何度か対戦したチームで戦績は5分と5分
緊迫した試合を予想したが
結果は、相手チームの自滅により大差での勝利
相手のチームは連戦で主力のメンバーが揃わなかった模様。
試合前に可愛い女子マネージャーがいて
「いいチームだなァー」と思っていたら
なんと二塁手
しかも上手い
うちの4番打者のサードへの痛烈な当たり
サードからの送球を「ヒョイ」と捕り5-4-3のダブルプレーに。
わたくし事ですが
1回表、2アウトの場面で2回目の打席
2ストライクと追い込まれた時
なんと味方のチームからの三振コール。
相手投手にも疲れが見え
それも「ありか」と頭をよぎったが
即「嫌だ」と打ち消したものの
セカンドの上手な女子選手と目が合い
いいとこ見せなきゃ
と力が入り、結果は見事な空降り三振。
やはり、野球は選手が揃うことと
ピッチャーがいないと試合にならない。

(写真:当企業団の野球チームのエース「アラフォー世代です」)
我がチームの
老体に鞭打ちながらも毎試合汗を流してくれる
「先輩エースに感謝を」
と再認識しました。
-----------------------------
あと2試合勝てば国体の県選考会への出場
しかし、次の試合は「たぶん負けるでしょう」と言う
「根性なし」のチームです。
次の試合は、2週間後
期待しないで結果を待ちます。
と聞きました。
当日、私は地域のお祭りで応援には行けず
試合のリポートをレフトで7番バッターのM君に頼んでいました
余談ですが、彼はスキーの国体選手です。
さて、今大会は国体の佐賀市選考会
佐賀市のブルースタジアムでの試合でした
以下、彼のレポート文です。
-----------------------------
我がチームは抽選に恵まれシード扱い
相手は、過去に何度か対戦したチームで戦績は5分と5分
緊迫した試合を予想したが
結果は、相手チームの自滅により大差での勝利
相手のチームは連戦で主力のメンバーが揃わなかった模様。
試合前に可愛い女子マネージャーがいて
「いいチームだなァー」と思っていたら
なんと二塁手
しかも上手い
うちの4番打者のサードへの痛烈な当たり
サードからの送球を「ヒョイ」と捕り5-4-3のダブルプレーに。
わたくし事ですが
1回表、2アウトの場面で2回目の打席
2ストライクと追い込まれた時
なんと味方のチームからの三振コール。
相手投手にも疲れが見え
それも「ありか」と頭をよぎったが
即「嫌だ」と打ち消したものの
セカンドの上手な女子選手と目が合い
いいとこ見せなきゃ
と力が入り、結果は見事な空降り三振。
やはり、野球は選手が揃うことと
ピッチャーがいないと試合にならない。
(写真:当企業団の野球チームのエース「アラフォー世代です」)
我がチームの
老体に鞭打ちながらも毎試合汗を流してくれる
「先輩エースに感謝を」
と再認識しました。
-----------------------------
あと2試合勝てば国体の県選考会への出場
しかし、次の試合は「たぶん負けるでしょう」と言う
「根性なし」のチームです。
次の試合は、2週間後
期待しないで結果を待ちます。
2013年05月17日
「筑後川フェスティバル」への協力依頼ある
先日、南小国町(熊本県)の河津町長が
わざわざお見えになりました。
主旨は「筑後川フェスティバル」への協力の依頼。
この筑後川フェスティバルは今回で27回目
昨年は佐賀市が開催事務局でした。

(写真:昨年の「第26回 筑後川フェスティバル in 佐賀」のチラシ)
筑後川流域の福岡・佐賀・大分・熊本の
4県持ちまわりで、毎年、開催されており
今年は南小国町が担当されます。
4つの県を流れる大河である筑後川は
流域の生活に密着しています。
それを反映して
川に関係する数多くの活動団体が存在し
活発な活動を展開されてきました。
しかし、当時団体同士の交流はなく
県境や市町村を越えて筑後川について語りあえる場
として、この筑後川フェスタが始まりました。
多くの方のお陰で
筑後川流域新聞の発行も定期的に行なわれ
地域間の交流が盛んになりました。
その主旨での、筑後川フェスティバルへの協力の依頼
筑後川の恩恵を頂いている
東部水道企業団としても支援と協力・参加を
させていただきます。
詳しい日程や内容が決まれば
改めて皆様にお知らせします。
わざわざお見えになりました。
主旨は「筑後川フェスティバル」への協力の依頼。
この筑後川フェスティバルは今回で27回目
昨年は佐賀市が開催事務局でした。

(写真:昨年の「第26回 筑後川フェスティバル in 佐賀」のチラシ)
筑後川流域の福岡・佐賀・大分・熊本の
4県持ちまわりで、毎年、開催されており
今年は南小国町が担当されます。
4つの県を流れる大河である筑後川は
流域の生活に密着しています。
それを反映して
川に関係する数多くの活動団体が存在し
活発な活動を展開されてきました。
しかし、当時団体同士の交流はなく
県境や市町村を越えて筑後川について語りあえる場
として、この筑後川フェスタが始まりました。
多くの方のお陰で
筑後川流域新聞の発行も定期的に行なわれ
地域間の交流が盛んになりました。
その主旨での、筑後川フェスティバルへの協力の依頼
筑後川の恩恵を頂いている
東部水道企業団としても支援と協力・参加を
させていただきます。
詳しい日程や内容が決まれば
改めて皆様にお知らせします。
2013年05月16日
バスは地域の宝
朝のスピーチからです。
彼は、人の世話を苦もなくする好青年です。
--------------------------------
普段は車で通勤しているが
仕事帰りの飲酒を伴う懇親会等には、バスを利用している。
乗ればサラリーマンや通学の小学生、年配の方々が
よく利用されている。
利用する路線の本数は1時間に1本程度で多くはない。

(写真:朝礼とスピーチの様子「総務課」)
そんなバスですが
前市長の時、赤字が続いている市営バスの見直しから
民営化や事業縮小が検討されました。
利用の方の多くは車の運転ができない方で
バスは地域の財産だと思います。
無くなれば年配者の外出は減り
学校に行くのも大変不便になることが想像できます。
その後、市長が代わり合理化を徹底し
経営を維持することになりました。
一人でも多くの利用が維持につながると思い
自分も積極的に利用するし
職員にも利用を呼びかけたくて朝のスピーチの
ネタとしました。
--------------------------------
特別、他意はないが
バスを外から見て空席が目立つと考えるか
バスの中から
乗って利用されている人の状況を見る人との
違いなんでしょう。
彼は、人の世話を苦もなくする好青年です。
--------------------------------
普段は車で通勤しているが
仕事帰りの飲酒を伴う懇親会等には、バスを利用している。
乗ればサラリーマンや通学の小学生、年配の方々が
よく利用されている。
利用する路線の本数は1時間に1本程度で多くはない。
(写真:朝礼とスピーチの様子「総務課」)
そんなバスですが
前市長の時、赤字が続いている市営バスの見直しから
民営化や事業縮小が検討されました。
利用の方の多くは車の運転ができない方で
バスは地域の財産だと思います。
無くなれば年配者の外出は減り
学校に行くのも大変不便になることが想像できます。
その後、市長が代わり合理化を徹底し
経営を維持することになりました。
一人でも多くの利用が維持につながると思い
自分も積極的に利用するし
職員にも利用を呼びかけたくて朝のスピーチの
ネタとしました。
--------------------------------
特別、他意はないが
バスを外から見て空席が目立つと考えるか
バスの中から
乗って利用されている人の状況を見る人との
違いなんでしょう。
2013年05月15日
5月課長会の報告
経営会議と戦略会議の設置を正式に提案しました。
既存の最高決定機関は課長会議
もちろん、通常の場合問題はありません。
しかし、現在長期の経営計画を議論中
それを計画で終わらせたくはない
そのためには、全員参加の議論が必要
そこで日常業務における
課題の整理と確認・徹底を仮称「戦略会議」で
企業団の方針決定に関わる案件を
仮称「経営会議」にて議論し決定していきたい。
もちろん、既存の課長会との役割分担も配慮する
大まかには
そんなイメージを課長会に提案しました。
その中での議論は
「会議が増えて会議倒れになる可能性がある。」
「課長会とのすみ分けの議論が必要。」
「メンバー構成は?」
等の意見がありました。
ここでは、会議をするのが目的ではないので
実効性のある仕組みをつくろうで決着。
他にも盛りだくさんの議論がありました
新年度になって課長会のメンバーにも変化があり
活発な討議の場になる予感がします。
具体的なことは順次お知らせします。
既存の最高決定機関は課長会議
もちろん、通常の場合問題はありません。
しかし、現在長期の経営計画を議論中
それを計画で終わらせたくはない
そのためには、全員参加の議論が必要
そこで日常業務における
課題の整理と確認・徹底を仮称「戦略会議」で
企業団の方針決定に関わる案件を
仮称「経営会議」にて議論し決定していきたい。
もちろん、既存の課長会との役割分担も配慮する
大まかには
そんなイメージを課長会に提案しました。
その中での議論は
「会議が増えて会議倒れになる可能性がある。」
「課長会とのすみ分けの議論が必要。」
「メンバー構成は?」
等の意見がありました。
ここでは、会議をするのが目的ではないので
実効性のある仕組みをつくろうで決着。
他にも盛りだくさんの議論がありました
新年度になって課長会のメンバーにも変化があり
活発な討議の場になる予感がします。
具体的なことは順次お知らせします。
2013年05月14日
クールビズ開始しました
今年もクールビズを5月から開始しました
夏の風物詩とまでは言わないが、すっかり定着しました。
一昨年までは、6月実施でしたが
昨年から東日本大震災での電力不足も考慮し
一か月の前倒しで実施し、今年もそれに倣いました。
個人的にはネクタイを外すことが好きであり
大歓迎です。

(写真:昨年の環境省啓蒙ポスター)
本来の主旨は、冷房を控えて電気の使用量を減らし
二酸化炭素の排出量を削減するためです。
冷房を入れるのは6月になってから
だから、ここ一か月はネクタイを外し
少しでも快適に仕事をする、ということになります。
ただ朝夕は、肌寒い日々が続きました
が、長期予報では、今年の夏は例年以上に暑い
とも聞きます。
話は少し変わりますが
昨年から「男の日傘」が話題になっていました
今年はブレイクの年にする、との業界の声も聞きます。
紫外線を恐れて、日傘をさす
それが、若い男子
「男の日傘」そんな世相なんですね。
夏の風物詩とまでは言わないが、すっかり定着しました。
一昨年までは、6月実施でしたが
昨年から東日本大震災での電力不足も考慮し
一か月の前倒しで実施し、今年もそれに倣いました。
個人的にはネクタイを外すことが好きであり
大歓迎です。

(写真:昨年の環境省啓蒙ポスター)
本来の主旨は、冷房を控えて電気の使用量を減らし
二酸化炭素の排出量を削減するためです。
冷房を入れるのは6月になってから
だから、ここ一か月はネクタイを外し
少しでも快適に仕事をする、ということになります。
ただ朝夕は、肌寒い日々が続きました
が、長期予報では、今年の夏は例年以上に暑い
とも聞きます。
話は少し変わりますが
昨年から「男の日傘」が話題になっていました
今年はブレイクの年にする、との業界の声も聞きます。
紫外線を恐れて、日傘をさす
それが、若い男子
「男の日傘」そんな世相なんですね。
2013年05月13日
水道週間児童図画の展示
当企業団の北茂安浄水場2階ロビーに
児童図画作品を展示しています。

(写真:図画作品の展示状況1)
現在展示しているのは、昨年度に募集を行い
12校の小学校からの応募総数452作品のうちの36作品です。

(写真:図画作品の展示状況2)
今年も、域内の小学校(5年生)へ作品応募を
お願いしました。

(写真:図画作品の展示状況3)
そろそろ、小学生の浄水場見学のシーズンが始まります。
浄水場では、施設見学の受け付けも行っていますので
浄水場見学にあわせて図画の見学もいかがでしょうか。
児童図画作品を展示しています。

(写真:図画作品の展示状況1)
現在展示しているのは、昨年度に募集を行い
12校の小学校からの応募総数452作品のうちの36作品です。

(写真:図画作品の展示状況2)
今年も、域内の小学校(5年生)へ作品応募を
お願いしました。

(写真:図画作品の展示状況3)
そろそろ、小学生の浄水場見学のシーズンが始まります。
浄水場では、施設見学の受け付けも行っていますので
浄水場見学にあわせて図画の見学もいかがでしょうか。
2013年05月10日
激論白熱「でも、嬉しい議論」
前回に続き
給水車購入についての議論での一幕を紹介します。
工務の二つの課で
1年間「議論を重ねてきた」ことは先日書きました。
そこで激しい「やりとり」がありました
それは、工務の皆さんの意見を代表した形で
K課長が「即、購入」論を
一方の相手は「わたし」
当然、必要性は認める
しかし、その前に「危機管理のシナリオ、その中での必要性を」
の主張が対立しました。
議論の概要は
「長年の思い」を実現したい
そのために、我々(特に工務系の職員)は議論を重ねてきた
「企業長も必要と言った」
私の主旨は「根拠付けの作業(危機管理)の概要は出来た」
そのことから「必要性は承知できる」
しかし「まだ、肝心のどこに使うがはっきりしていない」
と、主張。
また、K課長は給水車がないことで
他市への応援も「躊躇してきた」
災害で苦しんでいるのを知りながら
即「給水応援に行けない」辛さを幾度も経験してきた。
職員からも「給水車もない、はみっともない」
との本音も
で、私は「全て、もっとも」
だから「どこにどう使う」の具体論が必要と。

(写真:応急拠点給水訓練には、1トンタンクを使用しています)
議論は対立したままで、その場は終わりました
その後、私なりに考えをまとめ
次のことを「指示」
それは、最悪の事故の時
山間部(高所地区)への給水はできない
その解決策として「地下水利用」があるはず
問題エリア内の
公的な施設、個人の井戸も含めて「救える」部分と
「給水車でしか対応できない区域」を即、調査して欲しい。
その結果は翌日には私のところに
これで「オッケイ」でした。
給水車は「無いより、あった方が良い」
それでは利用者の皆様への説明ができません。
しかし、一連の議論のなかで
皆様に自信をもって購入の予算を提案できます。
給水車購入についての議論での一幕を紹介します。
工務の二つの課で
1年間「議論を重ねてきた」ことは先日書きました。
そこで激しい「やりとり」がありました
それは、工務の皆さんの意見を代表した形で
K課長が「即、購入」論を
一方の相手は「わたし」
当然、必要性は認める
しかし、その前に「危機管理のシナリオ、その中での必要性を」
の主張が対立しました。
議論の概要は
「長年の思い」を実現したい
そのために、我々(特に工務系の職員)は議論を重ねてきた
「企業長も必要と言った」
私の主旨は「根拠付けの作業(危機管理)の概要は出来た」
そのことから「必要性は承知できる」
しかし「まだ、肝心のどこに使うがはっきりしていない」
と、主張。
また、K課長は給水車がないことで
他市への応援も「躊躇してきた」
災害で苦しんでいるのを知りながら
即「給水応援に行けない」辛さを幾度も経験してきた。
職員からも「給水車もない、はみっともない」
との本音も
で、私は「全て、もっとも」
だから「どこにどう使う」の具体論が必要と。
(写真:応急拠点給水訓練には、1トンタンクを使用しています)
議論は対立したままで、その場は終わりました
その後、私なりに考えをまとめ
次のことを「指示」
それは、最悪の事故の時
山間部(高所地区)への給水はできない
その解決策として「地下水利用」があるはず
問題エリア内の
公的な施設、個人の井戸も含めて「救える」部分と
「給水車でしか対応できない区域」を即、調査して欲しい。
その結果は翌日には私のところに
これで「オッケイ」でした。
給水車は「無いより、あった方が良い」
それでは利用者の皆様への説明ができません。
しかし、一連の議論のなかで
皆様に自信をもって購入の予算を提案できます。
2013年05月09日
うちの職員は凄い
昨日の続きです
「給水車購入」に対し職員との議論の内容を少し紹介します。
事故や災害で「水道水の供給がストップする」
この防止が最大の課題です。
特に「山間部(高所地区)への対応」です
浄水場に近いところで事故があり送水管が破断する
これが「最悪のシナリオ」とはお知らせしました
その場合、山間部(高所地区)への水道水の供給がストップします。

(写真:「施設破損時の影響」についての説明の様子)
その場合は、どう対応するか?その手段は?
「給水車で水を送る」として、その範囲や対象の戸数は?
地下水や井戸水の利用の可能性は?
使える戸数は?
地域や利用者の皆様への周知の方法は?
応援の体制は?等々、議論を重ねてきました。
一方では、給水車の値段は約1千万円
危機の際の必要性はわかるが、通常の利用頻度は?
また、逆に他都市での応援も
「即、行ける」体制と認識はどうか?
そうなった場合のフォローの体制は?
こんな議論が「給水車購入」の
議論の中で職員間の共通認識となっていきました
わたしが一番求めていることは「このこと」です。
議論をする
そして、みんなで「決める」
嬉しい議論でした。
まだ伝えたいことがあります
明日もこの話題です。
「給水車購入」に対し職員との議論の内容を少し紹介します。
事故や災害で「水道水の供給がストップする」
この防止が最大の課題です。
特に「山間部(高所地区)への対応」です
浄水場に近いところで事故があり送水管が破断する
これが「最悪のシナリオ」とはお知らせしました
その場合、山間部(高所地区)への水道水の供給がストップします。
(写真:「施設破損時の影響」についての説明の様子)
その場合は、どう対応するか?その手段は?
「給水車で水を送る」として、その範囲や対象の戸数は?
地下水や井戸水の利用の可能性は?
使える戸数は?
地域や利用者の皆様への周知の方法は?
応援の体制は?等々、議論を重ねてきました。
一方では、給水車の値段は約1千万円
危機の際の必要性はわかるが、通常の利用頻度は?
また、逆に他都市での応援も
「即、行ける」体制と認識はどうか?
そうなった場合のフォローの体制は?
こんな議論が「給水車購入」の
議論の中で職員間の共通認識となっていきました
わたしが一番求めていることは「このこと」です。
議論をする
そして、みんなで「決める」
嬉しい議論でした。
まだ伝えたいことがあります
明日もこの話題です。
2013年05月08日
給水車購入の議論の経過
ここに就任した時
実は直感で「給水車がない、何故?」と問いました
直感とは「内情も分からずに」と言う意味です。
それを聞き、特に危機時には現場で対応する工務の職員や
危機管理を計画する立場の職員は
「長年の課題がこれで解決する」と考えたようです。
そこで1年かけて、給水車の管理や運用は当然のこと
他都市への支援計画に至るまで
綿密に話し合い、内定して
昨年度の予算策定時に提案がありました。

(写真:佐賀市上下水道局所有の給水車)
当初の私は「内情も分からずに提案」しましたが
給水車の必要性や優先度を考える際に
大事なことがあります
それは、東部水道の域内で必要な時の検証でした。
これは、具体的な場面を想定しての必要性が必須です
それが先般お知らせした
「一番危険な状況」を想定した危機管理計画でした。
その中で「高所地域には水の供給ができない」
他の手段(地下水利用等)を検討しても
「供給ができない地域がある」ことがはっきりしました。
もちろん、そうなった時には
1台程度の給水車では対応はできません
周辺地域からの応援や自衛隊への協力も必要です。
しかし、東日本震災後の危機対応への高まりと
区域内での「そなえ」として、給水車の購入時期は今だ!
と判断させてもらいました。
実は直感で「給水車がない、何故?」と問いました
直感とは「内情も分からずに」と言う意味です。
それを聞き、特に危機時には現場で対応する工務の職員や
危機管理を計画する立場の職員は
「長年の課題がこれで解決する」と考えたようです。
そこで1年かけて、給水車の管理や運用は当然のこと
他都市への支援計画に至るまで
綿密に話し合い、内定して
昨年度の予算策定時に提案がありました。
(写真:佐賀市上下水道局所有の給水車)
当初の私は「内情も分からずに提案」しましたが
給水車の必要性や優先度を考える際に
大事なことがあります
それは、東部水道の域内で必要な時の検証でした。
これは、具体的な場面を想定しての必要性が必須です
それが先般お知らせした
「一番危険な状況」を想定した危機管理計画でした。
その中で「高所地域には水の供給ができない」
他の手段(地下水利用等)を検討しても
「供給ができない地域がある」ことがはっきりしました。
もちろん、そうなった時には
1台程度の給水車では対応はできません
周辺地域からの応援や自衛隊への協力も必要です。
しかし、東日本震災後の危機対応への高まりと
区域内での「そなえ」として、給水車の購入時期は今だ!
と判断させてもらいました。
2013年05月07日
「佐賀県筑後川下流域環境協議会」を設立
先日、佐賀県、佐賀西部広域水道企業団と
当企業団の三者で
「佐賀県筑後川下流域環境協議会」が設立されました。
目的は、筑後川の下流域の環境保全
具体の取り組みは
河川由来の漂流物による水質悪化や水環境の保全への支援。
筑後川の水を利用させて頂いている一員として
何らか、形としても表していきたい、との思いによるものです。
福岡県側は、すでに実施されています。
当企業団は、今までも山林の保全や清掃活動
漂着ゴミの撤去等に参加してきましたが
それとは別に3者共同で環境保全に寄与しよう、との主旨です。

(写真:昨年の「有明海クリーンアップ作戦」の様子
県、関係市町が中心として取り組まれ、当企業団の職員も
ボランティア、漁業関係者の方と一緒に参加しています)
協議会の発足後
改めて、筑後川の水資源開発の計画や進捗状況
また課題等に対して議論を深めました。
佐賀県民87万人の37%にあたる
約32万人の方が利用されている筑後川
安全で安定的な水道水を供給するためには
欠かせないことだと思います。
当企業団の三者で
「佐賀県筑後川下流域環境協議会」が設立されました。
目的は、筑後川の下流域の環境保全
具体の取り組みは
河川由来の漂流物による水質悪化や水環境の保全への支援。
筑後川の水を利用させて頂いている一員として
何らか、形としても表していきたい、との思いによるものです。
福岡県側は、すでに実施されています。
当企業団は、今までも山林の保全や清掃活動
漂着ゴミの撤去等に参加してきましたが
それとは別に3者共同で環境保全に寄与しよう、との主旨です。

(写真:昨年の「有明海クリーンアップ作戦」の様子
県、関係市町が中心として取り組まれ、当企業団の職員も
ボランティア、漁業関係者の方と一緒に参加しています)
協議会の発足後
改めて、筑後川の水資源開発の計画や進捗状況
また課題等に対して議論を深めました。
佐賀県民87万人の37%にあたる
約32万人の方が利用されている筑後川
安全で安定的な水道水を供給するためには
欠かせないことだと思います。
2013年05月02日
「佐賀市川副町」の今年の工事予定
現在、佐賀市川副町では「早津江」、「東古賀」地区等で
下水道の布設工事が行なわれています。
それに伴って
支障になる水道管の布設替えを行ないます。

(写真:水道管の布設工事状況)
この地区の水道管は
昭和40年~50年代に布設した水道管で「石綿管」や
小口径の水道管が多く
水道使用のピーク時には水圧低下で
ご不自由をおかけすることもありました。
今回、下水道布設に伴って
直接支障となる水道管以外も
「老朽管の布施替え」、「増径」を行います。
今年の予定工事が終われば
「早津江」、「東古賀」地区の大部分の石綿管は無くなります。
なお、大詫間地区と他一部にまだ石綿管が
残存していますので、平成32年度の布設替え完了を目指し
努力していきます。
ご不自由をお掛けしますが
宜しくお願いします。
下水道の布設工事が行なわれています。
それに伴って
支障になる水道管の布設替えを行ないます。

(写真:水道管の布設工事状況)
この地区の水道管は
昭和40年~50年代に布設した水道管で「石綿管」や
小口径の水道管が多く
水道使用のピーク時には水圧低下で
ご不自由をおかけすることもありました。
今回、下水道布設に伴って
直接支障となる水道管以外も
「老朽管の布施替え」、「増径」を行います。
今年の予定工事が終われば
「早津江」、「東古賀」地区の大部分の石綿管は無くなります。
なお、大詫間地区と他一部にまだ石綿管が
残存していますので、平成32年度の布設替え完了を目指し
努力していきます。
ご不自由をお掛けしますが
宜しくお願いします。