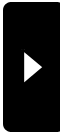2012年05月31日
水道週間始まる
国や県が主体となり「水道週間」が
今年も6月1日から7日までの期間で開催されます。
日本の水道は、ほとんどの国民が利用できるまで普及し
必要不可欠な社会基盤の施設です。
一方、日本の人口は減少に転じ
当企業団ではまだ、僅かながらも給水人口は増えていますが
2~3年後には減少することを予想しています。
人口の減少は経営状況に直結して
厳しくなることが予想されます。
反面、老朽化しつつある施設の更新や
耐震等の災害対策は推進が必要です。
とくに東日本大災害を教訓とした
災害に強い水道づくりや各家庭への応急的な給水
や復旧体制を整えることは重要なことです。
こうしたことを皆様にお伝えして
理解と協力を得るための水道週間です。

(写真:今年度の水道週間の案内ポスター)
今年のスローガンは「さあ今日も 水と元気が 蛇口から」です。
企業団でも、水道を身近に感じていただこうと
構成市町の小学校20校の5年生に対して
「水道週間 児童図画募集」をお願いしているところです。
今年も6月1日から7日までの期間で開催されます。
日本の水道は、ほとんどの国民が利用できるまで普及し
必要不可欠な社会基盤の施設です。
一方、日本の人口は減少に転じ
当企業団ではまだ、僅かながらも給水人口は増えていますが
2~3年後には減少することを予想しています。
人口の減少は経営状況に直結して
厳しくなることが予想されます。
反面、老朽化しつつある施設の更新や
耐震等の災害対策は推進が必要です。
とくに東日本大災害を教訓とした
災害に強い水道づくりや各家庭への応急的な給水
や復旧体制を整えることは重要なことです。
こうしたことを皆様にお伝えして
理解と協力を得るための水道週間です。
(写真:今年度の水道週間の案内ポスター)
今年のスローガンは「さあ今日も 水と元気が 蛇口から」です。
企業団でも、水道を身近に感じていただこうと
構成市町の小学校20校の5年生に対して
「水道週間 児童図画募集」をお願いしているところです。
2012年05月30日
第4回 係長会議
係長による月一回の定例会議を行なっています
会議発足の理由は「情報の共有」と「説明能力アップ」
自分のポジション優先、すなわち「縦割り思考」を
少し感じたことと「相手に伝える」話術の訓練でした。
今回が4回目、会議の運営もテーマも係長会議に一任です
私は傍聴者という立場で出席しています。

(写真:係長会議の様子)
さて、本日のテーマは「誤検針の事例報告」
絶対にあってはいけないことですが今年1月に発生しました。
誤検針の相手方は「ノリ協業加工の施設所有者」
通常多くの水を利用されており、誤って請求した金額も多額となりました。
ここでの問題は三点
一つめは誤った検針、メーターの数字を間違っての入力
これは人間がやることで間違いもあり得ますが
再チェックで大方は解消するはず、当然「検針員」の皆様に指示。
二つめが問題で、私たちの事務方のチェック体制です
通常、全てのデータから抽出・選別し、職員の目で現地確認して
誤検針を発見しますが、季節的大口使用者ということで
「誤検針チェック最終ライン」の自覚が薄れ
これを見落とした事に危機意識を持ちます。
「厳重な注意」と「再発防止の具体策」を指示しました。
三つめは、お客さま対応です
「ご迷惑をかけた」の姿勢を問いました。
関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけしました
再発防止に真剣に取組んでいるということで
ご勘弁を頂きたいと思います。
係長会議でも担当の部署だけの問題ではない
との反省が聞けたのは救いでした。
会議発足の理由は「情報の共有」と「説明能力アップ」
自分のポジション優先、すなわち「縦割り思考」を
少し感じたことと「相手に伝える」話術の訓練でした。
今回が4回目、会議の運営もテーマも係長会議に一任です
私は傍聴者という立場で出席しています。
(写真:係長会議の様子)
さて、本日のテーマは「誤検針の事例報告」
絶対にあってはいけないことですが今年1月に発生しました。
誤検針の相手方は「ノリ協業加工の施設所有者」
通常多くの水を利用されており、誤って請求した金額も多額となりました。
ここでの問題は三点
一つめは誤った検針、メーターの数字を間違っての入力
これは人間がやることで間違いもあり得ますが
再チェックで大方は解消するはず、当然「検針員」の皆様に指示。
二つめが問題で、私たちの事務方のチェック体制です
通常、全てのデータから抽出・選別し、職員の目で現地確認して
誤検針を発見しますが、季節的大口使用者ということで
「誤検針チェック最終ライン」の自覚が薄れ
これを見落とした事に危機意識を持ちます。
「厳重な注意」と「再発防止の具体策」を指示しました。
三つめは、お客さま対応です
「ご迷惑をかけた」の姿勢を問いました。
関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけしました
再発防止に真剣に取組んでいるということで
ご勘弁を頂きたいと思います。
係長会議でも担当の部署だけの問題ではない
との反省が聞けたのは救いでした。
2012年05月29日
日水協 佐賀県支部の役員会と総会
18日は日水協 佐賀県支部の役員会と総会に出席
日水協とは日本水道協会のことで
東北大震災では機敏な行動と全国からの応援で
想定より早く水道は復旧
「水道一家」と賞賛されました。
多久市で開催、開催市である横尾多久市長のあいさつ
「水道の水は蛇口をひねれば無尽蔵」との認識が一般的。
でも違う、多久も平成6年に大渇水にみまわれ全国ニュースに
いまはお陰で「大丈夫」になった。
多久聖廟の孔子さんは「水」との縁が深い
中国の皇帝のシンボルは龍。
その龍、その時代は皇帝以外は孔子関連しか使えない
「龍は水」だから孔子廟は水の神様でもある。

(写真:多久聖廟 多久市役所のホームページから転載しています)
多久聖廟とは:
多久家の四代領主多久茂文は人材育成に重きを置いた人物で、
のちに東原庠舎と呼ばれる学問所を建て、そのシンボルとして
宝永5年(1708年)孔子像、四配(顔子、曽子、子思子、孟子)を
祀る廟として完成しました。
国内に存在する孔子廟では足利学校、閑谷学校についで古く、
またもっとも壮麗な孔子廟だといわれています。
(多久市役所HPを参照)
そんな挨拶をいただき、議事は進行
H23の決算、H24の計画、予算も了承。
年一回、県内の水道の関係者が一同に集う
そのなかで東部水道企業団の課題である
「長期の経営」や「危機管理」は共通の課題。
情報交換や今後の連携での課題解決等々の話ができ
有意義でした。
日水協とは日本水道協会のことで
東北大震災では機敏な行動と全国からの応援で
想定より早く水道は復旧
「水道一家」と賞賛されました。
多久市で開催、開催市である横尾多久市長のあいさつ
「水道の水は蛇口をひねれば無尽蔵」との認識が一般的。
でも違う、多久も平成6年に大渇水にみまわれ全国ニュースに
いまはお陰で「大丈夫」になった。
多久聖廟の孔子さんは「水」との縁が深い
中国の皇帝のシンボルは龍。
その龍、その時代は皇帝以外は孔子関連しか使えない
「龍は水」だから孔子廟は水の神様でもある。

(写真:多久聖廟 多久市役所のホームページから転載しています)
多久聖廟とは:
多久家の四代領主多久茂文は人材育成に重きを置いた人物で、
のちに東原庠舎と呼ばれる学問所を建て、そのシンボルとして
宝永5年(1708年)孔子像、四配(顔子、曽子、子思子、孟子)を
祀る廟として完成しました。
国内に存在する孔子廟では足利学校、閑谷学校についで古く、
またもっとも壮麗な孔子廟だといわれています。
(多久市役所HPを参照)
そんな挨拶をいただき、議事は進行
H23の決算、H24の計画、予算も了承。
年一回、県内の水道の関係者が一同に集う
そのなかで東部水道企業団の課題である
「長期の経営」や「危機管理」は共通の課題。
情報交換や今後の連携での課題解決等々の話ができ
有意義でした。
2012年05月28日
「長期の財政計画」策定へ
今年の大きな課題として
ふたつを重点課題として内部で協議をしています。
ひとつは先日紹介した「危機管理」
ふたつめは「長期の財政計画」です。
当然、中期の計画はキチンとあり
その経過は順調に推移しています。

(写真:標高50m地点に設置された「白壁中継ポンプ場」)
ここでの想定は「20年後の姿」です
次の三点を問題提起しました。
水道は「未来永劫」必要です
しかし、極論すれば東部水道企業団が経営する
水道水かどうかは利用者の皆様の判断です。
20年後も東部水道企業団が「皆様の水道」を
担うためには皆様の信頼が必須です。
一点目の課題は
その信頼を得る「経営」とはどんなことか?
二点目は将来まで現在のエリアは普遍なのか?
東部水道企業団は広域での経営を実施していますが
周辺自冶体との関係はどうなるのか?
また、どうあるべきか。
三点目は施設の更新に対しての考え方と財源は?
ひとつひとつの課題は難しくて重いが
いろんな状況を想定して
未来を考えることが出来る企業団となりたい。
そんな企業団職員をめざしたいと思っています。
ふたつを重点課題として内部で協議をしています。
ひとつは先日紹介した「危機管理」
ふたつめは「長期の財政計画」です。
当然、中期の計画はキチンとあり
その経過は順調に推移しています。
(写真:標高50m地点に設置された「白壁中継ポンプ場」)
ここでの想定は「20年後の姿」です
次の三点を問題提起しました。
水道は「未来永劫」必要です
しかし、極論すれば東部水道企業団が経営する
水道水かどうかは利用者の皆様の判断です。
20年後も東部水道企業団が「皆様の水道」を
担うためには皆様の信頼が必須です。
一点目の課題は
その信頼を得る「経営」とはどんなことか?
二点目は将来まで現在のエリアは普遍なのか?
東部水道企業団は広域での経営を実施していますが
周辺自冶体との関係はどうなるのか?
また、どうあるべきか。
三点目は施設の更新に対しての考え方と財源は?
ひとつひとつの課題は難しくて重いが
いろんな状況を想定して
未来を考えることが出来る企業団となりたい。
そんな企業団職員をめざしたいと思っています。
2012年05月25日
筑後川流域講座を受講しました
5月21日(月) 久留米市にある久留米大学御井キャンパスにて
筑後川流域講座2012のひとコマを受講してきた職員からの報告です。
---(記事:総務課 福川)-------------------
筑後川流域講座とは、筑後川のものしり博士になろうということで、
豊かな自然と長い歴史に培われた文化を持つ筑後川流域において
個性豊かに活動しておられる方を講師に、
流域の課題や対策について、学生さんは単位の一環として、
一般の方でも興味のある方は受講できるという公開講座で、
今年で12年目になるそうです。
学生さんは単位取得のためレポートが必要であり、
一般の方も「学芸員認定コース」を希望される場合は、
認定レポートを提出することができるそうです。
面接や審査があり、現在、認定された学芸員は56名。
毎年一般からの受講は200名ぐらいあるけれども、
学芸員の認定にはある程度のハードルもあるので
近年は数名程度の応募。
それにこだわらずに、気軽に参加してほしいと
事務局である「筑後川まるごと博物館」運営委員会の
鍋田事務局長からお聞きしました。

(写真:講座が開かれた久留米大学御井キャンパス)
久留米大学以外でも、筑後川防災施設である
「くるめウス」にて開催されることもあるそうです。
受講料は無料ですが、現地見学会の場合はバス代等の経費が必要。
今回は、「筑後川上流域の自然エネルギー」の講座でした。

(写真:講師の甲斐先生が、まず朝倉の三連水車について紹介)
甲斐先生は、日田市民環境会議エネルギー部会長として
様々な環境問題に取り組んでおられるそうです。
今回の講演内容は・・・
・日田、玖珠地域は自然エネルギー利用の先進地
・実用化されたほとんど全ての自然エネルギーを利用
・太陽光から水力、木材チップを使ったエネルギーまで様々
・九重町の八丁原地熱発電所は日本一
・大規模でなく、地元密着の小水力発電も多い
・生ゴミ等利用のメタンガス発電
・木質バイオマス発電も国内最大級 など
当企業団でも、旧川副浄水場跡地にメガソーラーの誘致計画
が進行していますが、先生言われるには・・・
大手資本ではなく、地元密着で地元に雇用、地元に利益
そのスタンスで取り組むことに意義があるのではと。
また、江戸時代から現在までおなじように水力を利用して
陶土を粉砕する唐臼の紹介もあり、興味を引かれました。

(写真:びっしり詰まった会場 前列は一般参加の方が多数)
今回の自然エネルギー以外にも、中流域の江戸時代からの堰や
下流では佐野常民の講座等もあり、筑後川について
幅広い知識を得るカリキュラムとなっています。
今後も機会があれば、他の講座にも参加したいと思っています。
筑後川流域講座2012のひとコマを受講してきた職員からの報告です。
---(記事:総務課 福川)-------------------
筑後川流域講座とは、筑後川のものしり博士になろうということで、
豊かな自然と長い歴史に培われた文化を持つ筑後川流域において
個性豊かに活動しておられる方を講師に、
流域の課題や対策について、学生さんは単位の一環として、
一般の方でも興味のある方は受講できるという公開講座で、
今年で12年目になるそうです。
学生さんは単位取得のためレポートが必要であり、
一般の方も「学芸員認定コース」を希望される場合は、
認定レポートを提出することができるそうです。
面接や審査があり、現在、認定された学芸員は56名。
毎年一般からの受講は200名ぐらいあるけれども、
学芸員の認定にはある程度のハードルもあるので
近年は数名程度の応募。
それにこだわらずに、気軽に参加してほしいと
事務局である「筑後川まるごと博物館」運営委員会の
鍋田事務局長からお聞きしました。
(写真:講座が開かれた久留米大学御井キャンパス)
久留米大学以外でも、筑後川防災施設である
「くるめウス」にて開催されることもあるそうです。
受講料は無料ですが、現地見学会の場合はバス代等の経費が必要。
今回は、「筑後川上流域の自然エネルギー」の講座でした。
(写真:講師の甲斐先生が、まず朝倉の三連水車について紹介)
甲斐先生は、日田市民環境会議エネルギー部会長として
様々な環境問題に取り組んでおられるそうです。
今回の講演内容は・・・
・日田、玖珠地域は自然エネルギー利用の先進地
・実用化されたほとんど全ての自然エネルギーを利用
・太陽光から水力、木材チップを使ったエネルギーまで様々
・九重町の八丁原地熱発電所は日本一
・大規模でなく、地元密着の小水力発電も多い
・生ゴミ等利用のメタンガス発電
・木質バイオマス発電も国内最大級 など
当企業団でも、旧川副浄水場跡地にメガソーラーの誘致計画
が進行していますが、先生言われるには・・・
大手資本ではなく、地元密着で地元に雇用、地元に利益
そのスタンスで取り組むことに意義があるのではと。
また、江戸時代から現在までおなじように水力を利用して
陶土を粉砕する唐臼の紹介もあり、興味を引かれました。
(写真:びっしり詰まった会場 前列は一般参加の方が多数)
今回の自然エネルギー以外にも、中流域の江戸時代からの堰や
下流では佐野常民の講座等もあり、筑後川について
幅広い知識を得るカリキュラムとなっています。
今後も機会があれば、他の講座にも参加したいと思っています。
2012年05月24日
岡山からのお客さん
先日は岡山県南部水道企業団の
構成団体の議員さん一行が視察にこられた。
目的は浄水場の効率化
「収入が減少し財政的に苦しい
その中で更新等課題が山積、東部水道企業団を参考にしたい」
旨を代表である倉敷市の原議長から伺った。
今回の視察は、他に佐賀県の西部広域水道企業団と
福岡地区水道企業団の三ヶ所
かなりハードな日程のようだった。
また、泊りが佐賀市の某ホテル
佐賀に泊まってくれるお客さんは大歓迎
しっかりお金を使って頂くことをお願いした。
私たちの東部水道企業団の「ウリ」は多い
「用水供給事業」と「水道事業」の二本立て併営は全国でも稀。
浄水場の集中管理は最新鋭の機器ではないが万全
施設のセキュリティも悪くはない。
汚泥は当然出るが臭気もなく、全量を園芸等に二次利用し
「産業廃棄物」として金をかけて捨ててはいない。

(写真:浄水処理時に発生する汚泥を乾燥させる「天日乾燥床」)
そんな説明を担当は手際よくしかも誇り高く説明
聞いていたわたしも納得。
ペットボトルのお茶だけのご接待だが
皆さん満足されてお帰りいただいたと思います。
構成団体の議員さん一行が視察にこられた。
目的は浄水場の効率化
「収入が減少し財政的に苦しい
その中で更新等課題が山積、東部水道企業団を参考にしたい」
旨を代表である倉敷市の原議長から伺った。
今回の視察は、他に佐賀県の西部広域水道企業団と
福岡地区水道企業団の三ヶ所
かなりハードな日程のようだった。
また、泊りが佐賀市の某ホテル
佐賀に泊まってくれるお客さんは大歓迎
しっかりお金を使って頂くことをお願いした。
私たちの東部水道企業団の「ウリ」は多い
「用水供給事業」と「水道事業」の二本立て併営は全国でも稀。
浄水場の集中管理は最新鋭の機器ではないが万全
施設のセキュリティも悪くはない。
汚泥は当然出るが臭気もなく、全量を園芸等に二次利用し
「産業廃棄物」として金をかけて捨ててはいない。
(写真:浄水処理時に発生する汚泥を乾燥させる「天日乾燥床」)
そんな説明を担当は手際よくしかも誇り高く説明
聞いていたわたしも納得。
ペットボトルのお茶だけのご接待だが
皆さん満足されてお帰りいただいたと思います。
2012年05月23日
軟式野球 県大会に出場 結果は惜敗
職場の軟式野球チームが
高松宮杯(二部)の佐賀市予選で優勝
そのことはお伝えしていました。
先日の土曜日は、その県大会でした。

(写真:塩田北部球場での試合の様子)
場所は塩田北部球場(嬉野市)
対戦相手は鹿島地区代表の東亜工機さん。
事前の野球部員の話では
「我々は佐賀市の代表 だから負ける訳がない」から
「試合はみずもの 負けるかも」になり
「相手の実績は うちより高い」と予防線。

(写真:小技も織り交ぜての攻撃)
無責任な応援団の噂では
「年齢が邪魔して 実力は口ほどでもない」
でも、6対3で快勝
日曜日の二回戦に駒を進めました。

(写真:一回戦を突破し、意気揚々で引き上げる部員)
二回戦は健闘しましたが3対5の逆転負け
残念でした。
実はこの日の試合は監督まで入って10人
ギリギリの人数でした。
欠席の部員は、地域やPTAに参加
私はそのことも大歓迎、地域等の行事も大事です。
二日間応援に行きました
業務中も彼らはスポーツマンらしくきびきびしていますが
ユニホーム姿はなおさらでした。
高松宮杯(二部)の佐賀市予選で優勝
そのことはお伝えしていました。
先日の土曜日は、その県大会でした。
(写真:塩田北部球場での試合の様子)
場所は塩田北部球場(嬉野市)
対戦相手は鹿島地区代表の東亜工機さん。
事前の野球部員の話では
「我々は佐賀市の代表 だから負ける訳がない」から
「試合はみずもの 負けるかも」になり
「相手の実績は うちより高い」と予防線。
(写真:小技も織り交ぜての攻撃)
無責任な応援団の噂では
「年齢が邪魔して 実力は口ほどでもない」
でも、6対3で快勝
日曜日の二回戦に駒を進めました。
(写真:一回戦を突破し、意気揚々で引き上げる部員)
二回戦は健闘しましたが3対5の逆転負け
残念でした。
実はこの日の試合は監督まで入って10人
ギリギリの人数でした。
欠席の部員は、地域やPTAに参加
私はそのことも大歓迎、地域等の行事も大事です。
二日間応援に行きました
業務中も彼らはスポーツマンらしくきびきびしていますが
ユニホーム姿はなおさらでした。
2012年05月22日
隣りの水路 コイ達は元気
企業団の敷地に隣接して水路がある。
この水路は冬の渇水期でも水が流れる水路
日常の水深は30cm程度で水路底が見える。

(写真:佐賀市上下水道局の水管橋が水路の上にある)
この時期はコイの姿を良く見る
群れの集団もいるし、一匹だけで悠々とも見かける。
冬の間は下流の佐賀江川の深みで体力を温存して
産卵のために上流域にやって来たのだろう。

(写真:50センチ程のコイ 意外と岸の近くにいる)
私は子供の頃から
魚獲り(魚つり)が大好き。
魚の姿をみれば
ズボンの裾をまくりたくなる。
しかし、そうも出来ずに
昼休みは魚の姿を見るのが日課になった。
注意深く見ると
コイ以外にも沢山の魚を目にすることが出来る。
「フナ」「ハヤ」「カメ(すっぽん)」「クーズ(泥ガメ)」
「アメリカザリガニ」「ライギョ」等々。

(写真:最近見かけるのは外来種のカメが多い)
町の中でも自然が豊かであることに「安心」する。
この水路に水位調節用の水門がある
この下流は水流で掘られ「深い」
この場所に「網」が常設されている。

(写真:昔の「四つ手網」の簡易型)
まだ魚がとれたのは「見ていない」
この水路は冬の渇水期でも水が流れる水路
日常の水深は30cm程度で水路底が見える。
(写真:佐賀市上下水道局の水管橋が水路の上にある)
この時期はコイの姿を良く見る
群れの集団もいるし、一匹だけで悠々とも見かける。
冬の間は下流の佐賀江川の深みで体力を温存して
産卵のために上流域にやって来たのだろう。
(写真:50センチ程のコイ 意外と岸の近くにいる)
私は子供の頃から
魚獲り(魚つり)が大好き。
魚の姿をみれば
ズボンの裾をまくりたくなる。
しかし、そうも出来ずに
昼休みは魚の姿を見るのが日課になった。
注意深く見ると
コイ以外にも沢山の魚を目にすることが出来る。
「フナ」「ハヤ」「カメ(すっぽん)」「クーズ(泥ガメ)」
「アメリカザリガニ」「ライギョ」等々。
(写真:最近見かけるのは外来種のカメが多い)
町の中でも自然が豊かであることに「安心」する。
この水路に水位調節用の水門がある
この下流は水流で掘られ「深い」
この場所に「網」が常設されている。
(写真:昔の「四つ手網」の簡易型)
まだ魚がとれたのは「見ていない」
2012年05月21日
水道週間の児童図画作品
毎年6月1日~6月7日の一週間は「水道週間」として
水道事業についての全国的な広報活動が実施されています。
当企業団でも、生活に欠かせない「水道」への理解を
深めてもらうことを目的に、管内の小学5年生を対象に
図画募集を行っています。
昨年も多数(603点)の応募をいただきました。

(写真:昨年の最優秀賞「中原小学校 板谷俊輔さん」の作品)
その他の作品についても、当企業団のホームページに
掲載していますので、ご覧ください。
「水を大切に」という気持ちが色々なタッチで表現され
どれも素晴らしい作品ばかりでした。

(写真:北茂安浄水場の2階ロビーに作品を掲示しています)
今年も募集を行いますので、たくさんの応募をお待ちしています。
水道事業についての全国的な広報活動が実施されています。
当企業団でも、生活に欠かせない「水道」への理解を
深めてもらうことを目的に、管内の小学5年生を対象に
図画募集を行っています。
昨年も多数(603点)の応募をいただきました。
(写真:昨年の最優秀賞「中原小学校 板谷俊輔さん」の作品)
その他の作品についても、当企業団のホームページに
掲載していますので、ご覧ください。
「水を大切に」という気持ちが色々なタッチで表現され
どれも素晴らしい作品ばかりでした。
(写真:北茂安浄水場の2階ロビーに作品を掲示しています)
今年も募集を行いますので、たくさんの応募をお待ちしています。
2012年05月18日
窓に遮熱フィルムを
今年も暑い夏が予想され
南側に窓が多い本庁舎の暑さ対策を検討しました。
今までは、ブラインドを使用していましたが
長年(18年間)の利用により傷みが目立ち始めていました。
昨年、取替を検討する中で
私の部屋で「遮熱フィルムを試行してみよう」ということになり
良い結果が確認されました。
それに基づき、ブラインドより費用が安く施工できる
遮熱フィルムを利用することとしました。

(写真:遮熱フィルムの貼付工事の様子)
先日、二日間の工事で南側と西側の窓に
遮熱フィルムの貼付が完了しました。
室内が若干暗くなりましたが
温度が下がったように感じます。
今年の夏を控え
どれくらいの効果があるか楽しみです。
南側に窓が多い本庁舎の暑さ対策を検討しました。
今までは、ブラインドを使用していましたが
長年(18年間)の利用により傷みが目立ち始めていました。
昨年、取替を検討する中で
私の部屋で「遮熱フィルムを試行してみよう」ということになり
良い結果が確認されました。
それに基づき、ブラインドより費用が安く施工できる
遮熱フィルムを利用することとしました。
(写真:遮熱フィルムの貼付工事の様子)
先日、二日間の工事で南側と西側の窓に
遮熱フィルムの貼付が完了しました。
室内が若干暗くなりましたが
温度が下がったように感じます。
今年の夏を控え
どれくらいの効果があるか楽しみです。
2012年05月17日
課題 ひとつは「危機管理」
今年の大きな課題がふたつある
と先月書きました。
その概要と今の時点の考え方を
お知らせします。
ひとつは「危機管理」です
これの課題は大きく三つ。
一点目は
「壊れない菅(耐震菅)」への布設替えです。

(写真:600mm耐震型鋳鉄管の布設状況)
現在の耐震化率(平成22年度実績)は
・用水供給事業 32.6%
・水道事業 1.0%
全域を替えるには相当の年月と費用が必要です。
その対応策として二点
一点はバイパス菅や他地域との相互給水。
二点目は有明粘土層の地耐力の評価
耐震に関する現在の国の指針は「軟弱地盤は一律に駄目」
はたしてそうなのか
「軟弱地盤と耐震の融合」を研究中。
二点目は「断水地域」対策
大規模な災害を予想すれば「応援体制」が必要。
そのための「仕組みづくり」と
即時の対応マニュアルの作成。
三点目は職員の素早い対応
「現場で即判断 責任は企業長」
「大ざっぱ」な説明ですが
こんなことを全企業団職員で模索中です。
と先月書きました。
その概要と今の時点の考え方を
お知らせします。
ひとつは「危機管理」です
これの課題は大きく三つ。
一点目は
「壊れない菅(耐震菅)」への布設替えです。
(写真:600mm耐震型鋳鉄管の布設状況)
現在の耐震化率(平成22年度実績)は
・用水供給事業 32.6%
・水道事業 1.0%
全域を替えるには相当の年月と費用が必要です。
その対応策として二点
一点はバイパス菅や他地域との相互給水。
二点目は有明粘土層の地耐力の評価
耐震に関する現在の国の指針は「軟弱地盤は一律に駄目」
はたしてそうなのか
「軟弱地盤と耐震の融合」を研究中。
二点目は「断水地域」対策
大規模な災害を予想すれば「応援体制」が必要。
そのための「仕組みづくり」と
即時の対応マニュアルの作成。
三点目は職員の素早い対応
「現場で即判断 責任は企業長」
「大ざっぱ」な説明ですが
こんなことを全企業団職員で模索中です。
2012年05月16日
朝のスピーチ(老舗百貨店)
職場では毎朝、朝礼があります。
その日の行事や会議等の報告
それにその日の担当によるスピーチです。
このスピーチ、それぞれ個性があって
面白く、楽しみにしています。
もちろん、私も「担当」の一人です。
私のデスクがある2階は、総務課総勢15名。

(写真:総務課の朝礼風景)
月に1回か2回まわってくる頻度です。
スピーチですので3分、長くて5分。
この3分間が曲者で
「要領よく相手に伝える話しをする」訓練になります。
時々はこのブログで紹介したいと思います。
今日は、ある係長のスピーチの概要です。
-------------------------------
かれこれ30年前のとある老舗百貨店で
お中元の販売アルバイトをした時の話。
百貨店であることから
十分な在庫管理が行なわれていたが
お客さんが求められた商品(数千円のあまり出ない品)が
たまたま品切れ・・(中元、歳暮時の在庫管理は難しかった)
その時に、百貨店がとった行動は
お詫びし、すぐに福岡市内にある他の店舗に連絡して
電車で受け取りに向かわせた。
(お客さんが他の買い物をされている間に)
数千円の品物で経費を考えれば儲けはなく、赤字。
しかしながら、老舗百貨店のお客さまを大事にする姿勢には
商売のプライドを感じた。
水道においてもそうありたい。
「在庫はこれだけです」という店もある中
(不用な在庫を抱えないのはやむを得ないが)
そのような気概ある百貨店が
閉鎖あるいは人員整理されていくのは寂しい。
-------------------------------
そんな話を先日聞きました。
その日の行事や会議等の報告
それにその日の担当によるスピーチです。
このスピーチ、それぞれ個性があって
面白く、楽しみにしています。
もちろん、私も「担当」の一人です。
私のデスクがある2階は、総務課総勢15名。
(写真:総務課の朝礼風景)
月に1回か2回まわってくる頻度です。
スピーチですので3分、長くて5分。
この3分間が曲者で
「要領よく相手に伝える話しをする」訓練になります。
時々はこのブログで紹介したいと思います。
今日は、ある係長のスピーチの概要です。
-------------------------------
かれこれ30年前のとある老舗百貨店で
お中元の販売アルバイトをした時の話。
百貨店であることから
十分な在庫管理が行なわれていたが
お客さんが求められた商品(数千円のあまり出ない品)が
たまたま品切れ・・(中元、歳暮時の在庫管理は難しかった)
その時に、百貨店がとった行動は
お詫びし、すぐに福岡市内にある他の店舗に連絡して
電車で受け取りに向かわせた。
(お客さんが他の買い物をされている間に)
数千円の品物で経費を考えれば儲けはなく、赤字。
しかしながら、老舗百貨店のお客さまを大事にする姿勢には
商売のプライドを感じた。
水道においてもそうありたい。
「在庫はこれだけです」という店もある中
(不用な在庫を抱えないのはやむを得ないが)
そのような気概ある百貨店が
閉鎖あるいは人員整理されていくのは寂しい。
-------------------------------
そんな話を先日聞きました。
2012年05月15日
「長期財政計画プロジェクト」の中間報告
企業長に就任して
「これは」と思ったことがいくらかある。
そのひとつが「計画論の議論」
当然 既存の計画は「ある」
誤解がないように
「計画書」も「計画論」も既存のものがあります。
しかし「これは」と思った訳は二点
一点は将来の「あるべき姿」を想像しての計画か?
具体的には20年後、30年後も
東部水道企業団の営業エリアは今のままか?
二点目は施設を作って25年が経過し
施設の耐用年数からすれば「折り返し点」を過ぎている。

(写真:昭和59年度稼働の北茂安浄水場「沈殿池と管理本館」)
この更新にかかる費用の算段は?
毎日、水道は利用する訳だから既存施設はそのままで
新しい施設が必要になる、その場所は?
等々の疑問が生じた。
ここの企業団を担う職員と
将来の姿を「共に考えてみたい」と思った次第。
そこで20年後も
職員であるはずの若手による
プロジェクトチームが発足した。
その中間報告を先日聞きました
まだまだ報告できる内容にはほど遠いものです。
しかし将来像を想像し「あるべき姿」を描き
系統的に議論する
このような体験を重ねることが
職員の資質が向上し
結果として利用者の皆様方への
サービスアップに繋がると確信します。
「これは」と思ったことがいくらかある。
そのひとつが「計画論の議論」
当然 既存の計画は「ある」
誤解がないように
「計画書」も「計画論」も既存のものがあります。
しかし「これは」と思った訳は二点
一点は将来の「あるべき姿」を想像しての計画か?
具体的には20年後、30年後も
東部水道企業団の営業エリアは今のままか?
二点目は施設を作って25年が経過し
施設の耐用年数からすれば「折り返し点」を過ぎている。
(写真:昭和59年度稼働の北茂安浄水場「沈殿池と管理本館」)
この更新にかかる費用の算段は?
毎日、水道は利用する訳だから既存施設はそのままで
新しい施設が必要になる、その場所は?
等々の疑問が生じた。
ここの企業団を担う職員と
将来の姿を「共に考えてみたい」と思った次第。
そこで20年後も
職員であるはずの若手による
プロジェクトチームが発足した。
その中間報告を先日聞きました
まだまだ報告できる内容にはほど遠いものです。
しかし将来像を想像し「あるべき姿」を描き
系統的に議論する
このような体験を重ねることが
職員の資質が向上し
結果として利用者の皆様方への
サービスアップに繋がると確信します。
2012年05月14日
「暴追協」の総会
先日、暴力追放公共企業体等佐賀地区連絡協議会の総会があり
私は所用で不参加でしたが、3人の職員が出席しました。
以下、出席した職員からの報告です。
---------------------------------
先日、「暴力追放公共企業体等佐賀地区連絡協議会」略して「暴追協」
の総会が佐賀市のiスクエアビルにて開催されました。
この暴追協とは、佐賀・神埼・小城・多久地区の
各水道事業体、NHK、九州電力、NTT、ガス、通信事業者等の
公共企業体等と佐賀県警本部及び各警察署で組織され
平穏で安全な生活を目指して、いろいろな情報を共有し
協議して社会全体で暴力行為等の組織犯罪を失くして
いくことを目的として、設立運営されています。

(チラシ:全国暴力追放運動推進センター/警察庁)
総会では、佐賀県警察本部からの報告の中で
ここ最近頻発している九州北部での暴力団抗争の情勢報告があり
人数は減少しているものの過激な行動へと転換しており、地域住民
が巻き込まれる危険が増大し、対岸の火事ではないと感じました。
暴力追放運動推進センターの池田専務理事の講演があり
県民大会開催の活動や相談状況について報告がありました。
また、暴力団排除条例の
概要説明があり、県内全市町において制定され
平成24年4月1日から施行されたとのことでした。

(チラシ:佐賀県の暴力団排除条例は平成24年1月1日より施行)
住民の皆さまの身近なライフラインである「水道」を営む
佐賀東部水道企業団もこのような活動への取り組みを通じて
地域の皆さまの安全で平穏な生活に少しでも役立つ水道事業体
でありたいと考えています。
私は所用で不参加でしたが、3人の職員が出席しました。
以下、出席した職員からの報告です。
---------------------------------
先日、「暴力追放公共企業体等佐賀地区連絡協議会」略して「暴追協」
の総会が佐賀市のiスクエアビルにて開催されました。
この暴追協とは、佐賀・神埼・小城・多久地区の
各水道事業体、NHK、九州電力、NTT、ガス、通信事業者等の
公共企業体等と佐賀県警本部及び各警察署で組織され
平穏で安全な生活を目指して、いろいろな情報を共有し
協議して社会全体で暴力行為等の組織犯罪を失くして
いくことを目的として、設立運営されています。

(チラシ:全国暴力追放運動推進センター/警察庁)
総会では、佐賀県警察本部からの報告の中で
ここ最近頻発している九州北部での暴力団抗争の情勢報告があり
人数は減少しているものの過激な行動へと転換しており、地域住民
が巻き込まれる危険が増大し、対岸の火事ではないと感じました。
暴力追放運動推進センターの池田専務理事の講演があり
県民大会開催の活動や相談状況について報告がありました。
また、暴力団排除条例の
概要説明があり、県内全市町において制定され
平成24年4月1日から施行されたとのことでした。

(チラシ:佐賀県の暴力団排除条例は平成24年1月1日より施行)
住民の皆さまの身近なライフラインである「水道」を営む
佐賀東部水道企業団もこのような活動への取り組みを通じて
地域の皆さまの安全で平穏な生活に少しでも役立つ水道事業体
でありたいと考えています。
2012年05月11日
昨年は水不足
昨年の上半期は
筑後川流域の水不足が深刻な状況でした。
皆様もご心配されたことと思います。
平成22年の8月以降の少雨傾向により
水源である筑後川の流況が悪化しました。
平成22年12月に「渇水対策準備室」を
昨年の5月2日には「渇水対策本部」を立ち上げ
皆様に節水の呼びかけをしました。
6年ぶりのことでした。(前回は、平成17年6月に設置)
通常、水源である筑後川の流況が悪化した際には
江川・寺内両ダムに貯留している水を流況に応じて
補給しています。
昨年は少雨傾向だったため、流況がなかなか回復せず
補給が続き、貯水量が非常に厳しい状況となりました。
ダム貯水量を温存するために
4月21日から、日量5%の取水制限を実施しました。
この制限は、佐賀市のご協力を得て調整を行い
お客様への直接的な影響を出さないようにしました。
その後、5月11日より「恵みの雨」が降り
筑後川の流況が改善し、水不足は解消しました。
梅雨時期に入り、まとまった降雨があり
ダムの貯水量も順調に増えていったことから
6月16日に「渇水対策本部」を解散しました。
さて今年は、気象台の長期予報でも平年並みの降水が
見込まれていることより、心配は少ないと思われます。
今日現在まで平年並みの降雨があり、流況も安定しています。

(写真:久留米市にある水天宮 「全国にある水天宮の総本社」)
しかしながら、降雨に頼る状況が大きいので
久留米の水天宮に行って「適度な雨」をお願いしてきました。
筑後川流域の水不足が深刻な状況でした。
皆様もご心配されたことと思います。
平成22年の8月以降の少雨傾向により
水源である筑後川の流況が悪化しました。
平成22年12月に「渇水対策準備室」を
昨年の5月2日には「渇水対策本部」を立ち上げ
皆様に節水の呼びかけをしました。
6年ぶりのことでした。(前回は、平成17年6月に設置)
通常、水源である筑後川の流況が悪化した際には
江川・寺内両ダムに貯留している水を流況に応じて
補給しています。
昨年は少雨傾向だったため、流況がなかなか回復せず
補給が続き、貯水量が非常に厳しい状況となりました。
ダム貯水量を温存するために
4月21日から、日量5%の取水制限を実施しました。
この制限は、佐賀市のご協力を得て調整を行い
お客様への直接的な影響を出さないようにしました。
その後、5月11日より「恵みの雨」が降り
筑後川の流況が改善し、水不足は解消しました。
梅雨時期に入り、まとまった降雨があり
ダムの貯水量も順調に増えていったことから
6月16日に「渇水対策本部」を解散しました。
さて今年は、気象台の長期予報でも平年並みの降水が
見込まれていることより、心配は少ないと思われます。
今日現在まで平年並みの降雨があり、流況も安定しています。
(写真:久留米市にある水天宮 「全国にある水天宮の総本社」)
しかしながら、降雨に頼る状況が大きいので
久留米の水天宮に行って「適度な雨」をお願いしてきました。
2012年05月10日
5月定例課長会の報告
会議に先立ち、新しい年度になり一ヶ月が過ぎ
人事異動によってお客様に迷惑がないようにお願いしました。
また、次の3点について指示をしました。
一点は今年の課題の「長期財政計画」
全体シナリオの確認会議の段取りを
二点目は「危機管理対策」の
具体策の検討スケジュールを
三点目は新規の案件
例えば権限委譲・財産管理等の取り組みに対する議論と準備
以上を
連休明けには、それぞれの課題に対して本格始動をお願いしました。
さて、今月の議題は
給水量の認定方法の変更について議論を始めることを確認しました。
簡単にいえば統計上のことですが、給水量は旧市町村毎で算出して
いますが、「一本化できないか」との提案です。
問題もあり
その解決を図りながら提案の方向で作業を行うことにしました。
他にはメガソーラーの現状、国庫補助の申請
時間外のお客様サービス等の報告でした。
この中で、時間外のお客様サービスについて
特に深夜の対応についても今まで通り、的確に対応し処理する。
そのための職員や施工業者の方々との連絡、連携のやり方等
を再度確認することにしました。
人事異動によってお客様に迷惑がないようにお願いしました。
また、次の3点について指示をしました。
一点は今年の課題の「長期財政計画」
全体シナリオの確認会議の段取りを
二点目は「危機管理対策」の
具体策の検討スケジュールを
三点目は新規の案件
例えば権限委譲・財産管理等の取り組みに対する議論と準備
以上を
連休明けには、それぞれの課題に対して本格始動をお願いしました。
さて、今月の議題は
給水量の認定方法の変更について議論を始めることを確認しました。
簡単にいえば統計上のことですが、給水量は旧市町村毎で算出して
いますが、「一本化できないか」との提案です。
問題もあり
その解決を図りながら提案の方向で作業を行うことにしました。
他にはメガソーラーの現状、国庫補助の申請
時間外のお客様サービス等の報告でした。
この中で、時間外のお客様サービスについて
特に深夜の対応についても今まで通り、的確に対応し処理する。
そのための職員や施工業者の方々との連絡、連携のやり方等
を再度確認することにしました。
2012年05月09日
クールビズ開始
「夏の常識」として定着したクールビズ
例年は6月から9月末までの実施でした。
しかし、昨年は東日本大震災での
電力不足も考慮され5月から実施しました。
今年も同じような電力不足が予想されますので
昨年同様に5月からの実施としました。
「ノーネクタイ」がその代表ですが
ネクタイを外すことで快適な気分になります。

(写真:ネクタイを外し業務に従事する職員)
しかし、本来は冷房使用を控えて
二酸化炭素の増加を防ぐことが目的です。
二酸化炭素は地球温暖化の原因のひとつで
28度Cまでは冷房使用を控えることになります。
クールビズとは
暑さに耐えられる服装で仕事をするということでもあります。
ちなみに冷房を使用するのは早くて6月初旬
主に都市ガス利用の冷房装置を利用しています。
今年も「スーパークールビズを」といって
Tシャツ・半ズボン・ジーンズまでOKとの話がありますが
それは「どうかな」と思っています。
例年は6月から9月末までの実施でした。
しかし、昨年は東日本大震災での
電力不足も考慮され5月から実施しました。
今年も同じような電力不足が予想されますので
昨年同様に5月からの実施としました。
「ノーネクタイ」がその代表ですが
ネクタイを外すことで快適な気分になります。
(写真:ネクタイを外し業務に従事する職員)
しかし、本来は冷房使用を控えて
二酸化炭素の増加を防ぐことが目的です。
二酸化炭素は地球温暖化の原因のひとつで
28度Cまでは冷房使用を控えることになります。
クールビズとは
暑さに耐えられる服装で仕事をするということでもあります。
ちなみに冷房を使用するのは早くて6月初旬
主に都市ガス利用の冷房装置を利用しています。
今年も「スーパークールビズを」といって
Tシャツ・半ズボン・ジーンズまでOKとの話がありますが
それは「どうかな」と思っています。
2012年05月08日
大興善寺のツツジ(基山町)
各地から「花だより」が聞こえてきます。
大型連休いかがだったでしょうか?
今年は天気に恵まれたので
外出された方も多かったのではないでしょうか?
私は、基山にある大興善寺の状況を見に行ってきました。
随分と久し振りの訪問でした。

(写真:ツツジ寺として全国的に有名な「大興善寺」)
奈良時代の創建、行基によって開かれ
1300年の歴史をもつ古刹。
5万本のツツジと500本のモミジ
しかし「大興善寺 = ツツジ」が定着。
さて、駐車場からお寺さんまでの
道中の花が素敵で気分良く散歩。
階段を登り、門をくぐれば緑がまぶしい
モミジの新緑がお出迎え。

(写真:新緑と花に包まれた境内)
閉門直前になったために
園内に入るのは断念。
本堂に参拝して周辺を見学しているとご住職とバッタリ
今週が見頃とのことでした。
皆さんも機会があったら
散歩がてらの「ツツジ見学」いかがですか?
大型連休いかがだったでしょうか?
今年は天気に恵まれたので
外出された方も多かったのではないでしょうか?
私は、基山にある大興善寺の状況を見に行ってきました。
随分と久し振りの訪問でした。
(写真:ツツジ寺として全国的に有名な「大興善寺」)
奈良時代の創建、行基によって開かれ
1300年の歴史をもつ古刹。
5万本のツツジと500本のモミジ
しかし「大興善寺 = ツツジ」が定着。
さて、駐車場からお寺さんまでの
道中の花が素敵で気分良く散歩。
階段を登り、門をくぐれば緑がまぶしい
モミジの新緑がお出迎え。
(写真:新緑と花に包まれた境内)
閉門直前になったために
園内に入るのは断念。
本堂に参拝して周辺を見学しているとご住職とバッタリ
今週が見頃とのことでした。
皆さんも機会があったら
散歩がてらの「ツツジ見学」いかがですか?
2012年05月07日
佐賀市と芝浦HDが進出協定締結(メガソーラー)
4月13日、佐賀市川副町に
メガソーラー(大規模太陽光発電施設)を
建設することが決定しました。
残念ながら、私は、出張中で協定式に
参加できませんでしたが、当企業団も関係団体として
職員が協定式に参加しました。
正式名称は「川副発電所」
佐賀東部水道企業団所有の川副浄水場跡に
4,000枚の太陽光パネルが設置されます。
発電容量は1.2メガワットで
一般家庭約400戸相当分の電力を賄うことができます。
再生可能エネルギーとして
大いに期待される太陽光発電所。
発電開始が一日でも早く実現できるように
関係職員が頑張っています。
4月22日、川副町米納津地区で
メガソーラー事業の説明会が行われました。
メガソーラー建設については賛成いただきました。
今後は、旧施設の解体等の事務処理を進めていきます。
メガソーラー(大規模太陽光発電施設)を
建設することが決定しました。
残念ながら、私は、出張中で協定式に
参加できませんでしたが、当企業団も関係団体として
職員が協定式に参加しました。
正式名称は「川副発電所」
佐賀東部水道企業団所有の川副浄水場跡に
4,000枚の太陽光パネルが設置されます。
発電容量は1.2メガワットで
一般家庭約400戸相当分の電力を賄うことができます。
再生可能エネルギーとして
大いに期待される太陽光発電所。
発電開始が一日でも早く実現できるように
関係職員が頑張っています。
4月22日、川副町米納津地区で
メガソーラー事業の説明会が行われました。
メガソーラー建設については賛成いただきました。
今後は、旧施設の解体等の事務処理を進めていきます。
2012年05月02日
「アンネのバラ」(上峰町親水広場)の紹介
上峰町役場敷地にある
「アンネのバラ」を見てきました。
咲いていました。今五分咲き程です。

(写真:咲き誇るアンネのバラ)
事前に役場の方にお尋ねしたら
この町にお住まいの方が自宅で増やされ
それを寄付されたとのこと。
小川沿いに創られた親水広場に沿って
約40本のバラがあります。
連休後1週間程度が見頃と思います。
やはり「神聖な感じ」のバラでした。

(写真:アンネのバラの由来紹介板)
私も少し園芸をしますので
「アンネのバラ」のことは聞いて知っていた。
「アンネのバラ」について説明します。
「アンネの日記」のアンネです。
第二次大戦時ユダヤ人ということだけで
ナチスドイツは殺害した。
アンネは両親と姉の4人家族で
屋根裏部屋に隠れ住んでいた。
ここまでが「アンネの日記」のポピュラー編
その日記の5月17日に
「今日は父の誕生日」私はお祝いにバラの花を贈った。
「父はとっても喜んだ」と書いてあるそうです。
その後ベルギーの園芸家がそのバラの種子を持ち帰り
交配に交配を重ねてつくったバラが「アンネのバラ」です。
それをただ一人生き残った父親に贈った。
20年後、国語の教科書に一部が紹介され
東京の高井戸中学生が感想文を書き、父親に贈った。
感激した父親は
その礼として「アンネのバラ」の苗木を贈ってくれた。
苗は生徒たちの手で植えられ
今でもたくさんの花を咲かせていると言う。
このバラは流通ルートにはなく
値段もつけようがない。
と以前 佐賀バラ会の中野氏から
話しを伺ったことがありました。
「アンネのバラ」を見てきました。
咲いていました。今五分咲き程です。
(写真:咲き誇るアンネのバラ)
事前に役場の方にお尋ねしたら
この町にお住まいの方が自宅で増やされ
それを寄付されたとのこと。
小川沿いに創られた親水広場に沿って
約40本のバラがあります。
連休後1週間程度が見頃と思います。
やはり「神聖な感じ」のバラでした。
(写真:アンネのバラの由来紹介板)
私も少し園芸をしますので
「アンネのバラ」のことは聞いて知っていた。
「アンネのバラ」について説明します。
「アンネの日記」のアンネです。
第二次大戦時ユダヤ人ということだけで
ナチスドイツは殺害した。
アンネは両親と姉の4人家族で
屋根裏部屋に隠れ住んでいた。
ここまでが「アンネの日記」のポピュラー編
その日記の5月17日に
「今日は父の誕生日」私はお祝いにバラの花を贈った。
「父はとっても喜んだ」と書いてあるそうです。
その後ベルギーの園芸家がそのバラの種子を持ち帰り
交配に交配を重ねてつくったバラが「アンネのバラ」です。
それをただ一人生き残った父親に贈った。
20年後、国語の教科書に一部が紹介され
東京の高井戸中学生が感想文を書き、父親に贈った。
感激した父親は
その礼として「アンネのバラ」の苗木を贈ってくれた。
苗は生徒たちの手で植えられ
今でもたくさんの花を咲かせていると言う。
このバラは流通ルートにはなく
値段もつけようがない。
と以前 佐賀バラ会の中野氏から
話しを伺ったことがありました。