2013年09月30日
長野県の中央タクシーの話
職員の朝のスピーチの紹介
今回は、長野県の中央タクシーの話です。

(イラスト:タクシーを利用する)
9月頭にテレビで紹介された
全国から予約が入って忙しいタクシー会社の話でした。
-------------------------------
会社はプレハブの2階建てで大きな会社ではないが
オペレーターが数名おられて電話予約対応風景があっていた。
ではなぜそんなに人気なのか?
その理由の紹介で、事例を3つほど放映された。
その中の一つの事例を紹介すると、
東京の親子(母親と男の幼稚園児)が友人の結婚式で長野へ来た。
駅から式場まではタクシーで約40分位のところ
その日の長野はかなり寒く
その親子は薄着だったので寒そうであった。
(東京はポカポカ天気だったので薄着で来られたようである)
途中お母さんが幼稚園児の子供用に厚手の長い靴下を買いたいと
運転手に告げられたが、時間が朝8時前であり
途中に店が開いておらず、そうこうしているうちに式場へ着いた。
親子をおろしたタクシーは、帰社途中約30分くらい走ったところで
衣料品店がシャッターを開けていたのを見て
運転手は、衣料品店に寄り子供用靴下を購入して式場に戻られ
式場の受付係に、親子に靴下を渡してもらうよう
お願いし帰られたとのこと。
受付の人から靴下を渡されたお母さんは話を聞いて感激され
当然お礼の手紙をタクシー会社に送付。
この会社の社長のインタビューでの話
自分も商売だから損をして
会社が成り立たないならどうしようもないが
将来の集客につながる親切な対応は
1時間2時間かかっても損と思わない。
その心づかいで利用者が喜び、口コミで会社のPRをしてくれて
それが将来の集客につながれば会社にとっていいことだと思って
社員の自己判断での行動にまかせているとのことであった。
「損して得取れ」の精神ですとも言われたが
なかなかできないことだと思ったところである。
企業団もここまでのサービスはできないだろうが
せめてお客様対応については、言葉使いや電話対応には
充分注意していくのが大事であると感じたところです。
みなさんも長野でタクシー利用の際は
一度中央タクシーに乗ってみて
体験をしてみたらどうでしょうかのご紹介でした。
今回は、長野県の中央タクシーの話です。

(イラスト:タクシーを利用する)
9月頭にテレビで紹介された
全国から予約が入って忙しいタクシー会社の話でした。
-------------------------------
会社はプレハブの2階建てで大きな会社ではないが
オペレーターが数名おられて電話予約対応風景があっていた。
ではなぜそんなに人気なのか?
その理由の紹介で、事例を3つほど放映された。
その中の一つの事例を紹介すると、
東京の親子(母親と男の幼稚園児)が友人の結婚式で長野へ来た。
駅から式場まではタクシーで約40分位のところ
その日の長野はかなり寒く
その親子は薄着だったので寒そうであった。
(東京はポカポカ天気だったので薄着で来られたようである)
途中お母さんが幼稚園児の子供用に厚手の長い靴下を買いたいと
運転手に告げられたが、時間が朝8時前であり
途中に店が開いておらず、そうこうしているうちに式場へ着いた。
親子をおろしたタクシーは、帰社途中約30分くらい走ったところで
衣料品店がシャッターを開けていたのを見て
運転手は、衣料品店に寄り子供用靴下を購入して式場に戻られ
式場の受付係に、親子に靴下を渡してもらうよう
お願いし帰られたとのこと。
受付の人から靴下を渡されたお母さんは話を聞いて感激され
当然お礼の手紙をタクシー会社に送付。
この会社の社長のインタビューでの話
自分も商売だから損をして
会社が成り立たないならどうしようもないが
将来の集客につながる親切な対応は
1時間2時間かかっても損と思わない。
その心づかいで利用者が喜び、口コミで会社のPRをしてくれて
それが将来の集客につながれば会社にとっていいことだと思って
社員の自己判断での行動にまかせているとのことであった。
「損して得取れ」の精神ですとも言われたが
なかなかできないことだと思ったところである。
企業団もここまでのサービスはできないだろうが
せめてお客様対応については、言葉使いや電話対応には
充分注意していくのが大事であると感じたところです。
みなさんも長野でタクシー利用の際は
一度中央タクシーに乗ってみて
体験をしてみたらどうでしょうかのご紹介でした。
2013年09月27日
お二人の訪問
毎日、いくらかの方の訪問がある
先日は、国土交通省の河川部の方と水機構の方両名が
おそろいでお見えになった。
「ついでに寄った」
「久し振りにコーヒーを飲みたくなった」
とのことだった。
いつも気にかけて頂き「有り難い」
本来は、私が訪問してご挨拶や情報の交換をするのが筋
それなのに、気軽に寄って頂いている。
お忙しいご両名だが、ゆっくりとくつろいで貰いたい。
そこで、安物の豆で挽いたコーヒーを
陶磁器の本場、有田に近いにも関わらずに
安物のコーヒーカップで出す
しかも、豆の特性を理解しない私の「適当な濃いさ」のコーヒーを。
そんな雰囲気のなかで、ご両名からは
私にとっては、参考になる話のオンパレード。

(写真:九州一の大河「筑後川」筑後大堰付近)
例えば、つい先ほどまで筑後川流域は雨が少なく
大変な状況がありました
農業には、まだまだ多くの水が必要な時期の渇水状況
川の水の配分ルールは、もちろん決まっている。
おかげさまで「水道の水を制限する」までは至っていない状況
田んぼの水が不足して困っている地域がある
その時に、大都市福岡市は「困ったときはお互い様」と
ルールを自ら破って「困った地域に水を回して頂いた」
ルール上は、やる必要はない
しかし「お互いさま」との気持ちと
川の水は、全ての利用者にとって「自然からの贈りもの」
このことがベースにある、この北部九州は素晴らしい。
そんな内容の話を聞きました
ずーっと昔は、川の水は農業用の水と有明海の栄養源
私たち水道事業者は、その水を後から来て、分けて頂いている。
その気持ちを「忘れてはいけない」
もしも、水道水が不足した時には逆の話になることだから。
わたし一人が聞くには「もったいない」お話でした。
先日は、国土交通省の河川部の方と水機構の方両名が
おそろいでお見えになった。
「ついでに寄った」
「久し振りにコーヒーを飲みたくなった」
とのことだった。
いつも気にかけて頂き「有り難い」
本来は、私が訪問してご挨拶や情報の交換をするのが筋
それなのに、気軽に寄って頂いている。
お忙しいご両名だが、ゆっくりとくつろいで貰いたい。
そこで、安物の豆で挽いたコーヒーを
陶磁器の本場、有田に近いにも関わらずに
安物のコーヒーカップで出す
しかも、豆の特性を理解しない私の「適当な濃いさ」のコーヒーを。
そんな雰囲気のなかで、ご両名からは
私にとっては、参考になる話のオンパレード。

(写真:九州一の大河「筑後川」筑後大堰付近)
例えば、つい先ほどまで筑後川流域は雨が少なく
大変な状況がありました
農業には、まだまだ多くの水が必要な時期の渇水状況
川の水の配分ルールは、もちろん決まっている。
おかげさまで「水道の水を制限する」までは至っていない状況
田んぼの水が不足して困っている地域がある
その時に、大都市福岡市は「困ったときはお互い様」と
ルールを自ら破って「困った地域に水を回して頂いた」
ルール上は、やる必要はない
しかし「お互いさま」との気持ちと
川の水は、全ての利用者にとって「自然からの贈りもの」
このことがベースにある、この北部九州は素晴らしい。
そんな内容の話を聞きました
ずーっと昔は、川の水は農業用の水と有明海の栄養源
私たち水道事業者は、その水を後から来て、分けて頂いている。
その気持ちを「忘れてはいけない」
もしも、水道水が不足した時には逆の話になることだから。
わたし一人が聞くには「もったいない」お話でした。
2013年09月26日
「技術継承委員会」の議論
企業団内部の大きな課題のひとつが
熟練した技術者の定年退職に伴う「技術の継承」です。
内部で議論をお願いしています
今回は、それの中間報告です。
委員会は、各部署からの代表によって構成されています
その代表は、部署からの推薦です
だから、多士済々のメンバーです。
4回の委員会がすでに開かれていると聞いています
現在の状況は
すでに研修の方法論等、具体的な議論がされているようです。

(写真:平成5年11月に移転新築した「企業団本庁舎」
東部水道企業団は、昭和50年4月に設立されました)
「勉強!勉強!では駄目」
「企業団を担うとの意識が重要」
「各人のモチベーションを高める」
「この継承の議論は、とりかかり」
「若い職員が困らないように」
等々、中身の濃い議論がされているようです。
報告が委員会ごとに届きます
職員の意識の高さや積極的な姿勢に、未来を感じます。
熟練した技術者の定年退職に伴う「技術の継承」です。
内部で議論をお願いしています
今回は、それの中間報告です。
委員会は、各部署からの代表によって構成されています
その代表は、部署からの推薦です
だから、多士済々のメンバーです。
4回の委員会がすでに開かれていると聞いています
現在の状況は
すでに研修の方法論等、具体的な議論がされているようです。
(写真:平成5年11月に移転新築した「企業団本庁舎」
東部水道企業団は、昭和50年4月に設立されました)
「勉強!勉強!では駄目」
「企業団を担うとの意識が重要」
「各人のモチベーションを高める」
「この継承の議論は、とりかかり」
「若い職員が困らないように」
等々、中身の濃い議論がされているようです。
報告が委員会ごとに届きます
職員の意識の高さや積極的な姿勢に、未来を感じます。
2013年09月25日
私事です「瞬間だけ主夫」
このブログは「水道」の東部水道企業団が発信
だから、水道情報を皆様にお知らせすることが使命。
分かってはいますが
読むほうも、そればかりでは「つまらない」だろう
書いている私も「固い話題ばかり」はつらい。
かと言って、水道の話題がない訳ではありません
日々、企業団は動いていますので「あります」
それでも、時々は脱線をお許しください。
で、今日の話題は「わたくし事」です
ここ最近、夕飯に限って主婦(夫)をしています。

(イラスト:台所で食事の支度)
つれあいが、いなくなった訳ではありません
その直接的な理由は明かせませんが
「自立する」との決意も理由のひとつです。
まだ始めて3週間程度、大口は叩けません
いつかは料理を「チョイ チョイ」とできる男になりたい。
そんな気持ちを、以前から心の中に抱えていました
そのチャンスが来た
そう前向きに捉えて昨晩も台所に立ちました。
昨晩は、豚肉のしょうが焼きと冬瓜の煮物と味噌汁
「まあ まあ」の評判でした。
だから、水道情報を皆様にお知らせすることが使命。
分かってはいますが
読むほうも、そればかりでは「つまらない」だろう
書いている私も「固い話題ばかり」はつらい。
かと言って、水道の話題がない訳ではありません
日々、企業団は動いていますので「あります」
それでも、時々は脱線をお許しください。
で、今日の話題は「わたくし事」です
ここ最近、夕飯に限って主婦(夫)をしています。

(イラスト:台所で食事の支度)
つれあいが、いなくなった訳ではありません
その直接的な理由は明かせませんが
「自立する」との決意も理由のひとつです。
まだ始めて3週間程度、大口は叩けません
いつかは料理を「チョイ チョイ」とできる男になりたい。
そんな気持ちを、以前から心の中に抱えていました
そのチャンスが来た
そう前向きに捉えて昨晩も台所に立ちました。
昨晩は、豚肉のしょうが焼きと冬瓜の煮物と味噌汁
「まあ まあ」の評判でした。
2013年09月24日
苦情処理の報告
先日の早朝
「水道の水が赤く濁っている」との電話がありましたので
職員が現地調査確認のため、そのお宅に訪問し
台所・洗面台で濁っているのを確認しました。
宅地の前の道路に埋設されている配水管をまずチェック
管末のドレン(水抜き)での濁りが無い事を確認
次にメーターを取り外し
給水管の道路側を確認したが異常はない
最後に、台所の蛇口を全開にして出したところ
赤水に混じって、多数の鉄サビが確認されました。
ここまでの状況は、ご本人にも確認いただき
宅地側の水道管の腐食によるサビが原因であることが判明
説明を行ないました。
この時点で、ご本人は宅地内の水道管も
企業団で修理をするものと勘違いされていたが
「個人負担による工事」であるとの説明で納得されました。
以上が事の顛末であります。

(イラスト:給水装置の管理区分図)
一時的な対応策としては
朝一番の水をしばらく放水すれば濁りはなくなりますが
根本的には、宅地内の布設替えが必要
さらには
将来的に管の腐食が進み、漏水の可能性があることから
工事店へ配管替えを依頼されたほうがよい
との説明を行い納得・了解された。
このような事例があります
お宅の水道水には、異常はないでしょうか?
「水道の水が赤く濁っている」との電話がありましたので
職員が現地調査確認のため、そのお宅に訪問し
台所・洗面台で濁っているのを確認しました。
宅地の前の道路に埋設されている配水管をまずチェック
管末のドレン(水抜き)での濁りが無い事を確認
次にメーターを取り外し
給水管の道路側を確認したが異常はない
最後に、台所の蛇口を全開にして出したところ
赤水に混じって、多数の鉄サビが確認されました。
ここまでの状況は、ご本人にも確認いただき
宅地側の水道管の腐食によるサビが原因であることが判明
説明を行ないました。
この時点で、ご本人は宅地内の水道管も
企業団で修理をするものと勘違いされていたが
「個人負担による工事」であるとの説明で納得されました。
以上が事の顛末であります。

(イラスト:給水装置の管理区分図)
一時的な対応策としては
朝一番の水をしばらく放水すれば濁りはなくなりますが
根本的には、宅地内の布設替えが必要
さらには
将来的に管の腐食が進み、漏水の可能性があることから
工事店へ配管替えを依頼されたほうがよい
との説明を行い納得・了解された。
このような事例があります
お宅の水道水には、異常はないでしょうか?
2013年09月20日
長期計画ヒア「再度協議分」
各部署のヒアリングで
「再度の協議を」としていた案件が二つありました
1週間後に 「そのストーリーと資料を」と求めていました
まずひとつが老朽管更新と耐震管への変更
両方を連動させ しかも優先度合いを加味して
予算や人員のことを想定し
効率的しかも利用者の方が納得できるシナリオの作成でした
ここでは具体的なことは省きますが
災害時で危機状態になった時
最優先の水道供給先は避難場所や公共の病院です
また多くの地域に水道水を供給する幹線は当然のことです
このことのベースには 1年でも「長持ちさせる」
更新時に入れ替える管は 「長持ちする」が基本です
良く考え 納得いくシナリオでした
今後は 具体的な施設更新計画をたて
いずれかの時期には公表します
ふたつめは 「圧送所の更新計画の考え方」でした
たまたま 圧送所が話題になりましたが
施設管理の「基本的な課題を含んでいる」との思いから
関係部署で再度の協議をお願いしていました

(写真:S60年築造のみやき町山田圧送所)
造りはコンクリートだから60年の耐用年数があります
しかし 中の電気や機械設備は15年程度
だから何回かの更新があります これが基本です
これを踏まえて 各々の施設には周辺環境等それぞれの事情を含んでいます
そこで 基本的な更新のシナリオと
60年の耐用年数前での更新の費用比較の資料が提出されました
それでは 「途中更新の費用が安い」結果でした
維持管理のための人件費が主な理由です
「漫然とシナリオどおりに更新」が常識ではない
という結果です
もちろん費用比較だけでで決定する訳ではありません
「常に疑問を」が私の伝えたいことでした

(写真:H22年築造の吉野ケ里町松隈圧送所)
以上でヒアリングは終わりました
今後は 企業団経営を見ながらの財政的な検証が始まります
「再度の協議を」としていた案件が二つありました
1週間後に 「そのストーリーと資料を」と求めていました
まずひとつが老朽管更新と耐震管への変更
両方を連動させ しかも優先度合いを加味して
予算や人員のことを想定し
効率的しかも利用者の方が納得できるシナリオの作成でした
ここでは具体的なことは省きますが
災害時で危機状態になった時
最優先の水道供給先は避難場所や公共の病院です
また多くの地域に水道水を供給する幹線は当然のことです
このことのベースには 1年でも「長持ちさせる」
更新時に入れ替える管は 「長持ちする」が基本です
良く考え 納得いくシナリオでした
今後は 具体的な施設更新計画をたて
いずれかの時期には公表します
ふたつめは 「圧送所の更新計画の考え方」でした
たまたま 圧送所が話題になりましたが
施設管理の「基本的な課題を含んでいる」との思いから
関係部署で再度の協議をお願いしていました

(写真:S60年築造のみやき町山田圧送所)
造りはコンクリートだから60年の耐用年数があります
しかし 中の電気や機械設備は15年程度
だから何回かの更新があります これが基本です
これを踏まえて 各々の施設には周辺環境等それぞれの事情を含んでいます
そこで 基本的な更新のシナリオと
60年の耐用年数前での更新の費用比較の資料が提出されました
それでは 「途中更新の費用が安い」結果でした
維持管理のための人件費が主な理由です
「漫然とシナリオどおりに更新」が常識ではない
という結果です
もちろん費用比較だけでで決定する訳ではありません
「常に疑問を」が私の伝えたいことでした

(写真:H22年築造の吉野ケ里町松隈圧送所)
以上でヒアリングは終わりました
今後は 企業団経営を見ながらの財政的な検証が始まります
2013年09月19日
耳寄り情報
水道関係のいろいろな情報が日夜届きます
その中からの情報の提供です
「水道かわら版」もそのひとつです
そこに「ペットボトル症候群」という記載が目にとまりました
紹介します
9月になったものの 相変わらず暑さが続いています
暑さに負けないためには
水分補給と熱中症対策が欠かせませんが
「ペットボトル症候群」という大きな落とし穴があります
一般的に 熱中症はこまめな水分補給が
一番効果的とされています
だから 外出時にはペットボトルを持ち
水分の補給をするのが常識です
しかし ここに大きな落とし穴があります
コーラやスポーツドリンク 清涼飲料水などの糖質の多い飲料を
飲み続けていると「ペットボトル症候群」になってしまいます
血糖値が上がり急性の糖尿病の危険性があります
発症者の多くが 大量に飲んでいたところからこの名が付けられました
軽度の症状で 「ボーッとする」「落ち着きがなくなる」
最悪は意識障害を起こして倒れることも
甘いペットボトルにはご用心
お茶・ミネラルウォーターがよさそうです

(写真:水飲もうポスター)
ですが
水道事業者としては水道水も入れて欲しいと思います
まだ残暑きびしい日が続きます
お体を大事にして 実りの季節を迎えましょう
その中からの情報の提供です
「水道かわら版」もそのひとつです
そこに「ペットボトル症候群」という記載が目にとまりました
紹介します
9月になったものの 相変わらず暑さが続いています
暑さに負けないためには
水分補給と熱中症対策が欠かせませんが
「ペットボトル症候群」という大きな落とし穴があります
一般的に 熱中症はこまめな水分補給が
一番効果的とされています
だから 外出時にはペットボトルを持ち
水分の補給をするのが常識です
しかし ここに大きな落とし穴があります
コーラやスポーツドリンク 清涼飲料水などの糖質の多い飲料を
飲み続けていると「ペットボトル症候群」になってしまいます
血糖値が上がり急性の糖尿病の危険性があります
発症者の多くが 大量に飲んでいたところからこの名が付けられました
軽度の症状で 「ボーッとする」「落ち着きがなくなる」
最悪は意識障害を起こして倒れることも
甘いペットボトルにはご用心
お茶・ミネラルウォーターがよさそうです

(写真:水飲もうポスター)
ですが
水道事業者としては水道水も入れて欲しいと思います
まだ残暑きびしい日が続きます
お体を大事にして 実りの季節を迎えましょう
2013年09月18日
筑後川流域情報共有懇話会「報告」
昨年から始まり 第2回目の会議です
筑後川流域の利水を運用する関係団体の「長」の懇話会です
主催者の水資源機構の中西筑後川局長は
ここ数年夏場の水事情が悪い 雨台風のお陰で回復したが
まだまだ心配は続く
九州地方整備局の後藤管理官は
会議の主旨は流域の自然や環境上の種問題を共有する
やはり 話題は豪雨と渇水
気象庁が今年は異常気象との見解
ただし この傾向は今後も続くと想定
との挨拶で会議が進行
「水利用」の説明では
「川の水は人間のみのものではない 内水面 外水面 当然感心は高い
例えば 流域併せての海苔出荷高は全国の半分の生産を誇る」
だからこそ
私たち都市用水利用者は「おかげさまで」が必要
また「水資源開発」の説明では
「6月の灌漑期 筑後大堰・瀬の下地点での流量は40m3/sを割り込む
有明海を考えたら 大きな課題 努力を続けたい」

(写真:筑後大堰 左下が上流側、右上が下流側)
大堰築造時の下流域との約束 当然いろいろな努力が必要
佐賀東部としても一定の役割があると再認識
あと流域内の環境維持の取り組みや
有明海への豪雨時のゴミの流出と処分の内容等の報告
5時過ぎてからは 懇親会
私にとっては 関係する方々と情報の交換をする大事な時間
しかし 前日までの台風来襲予報で一旦は中止の連絡
即 別の用事を入れた後の懇親会再開催の一報
皆さん方 失礼をして申し訳ありませんでした
筑後川流域の利水を運用する関係団体の「長」の懇話会です
主催者の水資源機構の中西筑後川局長は
ここ数年夏場の水事情が悪い 雨台風のお陰で回復したが
まだまだ心配は続く
九州地方整備局の後藤管理官は
会議の主旨は流域の自然や環境上の種問題を共有する
やはり 話題は豪雨と渇水
気象庁が今年は異常気象との見解
ただし この傾向は今後も続くと想定
との挨拶で会議が進行
「水利用」の説明では
「川の水は人間のみのものではない 内水面 外水面 当然感心は高い
例えば 流域併せての海苔出荷高は全国の半分の生産を誇る」
だからこそ
私たち都市用水利用者は「おかげさまで」が必要
また「水資源開発」の説明では
「6月の灌漑期 筑後大堰・瀬の下地点での流量は40m3/sを割り込む
有明海を考えたら 大きな課題 努力を続けたい」

(写真:筑後大堰 左下が上流側、右上が下流側)
大堰築造時の下流域との約束 当然いろいろな努力が必要
佐賀東部としても一定の役割があると再認識
あと流域内の環境維持の取り組みや
有明海への豪雨時のゴミの流出と処分の内容等の報告
5時過ぎてからは 懇親会
私にとっては 関係する方々と情報の交換をする大事な時間
しかし 前日までの台風来襲予報で一旦は中止の連絡
即 別の用事を入れた後の懇親会再開催の一報
皆さん方 失礼をして申し訳ありませんでした
2013年09月17日
「胸のつかえ」が取れた
基山の浄水場が完成し 順調に運転中です
総工費も大きく 東部水道としては大きな投資でした
「胸のつかえ」の原因は この計画時点でのこと
当然 私が就任する前のことです
ここの計画は 民間事業者が有する技術力
ノウハウ等を有効に活用するために
設計施工の一括発注(デザイン・ビルド)方式により実施しました

(写真:基山浄水場)
その選定は
総合評価一般競争入札方式という堅苦しい名前で
簡単に言えば
「提案された案」を比較検討して業者を選定すること です
新しい浄化方式でもあり実証実験の実施も求めてきました
業者選定や実証実験は 公正に行う目的で
第三者による委員会で決定していただきました
そこで お願いした専門の先生方に対しての
「胸のつかえ」でした
本来ならば
その選定に関わった方々やたくさんお世話になった方々に対して
おかげで立派な施設が出来上がりました と
完了式でご披露するのが筋です
しかし 完了の式典を諸般の事情で実施しませんでした
関わったおおくの方々は いろんな場面で完成後の姿を
見て頂きましたが
「事業者選定委員会」の皆さまには
その機会がないまま 日にちだけが過ぎていました

(写真:施設内視察の様子)
そんななか 足を運んでいただき実現しました
先生方も 立派に完成し順調な運転を続けていることを確認され
「安心した」との言葉もいただきました
先生方 ありがとうございました
総工費も大きく 東部水道としては大きな投資でした
「胸のつかえ」の原因は この計画時点でのこと
当然 私が就任する前のことです
ここの計画は 民間事業者が有する技術力
ノウハウ等を有効に活用するために
設計施工の一括発注(デザイン・ビルド)方式により実施しました

(写真:基山浄水場)
その選定は
総合評価一般競争入札方式という堅苦しい名前で
簡単に言えば
「提案された案」を比較検討して業者を選定すること です
新しい浄化方式でもあり実証実験の実施も求めてきました
業者選定や実証実験は 公正に行う目的で
第三者による委員会で決定していただきました
そこで お願いした専門の先生方に対しての
「胸のつかえ」でした
本来ならば
その選定に関わった方々やたくさんお世話になった方々に対して
おかげで立派な施設が出来上がりました と
完了式でご披露するのが筋です
しかし 完了の式典を諸般の事情で実施しませんでした
関わったおおくの方々は いろんな場面で完成後の姿を
見て頂きましたが
「事業者選定委員会」の皆さまには
その機会がないまま 日にちだけが過ぎていました

(写真:施設内視察の様子)
そんななか 足を運んでいただき実現しました
先生方も 立派に完成し順調な運転を続けていることを確認され
「安心した」との言葉もいただきました
先生方 ありがとうございました
2013年09月13日
凍結工法
凍結工法の現地見学会があるので職員を参加させたい
旨の書類を見て
「エーッそんな工法があるのか」
「柔らかい地盤を固めるための薬液注入工法は知っているが・・」
「たぶん、薬液の代わりに凍結させるのだろう」
「しかし、地盤をどうやって凍結させるんだ?」
等々思いを馳せていました。
その後、参加した職員から聞いたら
私の想像は全て間違っていました。
この現場は、水道の本管から分岐した先の水道管部分を
都合で修理(撤去)をする必要があった
本管はたくさんの利用者に水を届けなくてはいけないので
水をストップさせて工事をする訳にはいけない
そこで、分岐部分を管ごと、中の水道水も凍結させる。
そうすれば
分岐の水道管には水道水は流れずに工事をすることが出来る
簡単に言えばそういうことでした。

(写真:凍結工法の現場)
凍結の方法は、分岐部分に発泡スチロールで枠をして
その枠の中に液体窒素を送り込む
時間がたてば当然「凍ってしまいます」
その間に、必要な工事をする
その工事後は、自然解凍をする。

(写真:凍結工法に用いる液体窒素)

(写真:分岐部を急冷し凍結させます)

(写真:「凍結後の分岐切り離し作業」凍結しているため、水は出ません)

(写真:凍結している間に蓋をします)

(写真:液体窒素を外しましたが、まだ白く凍結しています)

(写真:工事完了後は、自然解凍です)
そんな工法でした
東部水道企業団としては、この工法を利用することは
「ほぼない」とのことでした。
この工法の利点は「施工面積が少ない」「費用が安価」
欠点は「急速な冷凍による劣化の心配」
「鉄製品はいいが、ビニール管は割れる恐れがある」
「流水中の止水は難しい」
との報告を受けました。
旨の書類を見て
「エーッそんな工法があるのか」
「柔らかい地盤を固めるための薬液注入工法は知っているが・・」
「たぶん、薬液の代わりに凍結させるのだろう」
「しかし、地盤をどうやって凍結させるんだ?」
等々思いを馳せていました。
その後、参加した職員から聞いたら
私の想像は全て間違っていました。
この現場は、水道の本管から分岐した先の水道管部分を
都合で修理(撤去)をする必要があった
本管はたくさんの利用者に水を届けなくてはいけないので
水をストップさせて工事をする訳にはいけない
そこで、分岐部分を管ごと、中の水道水も凍結させる。
そうすれば
分岐の水道管には水道水は流れずに工事をすることが出来る
簡単に言えばそういうことでした。
(写真:凍結工法の現場)
凍結の方法は、分岐部分に発泡スチロールで枠をして
その枠の中に液体窒素を送り込む
時間がたてば当然「凍ってしまいます」
その間に、必要な工事をする
その工事後は、自然解凍をする。
(写真:凍結工法に用いる液体窒素)
(写真:分岐部を急冷し凍結させます)
(写真:「凍結後の分岐切り離し作業」凍結しているため、水は出ません)
(写真:凍結している間に蓋をします)
(写真:液体窒素を外しましたが、まだ白く凍結しています)
(写真:工事完了後は、自然解凍です)
そんな工法でした
東部水道企業団としては、この工法を利用することは
「ほぼない」とのことでした。
この工法の利点は「施工面積が少ない」「費用が安価」
欠点は「急速な冷凍による劣化の心配」
「鉄製品はいいが、ビニール管は割れる恐れがある」
「流水中の止水は難しい」
との報告を受けました。
2013年09月12日
京友禅に携わる人々
毎日の朝礼で
今回は、京友禅の着物に関する内容でした
京友禅の絵柄の下絵を描くのに
職人さんは「青花(あおばな)」という花の花弁を
絞った汁を使って下絵を描くそうです
この「青花」を栽培していた農家は
昔は約500軒あったが現在は2軒
このうちの1軒がテレビで紹介され
80代の老夫婦が京友禅の
一翼を担っているとの話
「青花」のしぼり汁を和紙に
塗り込み乾かすという工程を約80回繰り返す
この和紙を下絵師が切手程度の大きさに切り
水を入れた皿に溶かし
筆で下絵を描いていく
ではなぜ「青花」なのか?
下絵師曰く
「青花」で下絵を描くと着物の生地ににじみが出ない
化学染料ではにじんでしまう
下絵の線の上に
先端が細い器具を使って糊(のり)でなぞる
このあと水洗いすると
「青花」で書いた下絵の青がきれいに消えてしまう
乾かして色付けの工程となり
糊(のり)が土手となって隣の色と混ざらない役目となる
最後に京友禅をつくるには
いろいろな職人さんの合作であり
どれか一つが欠けても仕上がらないとの話だった
伝統工芸を支える次の世代は
間違いなく必要だ
今回は、京友禅の着物に関する内容でした
京友禅の絵柄の下絵を描くのに
職人さんは「青花(あおばな)」という花の花弁を
絞った汁を使って下絵を描くそうです
この「青花」を栽培していた農家は
昔は約500軒あったが現在は2軒
このうちの1軒がテレビで紹介され
80代の老夫婦が京友禅の
一翼を担っているとの話
「青花」のしぼり汁を和紙に
塗り込み乾かすという工程を約80回繰り返す
この和紙を下絵師が切手程度の大きさに切り
水を入れた皿に溶かし
筆で下絵を描いていく
ではなぜ「青花」なのか?
下絵師曰く
「青花」で下絵を描くと着物の生地ににじみが出ない
化学染料ではにじんでしまう
下絵の線の上に
先端が細い器具を使って糊(のり)でなぞる
このあと水洗いすると
「青花」で書いた下絵の青がきれいに消えてしまう
乾かして色付けの工程となり
糊(のり)が土手となって隣の色と混ざらない役目となる
最後に京友禅をつくるには
いろいろな職人さんの合作であり
どれか一つが欠けても仕上がらないとの話だった
伝統工芸を支える次の世代は
間違いなく必要だ
2013年09月11日
長期計画ヒア「営業課」
営業課は、佐賀市(川副町・東与賀町・諸富町)・神埼市
及び吉野ヶ里町の水道料金に関する事務を担当します。

(写真:企業団本庁舎1階の「営業課」)
議論の中身は
先日の三養基営業所との議論とほぼ同じ内容となりました。
宅地の増加に伴う「新設加入負担金」
家を新築して水道を利用する時の負担金ですが
人口減少は当然予想していますが
現況では、新設加入負担金の見込みに近い件数で
給水世帯数が増加し、水道使用料金は「微増」中です。
今後10年程度は「現在の状況が続く」
しかし、安全側を見て「過去3か年の最低値を使う」
が提案でした。
企業団経営の基本のところですので
慎重な議論をする必要があります
慎重を期して、最低値を使用することに「了解しました」
また、各市町で下水道の普及が進んでいます
東部水道企業団は、各市町の「下水道料金の徴収」を
「受託する」が方針です。
一部の市町とは、すでに委託契約を行い実施しています
未契約の市町との新規受託に向けた仕事も重要です。
企業団に委託するメリットは
水道とセットでの徴収で必然的に徴収率はアップすること
そこで未受託の市町との委託契約の時期も視野にいれています
市町は収納率アップ、企業団は受託費用の増加が狙いです。
これで、一応の各部署とのヒアリングは終了しました
積み残している課題や料金の考え方、職員定数、財政の収支等々
今後は企業団の方針として確立させていきます
当然、その経過も随時ご報告します。
及び吉野ヶ里町の水道料金に関する事務を担当します。
(写真:企業団本庁舎1階の「営業課」)
議論の中身は
先日の三養基営業所との議論とほぼ同じ内容となりました。
宅地の増加に伴う「新設加入負担金」
家を新築して水道を利用する時の負担金ですが
人口減少は当然予想していますが
現況では、新設加入負担金の見込みに近い件数で
給水世帯数が増加し、水道使用料金は「微増」中です。
今後10年程度は「現在の状況が続く」
しかし、安全側を見て「過去3か年の最低値を使う」
が提案でした。
企業団経営の基本のところですので
慎重な議論をする必要があります
慎重を期して、最低値を使用することに「了解しました」
また、各市町で下水道の普及が進んでいます
東部水道企業団は、各市町の「下水道料金の徴収」を
「受託する」が方針です。
一部の市町とは、すでに委託契約を行い実施しています
未契約の市町との新規受託に向けた仕事も重要です。
企業団に委託するメリットは
水道とセットでの徴収で必然的に徴収率はアップすること
そこで未受託の市町との委託契約の時期も視野にいれています
市町は収納率アップ、企業団は受託費用の増加が狙いです。
これで、一応の各部署とのヒアリングは終了しました
積み残している課題や料金の考え方、職員定数、財政の収支等々
今後は企業団の方針として確立させていきます
当然、その経過も随時ご報告します。
2013年09月10日
長期計画ヒア「三養基営業所」
三養基営業所は、基山町・上峰町・みやき町の
水道管の維持管理、水道料金に関する事務を担当しています。
営業所は、みやき町役場の北茂安庁舎の一部を借りており
職員は、所長を含めて12名です。

(写真:みやき町北茂安庁舎内にある「三養基営業所」)
さて、議論になった課題は
宅地の増加に伴う「新設加入負担金」
家を新築して水道を利用する時の負担金です。
すでに人口減少が進み、将来の予想値も示されていますが
有り難いことに東部水道の域内では、若干の人口減少はありますが
新設加入負担金の見込みに近い件数で給水世帯数が増加し
水道使用料金は「微増」中です。
この状況をどうみるか?
どこかの時点で
人口の減に伴い、水道使用料も減少のカーブをたどるはず
と思いますが、その予想が実際は難しい状況にあります
企業団経営の基本のところですので
慎重な議論をする必要があります。
また、下水道の普及が進み、一部の市町と
「下水道料金の徴収」の委託契約を行い実施しています。
未契約の市町との受託に向けた仕事も重要です
企業団に委託するメリットは、水道とセットでの徴収となることで
必然的に徴収率がアップすることです。
工務関係では、地域に企業団の重要な施設が点在しており
30年を経過した施設が多く、計画的な更新が必要です。
具体的に話を聞き、議論をし
「次の世代にツケをまわさない」を基本に計画を立てます。
水道管の維持管理、水道料金に関する事務を担当しています。
営業所は、みやき町役場の北茂安庁舎の一部を借りており
職員は、所長を含めて12名です。

(写真:みやき町北茂安庁舎内にある「三養基営業所」)
さて、議論になった課題は
宅地の増加に伴う「新設加入負担金」
家を新築して水道を利用する時の負担金です。
すでに人口減少が進み、将来の予想値も示されていますが
有り難いことに東部水道の域内では、若干の人口減少はありますが
新設加入負担金の見込みに近い件数で給水世帯数が増加し
水道使用料金は「微増」中です。
この状況をどうみるか?
どこかの時点で
人口の減に伴い、水道使用料も減少のカーブをたどるはず
と思いますが、その予想が実際は難しい状況にあります
企業団経営の基本のところですので
慎重な議論をする必要があります。
また、下水道の普及が進み、一部の市町と
「下水道料金の徴収」の委託契約を行い実施しています。
未契約の市町との受託に向けた仕事も重要です
企業団に委託するメリットは、水道とセットでの徴収となることで
必然的に徴収率がアップすることです。
工務関係では、地域に企業団の重要な施設が点在しており
30年を経過した施設が多く、計画的な更新が必要です。
具体的に話を聞き、議論をし
「次の世代にツケをまわさない」を基本に計画を立てます。
2013年09月09日
長期計画ヒア「工務2課」
工務2課は、佐賀市(川副町・東与賀町・諸富町)・神埼市
及び吉野ヶ里町の水道管の維持管理を担当する部署です。
建設の時代は終わり、維持・管理の必要性がますます増しており
皆様のお宅に、日々かわらぬ様に水道水を届ける大事な仕事です。
ここで議論になったことは三点
一点目は「現在の繁忙状態」その原因は下水道工事との関連です
特に佐賀市は
4~5年後の下水道の完成を目指して工事量が増大しています。
その関連での水道管の移設等や立会で
時間を取られている状態が続いています。
問題は「その後の仕事があるか?」
心配には及びませんでした
水道管の更新は際限なく続きそうです。
二点目は「漏水事故や漏水量」の状況についてです
毎年、管の更新は行っていますが、既存管の老朽化は進みます
「追いついているのか?」ということです。

(写真:安定供給を行うため、夜間にも修繕工事を行っています)
心配いりません、確実に毎年漏水量は減少しています
職員の印象でも10年前と比較し「確実に良くなっている」でした。
三点目は配水池等の今後の計画です
築30年を経過している施設が増えてきています。
日常の管理や器機の更新は当然ですが
今後の改築を予想した計画をどう立てるか?
議論を深めました
いろいろな状況を想定し、長期間での費用比較も行い
「一番良い方法」を選択することが出来た
と思います。
職員と、また職員間の議論を深める
方法は、直論すれば千差万別
その中で「利用者の皆様にとって良かれ」の方法を見い出す
そんなシナリオが定着しつつあると感じています。
及び吉野ヶ里町の水道管の維持管理を担当する部署です。
建設の時代は終わり、維持・管理の必要性がますます増しており
皆様のお宅に、日々かわらぬ様に水道水を届ける大事な仕事です。
ここで議論になったことは三点
一点目は「現在の繁忙状態」その原因は下水道工事との関連です
特に佐賀市は
4~5年後の下水道の完成を目指して工事量が増大しています。
その関連での水道管の移設等や立会で
時間を取られている状態が続いています。
問題は「その後の仕事があるか?」
心配には及びませんでした
水道管の更新は際限なく続きそうです。
二点目は「漏水事故や漏水量」の状況についてです
毎年、管の更新は行っていますが、既存管の老朽化は進みます
「追いついているのか?」ということです。
(写真:安定供給を行うため、夜間にも修繕工事を行っています)
心配いりません、確実に毎年漏水量は減少しています
職員の印象でも10年前と比較し「確実に良くなっている」でした。
三点目は配水池等の今後の計画です
築30年を経過している施設が増えてきています。
日常の管理や器機の更新は当然ですが
今後の改築を予想した計画をどう立てるか?
議論を深めました
いろいろな状況を想定し、長期間での費用比較も行い
「一番良い方法」を選択することが出来た
と思います。
職員と、また職員間の議論を深める
方法は、直論すれば千差万別
その中で「利用者の皆様にとって良かれ」の方法を見い出す
そんなシナリオが定着しつつあると感じています。
2013年09月06日
軽自動車の熾烈な争い
職員の朝のスピーチの紹介です。
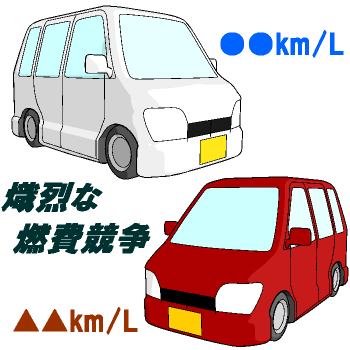
(イラスト:メーカーの意地を掛けた熾烈な燃費競争)
-----------------------------
現在、日本で売れている車トップ10のうち
なんと6台が軽自動車である。
そこには、自動車メーカー各社の意地とプライドをかけた
低燃費レースが繰り広げられている。
売れ筋のトールワゴン(3列シートを持たない「1.5ボックス」
タイプのミニバンを指す日本独自の呼び名)を例にとっても
昨年9月にS社が28.8km/Lを達成し、その3ヶ月後の12月には
ガチンコライバルのD社が29.0km/Lを達成したかと思えば
今年3月にはS社がD社に並んだ。
さらに6月には、ノーマークだったN社が29.2km/Lを達成し
トールワゴンのトップにたった。
すると今度はS社が異例のマイナーチェンジを決行し
なんと30.0km/Lの大台に乗った。
われわれ消費者からすると
その違いは実感できないレベルだろうが
自動車メーカーとしては、やはり1番じゃなきゃダメなんでしょう。
TPP参加で、軽自動車の優遇制度がなくなるとのうわさもあるが
庶民の生活の足として欠かせない日本独自の進化を遂げた
このガラパゴス自動車を守っていって欲しい。
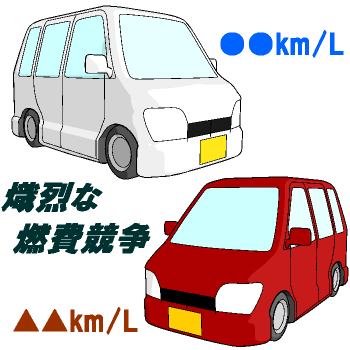
(イラスト:メーカーの意地を掛けた熾烈な燃費競争)
-----------------------------
現在、日本で売れている車トップ10のうち
なんと6台が軽自動車である。
そこには、自動車メーカー各社の意地とプライドをかけた
低燃費レースが繰り広げられている。
売れ筋のトールワゴン(3列シートを持たない「1.5ボックス」
タイプのミニバンを指す日本独自の呼び名)を例にとっても
昨年9月にS社が28.8km/Lを達成し、その3ヶ月後の12月には
ガチンコライバルのD社が29.0km/Lを達成したかと思えば
今年3月にはS社がD社に並んだ。
さらに6月には、ノーマークだったN社が29.2km/Lを達成し
トールワゴンのトップにたった。
すると今度はS社が異例のマイナーチェンジを決行し
なんと30.0km/Lの大台に乗った。
われわれ消費者からすると
その違いは実感できないレベルだろうが
自動車メーカーとしては、やはり1番じゃなきゃダメなんでしょう。
TPP参加で、軽自動車の優遇制度がなくなるとのうわさもあるが
庶民の生活の足として欠かせない日本独自の進化を遂げた
このガラパゴス自動車を守っていって欲しい。
2013年09月05日
長期計画ヒア「浄水課(設備・機械)」
今後、北茂安浄水場の設備・機械が更新時期を迎えます
一つひとつに大きな金額が必要です。
例えば、高圧受電設備に23億円、電気関係の設備には6億円
ポンプ設備に11億円等々です。

(写真:「北茂安浄水場」の全景)
当然、既存の計画でも計上していますので金額は想定内です
問題はその更新時期と施工管理の体制の確保
担当部署は、十分精査して提案してくれました
基本的には納得いくものでした。
ただ、少々の疑問点をぶつけてみました
例えば、各々の設備の更新は事業的にも密度が高く
より専門的な知識も必要です。
当然、専門のコンサルの力が必要です
そこで「総合的な視点で検討しては」と提案しました。
例えば、浄水場改築時を見据えての計画、それとの整合性
また、将来の人口減社会に対応した更新計画等々です。
各事業に必要なコンサルへの委託費用と変らない金額で
そのことが検討されるならば、将来にむけて
無駄がない万全な更新計画が出来るはずです
「十分検討に値する」と考えます。
また、調整池等の設備も同じ問題を抱えています
例えば「白壁の調整池」、小山の上にありますが
敷地に余裕がありませんので、改築時は大変です。

(写真:標高約50m地点に建設されている「白壁中継ポンプ場」)
しかも、設備や屋根(ドーム)部分の改築の必要性が
内部議論になっています
その場所での改築が難しい、しかし更新は必要
その更新が無駄にならないためには
抜本的な「考え方の変更」の是非を健闘する必要性があるのでは
との問いも提起しました
今後、大いに議論を深めていきたいと思います。
なお、更新工事の完了した「基山浄水場」は、15年間は
施工者の責任で機器等の更新を含め、責任施工で
契約しているので、今後15年間の更新費用の発生はありません。
一つひとつに大きな金額が必要です。
例えば、高圧受電設備に23億円、電気関係の設備には6億円
ポンプ設備に11億円等々です。

(写真:「北茂安浄水場」の全景)
当然、既存の計画でも計上していますので金額は想定内です
問題はその更新時期と施工管理の体制の確保
担当部署は、十分精査して提案してくれました
基本的には納得いくものでした。
ただ、少々の疑問点をぶつけてみました
例えば、各々の設備の更新は事業的にも密度が高く
より専門的な知識も必要です。
当然、専門のコンサルの力が必要です
そこで「総合的な視点で検討しては」と提案しました。
例えば、浄水場改築時を見据えての計画、それとの整合性
また、将来の人口減社会に対応した更新計画等々です。
各事業に必要なコンサルへの委託費用と変らない金額で
そのことが検討されるならば、将来にむけて
無駄がない万全な更新計画が出来るはずです
「十分検討に値する」と考えます。
また、調整池等の設備も同じ問題を抱えています
例えば「白壁の調整池」、小山の上にありますが
敷地に余裕がありませんので、改築時は大変です。
(写真:標高約50m地点に建設されている「白壁中継ポンプ場」)
しかも、設備や屋根(ドーム)部分の改築の必要性が
内部議論になっています
その場所での改築が難しい、しかし更新は必要
その更新が無駄にならないためには
抜本的な「考え方の変更」の是非を健闘する必要性があるのでは
との問いも提起しました
今後、大いに議論を深めていきたいと思います。
なお、更新工事の完了した「基山浄水場」は、15年間は
施工者の責任で機器等の更新を含め、責任施工で
契約しているので、今後15年間の更新費用の発生はありません。
2013年09月04日
長期計画ヒア「浄水課(構造物)」
企業団には、「北茂安浄水場」と「基山浄水場」の
2つの浄水場があります。
基山浄水場は、施設の老朽化及び能力増強のため
浄水施設の更新を行い、平成25年1月に竣工しました。

(写真:更新工事を完了した「基山浄水場」)
残る北茂安浄水場については、建設から30年を経て
設備や機械が古くなり、更新時期を迎えている状況です。
建物や土木構造物も「日頃の手入れ」を怠っていると長くは持ちません
そんな視点をもってヒアリングに臨みました
今回は、構造物についてです。
コンクリート構造物の耐用年数は60年です
今は、丁度半分の30年を過ぎたところで
原則的には、30年後には全面改修が必要です。
視点は、各設備等の更新が無駄にならないことと
1年でも長く構造物を持たせる
この二つです。

(写真:昭和59年度から稼働している「北茂安浄水場」)
無駄にならない更新計画は当然想定内のこと
問題は、構造物を長くもたせるための投資内容と金額です。
耐震に対する補強は現在施工中ですので
一般的な維持管理について議論を行いました。
二点です
一点目は、建物の屋上の排水、屋根の無いコンクリート造り
当然、雨水が直接たまるため排水を行なっていますが
防水機能の劣化防止を決定。
二点目は、構造物の劣化防止には
ひび割れ補修と全面的な塗装を決定しました。
ここ浄水場の改築には多大の費用が必要です
当然ですが「長く使う」が基本です。
2つの浄水場があります。
基山浄水場は、施設の老朽化及び能力増強のため
浄水施設の更新を行い、平成25年1月に竣工しました。
(写真:更新工事を完了した「基山浄水場」)
残る北茂安浄水場については、建設から30年を経て
設備や機械が古くなり、更新時期を迎えている状況です。
建物や土木構造物も「日頃の手入れ」を怠っていると長くは持ちません
そんな視点をもってヒアリングに臨みました
今回は、構造物についてです。
コンクリート構造物の耐用年数は60年です
今は、丁度半分の30年を過ぎたところで
原則的には、30年後には全面改修が必要です。
視点は、各設備等の更新が無駄にならないことと
1年でも長く構造物を持たせる
この二つです。
(写真:昭和59年度から稼働している「北茂安浄水場」)
無駄にならない更新計画は当然想定内のこと
問題は、構造物を長くもたせるための投資内容と金額です。
耐震に対する補強は現在施工中ですので
一般的な維持管理について議論を行いました。
二点です
一点目は、建物の屋上の排水、屋根の無いコンクリート造り
当然、雨水が直接たまるため排水を行なっていますが
防水機能の劣化防止を決定。
二点目は、構造物の劣化防止には
ひび割れ補修と全面的な塗装を決定しました。
ここ浄水場の改築には多大の費用が必要です
当然ですが「長く使う」が基本です。
2013年09月03日
長期計画ヒア「浄水課(水質)」
長期計画策定作業の一環としての企業長ヒアリング
今回から、浄水課をご紹介します。
浄水課関連は多岐にわたり、各々の部署に課題があり
しかも全ての機器が更新時期を迎えている状況にあって
少々の気合を入れて臨みました。
大きくわけて
「水質」「建築構造物」「設備・機械」がありますので
順次お知らせしていきます、まずは水質関係です。
今後20年間の「水質検査等の基本部分は直営」で行なう
そのためには、検査機器の更新は当然ありますが
大きな出費はありません、既存の全体計画のとおりです。
その議論のなかで、いろいろな課題がでましたので
その中の一つだけ紹介します。
それは、河川の水質のことです
企業団の水源は筑後川の水です
その水質が「年々悪くなっている、結果浄化するための費用がかさむ」
私たちの仕事は、水道水として安全な水を皆様の家庭に届ける
あたり前のことです。
ただし
「安全でおいしい水」をつくる為には様々な努力が必要になります。
ここで、筑後川の水質が悪いとは「泥臭がある」要するに土臭さです
それを除去するには「活性炭」が必要です。
端的な話が、泥臭が強ければ、それだけ多くの活性炭が必要です
その活性炭が非常に高い
その「高い価格の材料」を多く使用せざるを得ないことが問題です。

(写真:基山浄水場に設置している「粉末活性炭供給施設」)
なぜ、筑後川の水が悪くなっているか?
それは、科学的な根拠に基づいたことではありませんが
最近の気候環境が最も影響しているのでは、との話でした。
今年もそうでしたが、雨がなかなか降らない
トータルの雨量に違いはないが、降る時は「ドカッ」と降る
出来れば、雨は満遍なく降ってもらいたいものです。
今回から、浄水課をご紹介します。
浄水課関連は多岐にわたり、各々の部署に課題があり
しかも全ての機器が更新時期を迎えている状況にあって
少々の気合を入れて臨みました。
大きくわけて
「水質」「建築構造物」「設備・機械」がありますので
順次お知らせしていきます、まずは水質関係です。
今後20年間の「水質検査等の基本部分は直営」で行なう
そのためには、検査機器の更新は当然ありますが
大きな出費はありません、既存の全体計画のとおりです。
その議論のなかで、いろいろな課題がでましたので
その中の一つだけ紹介します。
それは、河川の水質のことです
企業団の水源は筑後川の水です
その水質が「年々悪くなっている、結果浄化するための費用がかさむ」
私たちの仕事は、水道水として安全な水を皆様の家庭に届ける
あたり前のことです。
ただし
「安全でおいしい水」をつくる為には様々な努力が必要になります。
ここで、筑後川の水質が悪いとは「泥臭がある」要するに土臭さです
それを除去するには「活性炭」が必要です。
端的な話が、泥臭が強ければ、それだけ多くの活性炭が必要です
その活性炭が非常に高い
その「高い価格の材料」を多く使用せざるを得ないことが問題です。
(写真:基山浄水場に設置している「粉末活性炭供給施設」)
なぜ、筑後川の水が悪くなっているか?
それは、科学的な根拠に基づいたことではありませんが
最近の気候環境が最も影響しているのでは、との話でした。
今年もそうでしたが、雨がなかなか降らない
トータルの雨量に違いはないが、降る時は「ドカッ」と降る
出来れば、雨は満遍なく降ってもらいたいものです。
2013年09月02日
長期計画ヒア「用水係」
企業団の長期計画を策定中です
その作業の中で、大きな節目を迎えました。
それは、各部署で検討した原案に対する企業長ヒアリングです
随時、お知らせしていきます。
始めは、工務1課の中の用水係
送水管の布設計画や維持管理を担当する部署です。

(写真:口径600mm耐震管布設工事の様子)
大きな課題は、送水管のバイパス化の実施と
耐震管への本格更新の着手の時期・投資費用
および維持管理への考え方です。
説明の概要は
全体計画を想定して「今後の10年間のシナリオをどう描いたか」
ここでの考えのベースは
「人員は既存の数」「投資費用は上限と考える年3億円」
それに基づいた資料により説明を受けました
受ける側は、私と総務課長と財政係
考え方は理路整然と整理され
課題の把握や優先順位の考え方も納得できるものでした
しかし、今の状況は当然ですが「用水係のみ」を考えたもの
今後、全ての部署の話を聞き
企業団としての財政計画や人員計画・料金の設定等
総合的な判断が必要になります。
引き続き「職員みんなで考え、決める」
責任は「私」で進めます。
その作業の中で、大きな節目を迎えました。
それは、各部署で検討した原案に対する企業長ヒアリングです
随時、お知らせしていきます。
始めは、工務1課の中の用水係
送水管の布設計画や維持管理を担当する部署です。
(写真:口径600mm耐震管布設工事の様子)
大きな課題は、送水管のバイパス化の実施と
耐震管への本格更新の着手の時期・投資費用
および維持管理への考え方です。
説明の概要は
全体計画を想定して「今後の10年間のシナリオをどう描いたか」
ここでの考えのベースは
「人員は既存の数」「投資費用は上限と考える年3億円」
それに基づいた資料により説明を受けました
受ける側は、私と総務課長と財政係
考え方は理路整然と整理され
課題の把握や優先順位の考え方も納得できるものでした
しかし、今の状況は当然ですが「用水係のみ」を考えたもの
今後、全ての部署の話を聞き
企業団としての財政計画や人員計画・料金の設定等
総合的な判断が必要になります。
引き続き「職員みんなで考え、決める」
責任は「私」で進めます。

