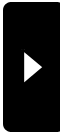2014年10月31日
河川美化「ノーポイ」運動
10月26日(日)
筑後川・矢部川河川美化「ノーポイ」運動が実施されました。
東部水道企業団からも
6名の職員が参加し、一斉清掃を行ってきました
参加の職員からの紹介です。

(写真:筑後大堰付近の清掃を担当しました)
-------------------------------
筑後川・矢部川河川美化「ノーポイ」運動とは
筑後川及び矢部川の河川堤防に不法投棄された空き缶、空き瓶
ゴミ等の一斉清掃です。
河川に物を捨てない「ノーポイ」を合言葉にした運動を推進し
河川美化意識の高揚と河川愛護思想の啓蒙に資することを
目的としています。
筑後川、矢部川及びその支線等を実施場所とし
大分県、福岡県、佐賀県の13市2町の沿川住民
国土交通省、関係自治体・団体の職員が参加しています。
今年で29回目を数える「ノーポイ」運動は
毎年2万人近くが参加する地域に根付いた活動です。

(写真:不燃物、可燃物いろいろなゴミがありました)
私たちも筑後川から取水し事業運営を行っているため
毎年この運動に参加し、活動に協力しています。

(写真:テレビや液晶モニタの不法投棄も)

(写真:収集場所に集められたゴミ)
昨年度のゴミ回収量は約28トンもあったそうですが
今年も不法投棄されたと思われるゴミが多数散見されました。
今後も河川環境を守るため
定期的な活動の必要性を切に感じました。
参加の皆様、お疲れ様でした。
筑後川・矢部川河川美化「ノーポイ」運動が実施されました。
東部水道企業団からも
6名の職員が参加し、一斉清掃を行ってきました
参加の職員からの紹介です。
(写真:筑後大堰付近の清掃を担当しました)
-------------------------------
筑後川・矢部川河川美化「ノーポイ」運動とは
筑後川及び矢部川の河川堤防に不法投棄された空き缶、空き瓶
ゴミ等の一斉清掃です。
河川に物を捨てない「ノーポイ」を合言葉にした運動を推進し
河川美化意識の高揚と河川愛護思想の啓蒙に資することを
目的としています。
筑後川、矢部川及びその支線等を実施場所とし
大分県、福岡県、佐賀県の13市2町の沿川住民
国土交通省、関係自治体・団体の職員が参加しています。
今年で29回目を数える「ノーポイ」運動は
毎年2万人近くが参加する地域に根付いた活動です。
(写真:不燃物、可燃物いろいろなゴミがありました)
私たちも筑後川から取水し事業運営を行っているため
毎年この運動に参加し、活動に協力しています。
(写真:テレビや液晶モニタの不法投棄も)
(写真:収集場所に集められたゴミ)
昨年度のゴミ回収量は約28トンもあったそうですが
今年も不法投棄されたと思われるゴミが多数散見されました。
今後も河川環境を守るため
定期的な活動の必要性を切に感じました。
参加の皆様、お疲れ様でした。
2014年10月30日
クローズアップ現代「水道ピンチ」
NHKのクローズアップ現代での「水道ピンチ」の報道
見た方も多かったと思います。
「蛇口をひねれば水が出る」当たり前のことですが
それが当たり前ではない日がくるかも知れない
そんな刺激的な内容で番組は始まりました。
モデルになったのは埼玉県の秩父市
水道の歴史は古く、大正13年に埼玉県初の水道として誕生
人口密度も低く人口減少にも悩まされ、収益は年々減少し
今年度からは大幅な赤字が見込まれているそうだ。
また、埋設されている水道管が古く漏水にも悩まされ
その補修にも予算がなく
追い付かない様子が映し出されていました。

(写真:水道管からの漏水の様子)
それが如実に表れている指標が「有収率」で
金を投入して作った水道水が
使用料金として回収されているかの指標ですが
「73.6%」とかなり低く、浄水した水の約3割が
家庭まで届かずに「途中で漏水」しているということです。
参考までに東部水道企業団との比較をしてみます
●秩父市
現在の給水人口 6万7千人
有収率 73.6%
水道料金 月10m3で1361円(H27年1月から1814円)
管路延長 597km
●東部水道企業団は
現在の給水人口 11万6千人
有収率 94.3%
水道料金 月10m3で1404円
管路延長 886km
東部水道企業団は
秩父市の状況までには至ってはいませんが
将来に向けて対策を講じなければ同じようになります。
また、大都会の人口密度の高い地域を除けば
日本国中が五十歩百歩の状況です。
今後、人口はますます減少し
尚且つ「低密度・分散型」になります
結果、あたり前ですが「効率は悪く」なります
現在、水道事業は1700の市町村等に分かれています。
番組では
「サービスの見直し」「優先度の決定」等々で
住民と共同で水道事業を維持していく例が紹介されました。
また、専門家のコメントとして
「身軽な設備等々」も示されていました。
いろいろ参考にはなりましたが、「他山の石」とせず
将来展望を持って課題に取り組む以外にありません。
現在行っている「連携協議」と「施設の省力化」を
いっそう進める決意を新たにした番組でした。
見た方も多かったと思います。
「蛇口をひねれば水が出る」当たり前のことですが
それが当たり前ではない日がくるかも知れない
そんな刺激的な内容で番組は始まりました。
モデルになったのは埼玉県の秩父市
水道の歴史は古く、大正13年に埼玉県初の水道として誕生
人口密度も低く人口減少にも悩まされ、収益は年々減少し
今年度からは大幅な赤字が見込まれているそうだ。
また、埋設されている水道管が古く漏水にも悩まされ
その補修にも予算がなく
追い付かない様子が映し出されていました。

(写真:水道管からの漏水の様子)
それが如実に表れている指標が「有収率」で
金を投入して作った水道水が
使用料金として回収されているかの指標ですが
「73.6%」とかなり低く、浄水した水の約3割が
家庭まで届かずに「途中で漏水」しているということです。
参考までに東部水道企業団との比較をしてみます
●秩父市
現在の給水人口 6万7千人
有収率 73.6%
水道料金 月10m3で1361円(H27年1月から1814円)
管路延長 597km
●東部水道企業団は
現在の給水人口 11万6千人
有収率 94.3%
水道料金 月10m3で1404円
管路延長 886km
東部水道企業団は
秩父市の状況までには至ってはいませんが
将来に向けて対策を講じなければ同じようになります。
また、大都会の人口密度の高い地域を除けば
日本国中が五十歩百歩の状況です。
今後、人口はますます減少し
尚且つ「低密度・分散型」になります
結果、あたり前ですが「効率は悪く」なります
現在、水道事業は1700の市町村等に分かれています。
番組では
「サービスの見直し」「優先度の決定」等々で
住民と共同で水道事業を維持していく例が紹介されました。
また、専門家のコメントとして
「身軽な設備等々」も示されていました。
いろいろ参考にはなりましたが、「他山の石」とせず
将来展望を持って課題に取り組む以外にありません。
現在行っている「連携協議」と「施設の省力化」を
いっそう進める決意を新たにした番組でした。
2014年10月29日
群馬県太田市より行政視察
10月8日、群馬県太田市より議長さんと
3名の議員さんが行政視察にお見えになりました。
将来の水道についてどうあるべきか
お話しを伺いたかったのですが、当日はあいにく
出張があったためお会いできず申し訳なく思っております。
太田市さんでは
3市5町で「群馬東部水道基本構想」が策定され
水道事業の統合について計画されていて
県の用水供給事業からの受水もあるとのこと。
当企業団を視察先に選んでいただいたのは
当企業団が「用水供給事業」と「水道事業」の
2事業を行っている数少ない企業団であったためと思います。
以下は、対応した職員からの報告です。
-----------------------------
●視察の内容について
企業団設立の経緯が
群馬東部の水道事業とは多少異なることからお話しし
次の点について作成資料にて説明し、ご質問を受けました。
広域化、企業団化されたことによる
(1)水源の有効活用
(2)安定給水体制の確立
(3)維持管理、更新コストの削減
(4)災害対策
(5)サービス水準と品質の維持
(6)建設事業費の削減
(7)人件費等維持管理費の削減
(8)供給単価(水道料金)の変遷
※供給単価=年間の水道料金総額/水道料金となる年間総水量
いずれにも共通することですが
キャパが大きくなることはより質にも有効であること。
理想は、水源から蛇口までの広域化であること。
また、民間への委託の流れの中で
技術継承をどう図るか等の問題まで踏み込んでお話ししました。

(写真:視察の様子)
予定時間を過ぎても、熱心な質問等が続き
こちらにとっても広域化において違った立場の方の見方、考え方
を知ることができお受けしたことは非常に有意義でありました。
当企業団も
将来の人口減少による事業継続の地域連携を模索している中
太田市さんの広域化が進んだ折に
是非ともお話しを伺いたいと思っております
よろしく、お願いします。
遠い佐賀の地までお越しいただき
ありがとうございました。
3名の議員さんが行政視察にお見えになりました。
将来の水道についてどうあるべきか
お話しを伺いたかったのですが、当日はあいにく
出張があったためお会いできず申し訳なく思っております。
太田市さんでは
3市5町で「群馬東部水道基本構想」が策定され
水道事業の統合について計画されていて
県の用水供給事業からの受水もあるとのこと。
当企業団を視察先に選んでいただいたのは
当企業団が「用水供給事業」と「水道事業」の
2事業を行っている数少ない企業団であったためと思います。
以下は、対応した職員からの報告です。
-----------------------------
●視察の内容について
企業団設立の経緯が
群馬東部の水道事業とは多少異なることからお話しし
次の点について作成資料にて説明し、ご質問を受けました。
広域化、企業団化されたことによる
(1)水源の有効活用
(2)安定給水体制の確立
(3)維持管理、更新コストの削減
(4)災害対策
(5)サービス水準と品質の維持
(6)建設事業費の削減
(7)人件費等維持管理費の削減
(8)供給単価(水道料金)の変遷
※供給単価=年間の水道料金総額/水道料金となる年間総水量
いずれにも共通することですが
キャパが大きくなることはより質にも有効であること。
理想は、水源から蛇口までの広域化であること。
また、民間への委託の流れの中で
技術継承をどう図るか等の問題まで踏み込んでお話ししました。
(写真:視察の様子)
予定時間を過ぎても、熱心な質問等が続き
こちらにとっても広域化において違った立場の方の見方、考え方
を知ることができお受けしたことは非常に有意義でありました。
当企業団も
将来の人口減少による事業継続の地域連携を模索している中
太田市さんの広域化が進んだ折に
是非ともお話しを伺いたいと思っております
よろしく、お願いします。
遠い佐賀の地までお越しいただき
ありがとうございました。
2014年10月28日
企業会計及び財務管理勉強会に参加して
10月17日に職員が熊本県宇土市で開催された
「企業会計及び財務管理に関する勉強会」に
参加してきたので、担当職員から記事を紹介します。
------------------------------
この勉強会は公営企業会計や財務管理について
当面する課題に対し、佐賀、福岡及び熊本県内の
水道企業団で情報交換を行っているもので
当初は
平成22年3月同じ筑後川という水源を利用している
佐賀東部、福岡地区、福岡県南広域の
三企業団でスタートしました。
今回は熊本県宇土市で開催され、10団体23名が出席
開催地は、上天草・宇城水道企業団さんでした。
◆上天草・宇城水道企業団について
平成10年に設立された新しい企業団で、宇土市、宇城市
上天草市、天草市の4つの市10万7千人に
平成16年2月から水道用水を供給しています。
計画1日最大供給量は21,050m3
水源は八代市の球磨川であり、浄水場も八代市にあります。

(写真:大牟田駅から「快速くまもとライナー」に乗車)
二両編成だったのに驚き。

(写真:平成21年に新しくなった駅舎「宇土駅(うとえき)」)
ICカード式の改札機はありましたが
普通の切符を入れる場所がなく、駅員さんの前にある
小さな箱に入れるようになっていたので、少し戸惑いました。

(写真:宇土市役所の別館に行きます)

(写真:開催地の山本事務局長より挨拶があり議題を進めていきます)

(写真:議題は全部で7つ
真剣な議論や情報交換が行われました)
新会計基準への移行年度であることから、それらの課題がメイン
消費税改定への対応や課税・非課税の区分対応も。

(写真:次期開催は福岡地区水道企業団さん)
お世話になります、よろしくお願いします。
「企業会計及び財務管理に関する勉強会」に
参加してきたので、担当職員から記事を紹介します。
------------------------------
この勉強会は公営企業会計や財務管理について
当面する課題に対し、佐賀、福岡及び熊本県内の
水道企業団で情報交換を行っているもので
当初は
平成22年3月同じ筑後川という水源を利用している
佐賀東部、福岡地区、福岡県南広域の
三企業団でスタートしました。
今回は熊本県宇土市で開催され、10団体23名が出席
開催地は、上天草・宇城水道企業団さんでした。
◆上天草・宇城水道企業団について
平成10年に設立された新しい企業団で、宇土市、宇城市
上天草市、天草市の4つの市10万7千人に
平成16年2月から水道用水を供給しています。
計画1日最大供給量は21,050m3
水源は八代市の球磨川であり、浄水場も八代市にあります。
(写真:大牟田駅から「快速くまもとライナー」に乗車)
二両編成だったのに驚き。
(写真:平成21年に新しくなった駅舎「宇土駅(うとえき)」)
ICカード式の改札機はありましたが
普通の切符を入れる場所がなく、駅員さんの前にある
小さな箱に入れるようになっていたので、少し戸惑いました。
(写真:宇土市役所の別館に行きます)
(写真:開催地の山本事務局長より挨拶があり議題を進めていきます)
(写真:議題は全部で7つ
真剣な議論や情報交換が行われました)
新会計基準への移行年度であることから、それらの課題がメイン
消費税改定への対応や課税・非課税の区分対応も。
(写真:次期開催は福岡地区水道企業団さん)
お世話になります、よろしくお願いします。
2014年10月27日
秋・本番
すっかり日が落ちるのが早くなりました
もう、秋本番です。
佐賀平野にも実りの秋が満載です
夏の時期の雨(日照不足)で収穫が心配された稲も
その後の好天で、やや不良程度(作況指数96)
まで持ち直しているとのことで、一安心です。
米どころの佐賀平野
「良い米がたくさん採れた」で元気づきます
秋晴れの空の下
多くのコンバインが動いています。

(写真:近所の稲刈り風景)
黄金色のたわわに実り垂れ下がった稲穂の姿は
農業には関係がない私も
豊かな気持ちにしてくれます。
働きまわっている近くの水路には
ススキの白い穂を風が揺らしていました
近くに寄ったら、鯉や鮒やメダカの姿が・・・。
稲刈りが終わったら紅葉の季節
そして、冬に向かってまっしぐら
季節の変わり目です
皆さんもお体をお大事にご自愛ください。
もう、秋本番です。
佐賀平野にも実りの秋が満載です
夏の時期の雨(日照不足)で収穫が心配された稲も
その後の好天で、やや不良程度(作況指数96)
まで持ち直しているとのことで、一安心です。
米どころの佐賀平野
「良い米がたくさん採れた」で元気づきます
秋晴れの空の下
多くのコンバインが動いています。
(写真:近所の稲刈り風景)
黄金色のたわわに実り垂れ下がった稲穂の姿は
農業には関係がない私も
豊かな気持ちにしてくれます。
働きまわっている近くの水路には
ススキの白い穂を風が揺らしていました
近くに寄ったら、鯉や鮒やメダカの姿が・・・。
稲刈りが終わったら紅葉の季節
そして、冬に向かってまっしぐら
季節の変わり目です
皆さんもお体をお大事にご自愛ください。
2014年10月24日
視察の報告(4) 八戸のここが凄い
八戸の研修報告の最後です
少し前の資料や文献を読み返すと
良く出てくるのが「東の八戸、西の佐賀東部」という言葉です。
それは、両企業団が全国に先駆けて
水道の先進的広域化により生まれた企業団だからでしょう。
そのことを知り、八戸圏域水道企業団の事業展開や
時々お会いする指導部の方々とお話する機会を得ては
様々なことを学ばせてもらっていました。
また、今年の冬には、「うちの職員」の受け入れもお願いし
一皮むけて帰ってきました。

(写真:冬の「八戸圏域水道企業団」庁舎全景)
だから資料を読んだり
派遣した職員の話を聞いたりは常々して
一応の概要は知ってはいましたが、やはり行って良かった。
企業団の持つ全体の意識や指導部の先見性や実行力
おおいに刺激を受けました。
また、私たちの最大の課題と認識する
「水源の多源化」も実現していました
聞けば 発足当初からのシナリオだったとか。
素晴らしい
感服しました。
その実現も、広域化に展望を持つしかない状況も
当企業団と似ているのではと参考となります。
事例を参考にしつつ東部水道企業団らしい
連携シナリオを追及していくことで
50年後・100年後の水道の未来図を描きたいと思います。
最後になりましたが、八戸圏域水道企業団の皆様方
お世話になりました
ありがとうございました。
少し前の資料や文献を読み返すと
良く出てくるのが「東の八戸、西の佐賀東部」という言葉です。
それは、両企業団が全国に先駆けて
水道の先進的広域化により生まれた企業団だからでしょう。
そのことを知り、八戸圏域水道企業団の事業展開や
時々お会いする指導部の方々とお話する機会を得ては
様々なことを学ばせてもらっていました。
また、今年の冬には、「うちの職員」の受け入れもお願いし
一皮むけて帰ってきました。
(写真:冬の「八戸圏域水道企業団」庁舎全景)
だから資料を読んだり
派遣した職員の話を聞いたりは常々して
一応の概要は知ってはいましたが、やはり行って良かった。
企業団の持つ全体の意識や指導部の先見性や実行力
おおいに刺激を受けました。
また、私たちの最大の課題と認識する
「水源の多源化」も実現していました
聞けば 発足当初からのシナリオだったとか。
素晴らしい
感服しました。
その実現も、広域化に展望を持つしかない状況も
当企業団と似ているのではと参考となります。
事例を参考にしつつ東部水道企業団らしい
連携シナリオを追及していくことで
50年後・100年後の水道の未来図を描きたいと思います。
最後になりましたが、八戸圏域水道企業団の皆様方
お世話になりました
ありがとうございました。
2014年10月23日
視察の報告(3) 企業長研修の概要
先日から報告している研修の概要を紹介します
今回の企業長視察・研修は秋田県からの始まりです。
秋田県では、国指定重要文化財近代化遺産であり
秋田市水道の始まりでもある藤倉水源地を視察しました。

(写真:藤倉水源地の看板)
秋田市内には、旭川があり
明治時代より井戸水と併用し飲料水・生活用水として
重要な役割を担っていました。
しかし、人口増加や生活排水の流入により
旭川の水質汚染が進み生活に必要な飲料水の確保に
苦労するようになりました。
また、コレラや腸チフス、赤痢などの伝染病が流行し
水道を求める市民の願いは切実なものとなってきました。

(写真:藤倉水源地)
この時期は、明治20年の横浜市を皮切りに
全国各地で近代水道が急速に広がり始めたころで
秋田市でも、国庫補助金がなくとも市の独力で
水道布設工事に着手するという大きな決断をしましたが
日露戦争が勃発し思うように工事が進まず
苦難の連続でしたが、ようやく明治39年に
藤倉水源地から浄水場までの送水管通水に見通しが立ち
明治40年10月に市内一部地域に飲料水供給が正式に開始され
全国で11番目、東北地方初の通水となりました。
この様な歴史のある水源地で
秋田市民の願いのこもった施設でした。
2日目は「玉川ダム」視察で、このダムは
上流部にある玉川温泉の大噴から流れ出す強酸性泉が
玉川の水を酸性に変えるため上流に中和処理施設があり
ダム湖は宝仙湖と呼ばれ、中和処理施設から
流出した石灰水を撹拌中和させることを目的としており
青い湖水が特徴です。

(写真:「玉川ダム」ダム湖)

(写真:「玉川ダム」資料室)
有効貯水容量は、全国で7番目の大きさがあり
100メートルクラスのダムの中で
日本初のRCD工法(コンクリートダムの合理化施工法)により
平成2年に完成したダムでした。

(写真:「玉川ダム」ダム堤体)
最終日は、八戸圏域水道企業団での水道の広域化と
危機管理のテーマにした勉強会でした。
私の感想は、すべてにおいて「さすが東の八戸」でした
広域化の考え方
東日本大震災を経験された上での危機管理体制
備蓄品など、さすがでした。

(写真:今回の研修参加者と)
今回の企業長視察・研修のテーマは
「水道の歴史を再認識し、今後の経営、危機管理を考える」
でしたので充実した視察・研修でした。
今回の企業長視察・研修は秋田県からの始まりです。
秋田県では、国指定重要文化財近代化遺産であり
秋田市水道の始まりでもある藤倉水源地を視察しました。
(写真:藤倉水源地の看板)
秋田市内には、旭川があり
明治時代より井戸水と併用し飲料水・生活用水として
重要な役割を担っていました。
しかし、人口増加や生活排水の流入により
旭川の水質汚染が進み生活に必要な飲料水の確保に
苦労するようになりました。
また、コレラや腸チフス、赤痢などの伝染病が流行し
水道を求める市民の願いは切実なものとなってきました。
(写真:藤倉水源地)
この時期は、明治20年の横浜市を皮切りに
全国各地で近代水道が急速に広がり始めたころで
秋田市でも、国庫補助金がなくとも市の独力で
水道布設工事に着手するという大きな決断をしましたが
日露戦争が勃発し思うように工事が進まず
苦難の連続でしたが、ようやく明治39年に
藤倉水源地から浄水場までの送水管通水に見通しが立ち
明治40年10月に市内一部地域に飲料水供給が正式に開始され
全国で11番目、東北地方初の通水となりました。
この様な歴史のある水源地で
秋田市民の願いのこもった施設でした。
2日目は「玉川ダム」視察で、このダムは
上流部にある玉川温泉の大噴から流れ出す強酸性泉が
玉川の水を酸性に変えるため上流に中和処理施設があり
ダム湖は宝仙湖と呼ばれ、中和処理施設から
流出した石灰水を撹拌中和させることを目的としており
青い湖水が特徴です。
(写真:「玉川ダム」ダム湖)
(写真:「玉川ダム」資料室)
有効貯水容量は、全国で7番目の大きさがあり
100メートルクラスのダムの中で
日本初のRCD工法(コンクリートダムの合理化施工法)により
平成2年に完成したダムでした。
(写真:「玉川ダム」ダム堤体)
最終日は、八戸圏域水道企業団での水道の広域化と
危機管理のテーマにした勉強会でした。
私の感想は、すべてにおいて「さすが東の八戸」でした
広域化の考え方
東日本大震災を経験された上での危機管理体制
備蓄品など、さすがでした。
(写真:今回の研修参加者と)
今回の企業長視察・研修のテーマは
「水道の歴史を再認識し、今後の経営、危機管理を考える」
でしたので充実した視察・研修でした。
2014年10月22日
視察の報告(2) 八戸の広域連携に学ぶ
昨日の続きです
テーマの2点目「広域連携」の現状です。
現在でも八戸圏域水道企業団として
広域で事業の展開がなされていますが
将来は県をまたいでの連携を模索されています。
その理由は、全国の水道が直面している
少子化・過疎化による人口減少
また、更新・耐震化等の財源確保
及び団塊世代の退職や職員の人事異動などによる
職員の技術力や専門知識の不足があります。
こうした課題は、個々の水道事業体単独では限界があり
相互に情報を交換し連携していくことが重要です。
もちろん私たちも同じ課題と展望を持っています
そこで青森・岩手と県境を越えて考えられている
「北奥羽地区水道事業協議会」の考え方や
進展具合を知りたくての訪問でした。
平成19年に、22の水道事業体で第一歩が踏み出され
今年度に「八戸圏域周辺地域における新たな広域的水道基本調査」
を実施されています。
この中で4つの基本的視点の合意をみました
その4つとは
「施設の共同化」「施設管理の共同化」
「水質データ管理の共同化」「システムの共同化」です。
それらを具体化するための専門部会が設置され
スケジュールも示されていました。
今後の展開には注視して行きますが
課題が明確であり、その対処方針がシンプルで分かりやすく
多いに刺激を頂いたところです。
広域連携や広域化を避けては通れません
私たちが今議論していることが
正しい道だとの確信を得ました。
八戸圏域を十分に意識したうえで
東部水道企業団や周辺水道の未来を語り
「良かれ」のシナリオを描いていきたいと考えます。
テーマの2点目「広域連携」の現状です。
現在でも八戸圏域水道企業団として
広域で事業の展開がなされていますが
将来は県をまたいでの連携を模索されています。
その理由は、全国の水道が直面している
少子化・過疎化による人口減少
また、更新・耐震化等の財源確保
及び団塊世代の退職や職員の人事異動などによる
職員の技術力や専門知識の不足があります。
こうした課題は、個々の水道事業体単独では限界があり
相互に情報を交換し連携していくことが重要です。
もちろん私たちも同じ課題と展望を持っています
そこで青森・岩手と県境を越えて考えられている
「北奥羽地区水道事業協議会」の考え方や
進展具合を知りたくての訪問でした。
平成19年に、22の水道事業体で第一歩が踏み出され
今年度に「八戸圏域周辺地域における新たな広域的水道基本調査」
を実施されています。
この中で4つの基本的視点の合意をみました
その4つとは
「施設の共同化」「施設管理の共同化」
「水質データ管理の共同化」「システムの共同化」です。
それらを具体化するための専門部会が設置され
スケジュールも示されていました。
今後の展開には注視して行きますが
課題が明確であり、その対処方針がシンプルで分かりやすく
多いに刺激を頂いたところです。
広域連携や広域化を避けては通れません
私たちが今議論していることが
正しい道だとの確信を得ました。
八戸圏域を十分に意識したうえで
東部水道企業団や周辺水道の未来を語り
「良かれ」のシナリオを描いていきたいと考えます。
2014年10月21日
視察の報告(1) 八戸の危機管理に学ぶ
筑後川からの水を頂き水道事業を行っている
筑後川流域の三つの企業団
すなわち、福岡地区水道企業団
福岡県南広域水道企業団と
私たち佐賀東部水道企業団の企業長が合同で行った
視察・研修の報告です。
目的は大きくはふたつ
「危機管理」と「広域連携」でした。
特に青森県の八戸圏域水道企業団の状況を知りたい
ここは、先進的な施策を持つ企業団です。
まずは「危機管理」についての報告です
八戸は地震に襲われた土地で
その危機感が「私たちとは違う」と正直そう思いました
しかし、だからこその危機管理の研修地でもありました。
今の企業団の前身である八戸市水道は
昭和45年の十勝沖地震で甚大な水道管路被害を受けて
翌年からの拡張工事の事業では
管路の地震対策を取り組まれています。
企業団発足後も踏襲され
その後の平成6年の三陸はるか沖地震以後は
全てを耐震管で施工されています。
平成30年度までの管路全体の耐震化率の目標を
50%と設定し努力をされていました。
現在時点での耐震化率は38.4%
そのうちの基幹管路は70%でありました
東部水道企業団の基幹管路の耐震化率は34.3%です。

(写真:耐震管の布設工事の様子)
主要構造物も着々と整備中でしたが、この部分は
我が東部水道企業団も劣ってはいないと思います。
また、配水池の貯留能力を
30時間目標に増設等が行われていました。
このことは大変重要な視点で
非常時(施設事故・災害時等)に一定の時間は
貯留している水で家庭への配水を確保することが出来ます。
私たち東部水道企業団の貯水容量は約15時間分です。

(写真:東部水道企業団の「中原調整池」貯水容量33,690m3)
また、今度の東日本大震災の教訓を生かした整備も
数々行われています。
例えば、長時間停電に対応する自家発電装置の
燃料確保のための燃料タンクの増設や
周辺給油所との優先確保の協定
また、浄水場で使用する各種薬品の
貯蔵の管理基準制定や備蓄倉庫
災害時の資材等々の確保や応援体制および訓練等々
全てにおいて先進でした。
このことを参考にして早速
私たちの危機管理計画の再確認
必要な見直しを指示したところです。
筑後川流域の三つの企業団
すなわち、福岡地区水道企業団
福岡県南広域水道企業団と
私たち佐賀東部水道企業団の企業長が合同で行った
視察・研修の報告です。
目的は大きくはふたつ
「危機管理」と「広域連携」でした。
特に青森県の八戸圏域水道企業団の状況を知りたい
ここは、先進的な施策を持つ企業団です。
まずは「危機管理」についての報告です
八戸は地震に襲われた土地で
その危機感が「私たちとは違う」と正直そう思いました
しかし、だからこその危機管理の研修地でもありました。
今の企業団の前身である八戸市水道は
昭和45年の十勝沖地震で甚大な水道管路被害を受けて
翌年からの拡張工事の事業では
管路の地震対策を取り組まれています。
企業団発足後も踏襲され
その後の平成6年の三陸はるか沖地震以後は
全てを耐震管で施工されています。
平成30年度までの管路全体の耐震化率の目標を
50%と設定し努力をされていました。
現在時点での耐震化率は38.4%
そのうちの基幹管路は70%でありました
東部水道企業団の基幹管路の耐震化率は34.3%です。
(写真:耐震管の布設工事の様子)
主要構造物も着々と整備中でしたが、この部分は
我が東部水道企業団も劣ってはいないと思います。
また、配水池の貯留能力を
30時間目標に増設等が行われていました。
このことは大変重要な視点で
非常時(施設事故・災害時等)に一定の時間は
貯留している水で家庭への配水を確保することが出来ます。
私たち東部水道企業団の貯水容量は約15時間分です。

(写真:東部水道企業団の「中原調整池」貯水容量33,690m3)
また、今度の東日本大震災の教訓を生かした整備も
数々行われています。
例えば、長時間停電に対応する自家発電装置の
燃料確保のための燃料タンクの増設や
周辺給油所との優先確保の協定
また、浄水場で使用する各種薬品の
貯蔵の管理基準制定や備蓄倉庫
災害時の資材等々の確保や応援体制および訓練等々
全てにおいて先進でした。
このことを参考にして早速
私たちの危機管理計画の再確認
必要な見直しを指示したところです。
2014年10月20日
ねんりんピック栃木2014
「ねんりんピック」に参加した職員からの紹介です。
●ねんりんピックとは、全国健康福祉祭の愛称です
60歳以上の方々を中心として
あらゆる世代の人たちが楽しみ
交流を深めることができる総合的な祭典です。
厚生省創立50周年を記念して
昭和63(1988)年に第1回大会が開催されて以来
毎年開催されており、平成26年の第27回大会は
栃木県で開催されました。
------------------------------
10月4日(土)~6日(月)の日程で
栃木県宇都宮市及び壬生町で開催された
「ねんりんピック栃木2014」のサッカー交流大会に
佐賀県代表として初めて参加してきました。

(写真:サッカー交流大会開始式でのレセプションの様子)
【咲かせよう!長寿の花を 栃木路で】が
今年度、第27回大会の大会スローガンでした。
主催は、厚生労働省・栃木県
一般財団法人長寿社会開発センター
ねんりんピック栃木2014実行委員会
宇都宮市実行委員会・壬生町実行委員会です。
今回の栃木大会では
県内の14市6町で20種目のスポーツ
4種目の文化交流大会等が開催されました。
その中の1種目サッカー交流大会に
FW(フォワード)として出場しました。
他に、健康マージャン交流大会に興味がありましたが
応援には行けませんでした。
サッカー交流大会は、監督含め20名が1チームで
全国から64チーム1,160名が参加されました。
64チームを16ブロックに分け
4県総当たりでブロック毎に成績が決定されます。
試合時間は、前後半20分、ハーフタイム5分
1試合45分で、1試合交代は8人までです。
最高高齢者は、三重県の男性84歳の方
女性は和歌山県63歳の方で表彰を受けられました。
私も、頑張って三重県の方くらいの年齢になるまで
参加できればと思いました。
そのためには、日常の練習が非常に重要です
また、年齢に応じて
楽しく練習・試合ができればと思います。
佐賀県は、Mブロック
チーム名は、佐賀県シニア選抜(O-60)
14名の参加で、最高高齢者は71歳の方でした
私は、まだハナタレ小僧くらいかも(笑い)。

(写真:試合の様子)
1回戦は10月5日(日)11時45分開始
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場で
対戦相手は、地元栃木選抜Over60チーム。
朝から台風18号の影響で雨が降り、気温12度
雨中の決戦で前半1対0、後半2対0で
地の利、走力、総合力で3対0
栃木では花を咲かせることはできませんでしたが
コート内を走り周ることはできました
しかし悔しいー。(もっと練習しなければ・・・)
2・3回戦は、10月6日(月)9時・12時40分
栃木県総合運動公園ラクビー場で対戦相手は
長野県(信州惑々サッカークラブ)と
滋賀県(滋賀選抜)の予定でしたが
1回戦終了間際に台風18号の影響で中止が決まり
交流戦ができず非常に残念でした。
しかし、負けたにも関わらず、「成績なし」
と結果往来だったかもしれません。
2試合できなかった分、来年も是非出場し
次回開催地の山口県で花を咲かせたいと思います。
最後になりましたが、今回の参加にあたり
栃木県の大会関係者の皆様
レセプションで大会を盛り上げて頂いた皆様
楽しい一時でした。
10月5日(日)は、雨が降って寒い中
本当にありがとうございました。
企業団職員の皆様、応援ありがとうございました
多くの方の御支援で、退職を迎える年に
ねんりんピックに参加でき大変嬉しく思っています。
(公財)佐賀県長寿社会振興財団の皆様
神埼市高齢障がい課の皆様、ありがとうございました。
佐賀県サッカー協会の皆様、チームメイトの皆様
力にはなれまれませんでしたが本当に良い思い出ができました
ありがとうございました。
●ねんりんピックとは、全国健康福祉祭の愛称です
60歳以上の方々を中心として
あらゆる世代の人たちが楽しみ
交流を深めることができる総合的な祭典です。
厚生省創立50周年を記念して
昭和63(1988)年に第1回大会が開催されて以来
毎年開催されており、平成26年の第27回大会は
栃木県で開催されました。
------------------------------
10月4日(土)~6日(月)の日程で
栃木県宇都宮市及び壬生町で開催された
「ねんりんピック栃木2014」のサッカー交流大会に
佐賀県代表として初めて参加してきました。
(写真:サッカー交流大会開始式でのレセプションの様子)
【咲かせよう!長寿の花を 栃木路で】が
今年度、第27回大会の大会スローガンでした。
主催は、厚生労働省・栃木県
一般財団法人長寿社会開発センター
ねんりんピック栃木2014実行委員会
宇都宮市実行委員会・壬生町実行委員会です。
今回の栃木大会では
県内の14市6町で20種目のスポーツ
4種目の文化交流大会等が開催されました。
その中の1種目サッカー交流大会に
FW(フォワード)として出場しました。
他に、健康マージャン交流大会に興味がありましたが
応援には行けませんでした。
サッカー交流大会は、監督含め20名が1チームで
全国から64チーム1,160名が参加されました。
64チームを16ブロックに分け
4県総当たりでブロック毎に成績が決定されます。
試合時間は、前後半20分、ハーフタイム5分
1試合45分で、1試合交代は8人までです。
最高高齢者は、三重県の男性84歳の方
女性は和歌山県63歳の方で表彰を受けられました。
私も、頑張って三重県の方くらいの年齢になるまで
参加できればと思いました。
そのためには、日常の練習が非常に重要です
また、年齢に応じて
楽しく練習・試合ができればと思います。
佐賀県は、Mブロック
チーム名は、佐賀県シニア選抜(O-60)
14名の参加で、最高高齢者は71歳の方でした
私は、まだハナタレ小僧くらいかも(笑い)。
(写真:試合の様子)
1回戦は10月5日(日)11時45分開始
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場で
対戦相手は、地元栃木選抜Over60チーム。
朝から台風18号の影響で雨が降り、気温12度
雨中の決戦で前半1対0、後半2対0で
地の利、走力、総合力で3対0
栃木では花を咲かせることはできませんでしたが
コート内を走り周ることはできました
しかし悔しいー。(もっと練習しなければ・・・)
2・3回戦は、10月6日(月)9時・12時40分
栃木県総合運動公園ラクビー場で対戦相手は
長野県(信州惑々サッカークラブ)と
滋賀県(滋賀選抜)の予定でしたが
1回戦終了間際に台風18号の影響で中止が決まり
交流戦ができず非常に残念でした。
しかし、負けたにも関わらず、「成績なし」
と結果往来だったかもしれません。
2試合できなかった分、来年も是非出場し
次回開催地の山口県で花を咲かせたいと思います。
最後になりましたが、今回の参加にあたり
栃木県の大会関係者の皆様
レセプションで大会を盛り上げて頂いた皆様
楽しい一時でした。
10月5日(日)は、雨が降って寒い中
本当にありがとうございました。
企業団職員の皆様、応援ありがとうございました
多くの方の御支援で、退職を迎える年に
ねんりんピックに参加でき大変嬉しく思っています。
(公財)佐賀県長寿社会振興財団の皆様
神埼市高齢障がい課の皆様、ありがとうございました。
佐賀県サッカー協会の皆様、チームメイトの皆様
力にはなれまれませんでしたが本当に良い思い出ができました
ありがとうございました。
2014年10月17日
監査委員の主要施設視察 基山浄水場
今回は、送水施設と
基山浄水場の視察の様子を紹介します。
北茂安浄水場からのメイン管(送水管)を
目視できる場所があるのでご案内しました。

(写真:口径1100mmの水管橋)
北茂安浄水場で作られた浄水(水道水)は、
いったん白壁中継ポンプ場に送られ
更に中原調整池に圧送された後、
自然流下方式で各構成団体に届けられます。

(写真:中原調整池は、16,845m3の池が二つ。標高は約100m)
中原調整池の場所は
高速道路の鳥栖インターと東脊振インターの中間地点あたり
山沿いにあるので結構目立つ施設です。
一方の基山浄水場は、鳥栖市を挟んで飛び地となっている
三養基郡基山町の水道水を作る施設。
町内に大きな河川水源がなかったので
創設時は、工業用水を水源として利用していました
現在は、浄水場までは(独)水資源機構の福岡導水より
筑後川の原水を取り入れ
安心して飲める水道水にしてお届けしています。

(写真:浄水処理施設の更新工事が完成した基山浄水場)
基山浄水場は、平成25年1月に
浄水処理施設の更新を完成しました。
それまでは、従来方式の急速ろ過処理でしたが
既存施設を運転しながら、既存の敷地内で
新・増設する必要があったため
コンパクトな膜処理方式を選定しました。

(写真:北茂安浄水場と同様ここでも中央監視室で管理しています)

(写真:膜処理モジュール)
セラミック膜ろ過装置の膜モジュールは
0.1ミクロンより大きいゴミは通りません
1ミクロンは、1000分の1ミリです。

(写真:0.1ミクロンの穴を持つセラミック膜)

(写真:この膜モジュールを入れた槽は4つあります)

(写真:一つの槽に528個の膜モジュールが入っています)

(写真:膜ろ過水ポンプ)

(写真:各種薬品を注入する設備)

(写真:濃縮汚泥設備)

(写真:天日乾燥床)
この他、水質試験室や自家発電機
太陽光発電設備も備えています。
以上駆け足でしたが
水源施設を除く主要な施設を視察していただきました。
監査委員からは、
「百聞は一見にしかず、大変よく分かりました」とのこと。
今後も将来を見据えた効率的な事業運営を
行っていくよう努めますので、よろしくお願いします。
基山浄水場の視察の様子を紹介します。
北茂安浄水場からのメイン管(送水管)を
目視できる場所があるのでご案内しました。
(写真:口径1100mmの水管橋)
北茂安浄水場で作られた浄水(水道水)は、
いったん白壁中継ポンプ場に送られ
更に中原調整池に圧送された後、
自然流下方式で各構成団体に届けられます。
(写真:中原調整池は、16,845m3の池が二つ。標高は約100m)
中原調整池の場所は
高速道路の鳥栖インターと東脊振インターの中間地点あたり
山沿いにあるので結構目立つ施設です。
一方の基山浄水場は、鳥栖市を挟んで飛び地となっている
三養基郡基山町の水道水を作る施設。
町内に大きな河川水源がなかったので
創設時は、工業用水を水源として利用していました
現在は、浄水場までは(独)水資源機構の福岡導水より
筑後川の原水を取り入れ
安心して飲める水道水にしてお届けしています。
(写真:浄水処理施設の更新工事が完成した基山浄水場)
基山浄水場は、平成25年1月に
浄水処理施設の更新を完成しました。
それまでは、従来方式の急速ろ過処理でしたが
既存施設を運転しながら、既存の敷地内で
新・増設する必要があったため
コンパクトな膜処理方式を選定しました。
(写真:北茂安浄水場と同様ここでも中央監視室で管理しています)
(写真:膜処理モジュール)
セラミック膜ろ過装置の膜モジュールは
0.1ミクロンより大きいゴミは通りません
1ミクロンは、1000分の1ミリです。
(写真:0.1ミクロンの穴を持つセラミック膜)
(写真:この膜モジュールを入れた槽は4つあります)
(写真:一つの槽に528個の膜モジュールが入っています)
(写真:膜ろ過水ポンプ)
(写真:各種薬品を注入する設備)
(写真:濃縮汚泥設備)
(写真:天日乾燥床)
この他、水質試験室や自家発電機
太陽光発電設備も備えています。
以上駆け足でしたが
水源施設を除く主要な施設を視察していただきました。
監査委員からは、
「百聞は一見にしかず、大変よく分かりました」とのこと。
今後も将来を見据えた効率的な事業運営を
行っていくよう努めますので、よろしくお願いします。
2014年10月16日
監査委員の主要施設視察 北茂安浄水場(2)
昨日からの続きです
北茂安浄水場の屋外施設も視察してもらいました。
取水口から取水した水は、活性炭を入れた後
沈砂池で大きなゴミが取り除かれ着水井に流れてきます。

(写真:着水井と急速混和池)
急速混和池で
PACや苛性ソーダを入れて急速に混ぜ合わせます。

(写真:フロック形成池のフロキュレータが見えています)
このフロキュレーター(羽根)で
ゆっくり撹拌することにより、水の中の小さなゴミが
大きなかたまり(フロック)になります。
実際の運転時は水が入っているのですが
運転管理サイクルの関係で池に水がない時もあります。

(写真:ブルーになっているのは今回耐震補強した部分)
北茂安浄水場では
三年間をかけて主要施設の耐震化に取り組んでおり
今年度がその最終年度となっています。

(写真:稼働しているフロック形成池)

(写真:薬品沈でん池の下にゆっくりとフロックが沈んでいきます)

(写真:沈殿池のうわ水だけを集めます)

(写真:見た目ではかなりきれいな水になっています)
更にそれを砂の層でろ過して
塩素を加えたのが浄水(水道水)です。
続きます。
北茂安浄水場の屋外施設も視察してもらいました。
取水口から取水した水は、活性炭を入れた後
沈砂池で大きなゴミが取り除かれ着水井に流れてきます。
(写真:着水井と急速混和池)
急速混和池で
PACや苛性ソーダを入れて急速に混ぜ合わせます。
(写真:フロック形成池のフロキュレータが見えています)
このフロキュレーター(羽根)で
ゆっくり撹拌することにより、水の中の小さなゴミが
大きなかたまり(フロック)になります。
実際の運転時は水が入っているのですが
運転管理サイクルの関係で池に水がない時もあります。
(写真:ブルーになっているのは今回耐震補強した部分)
北茂安浄水場では
三年間をかけて主要施設の耐震化に取り組んでおり
今年度がその最終年度となっています。
(写真:稼働しているフロック形成池)
(写真:薬品沈でん池の下にゆっくりとフロックが沈んでいきます)
(写真:沈殿池のうわ水だけを集めます)
(写真:見た目ではかなりきれいな水になっています)
更にそれを砂の層でろ過して
塩素を加えたのが浄水(水道水)です。
続きます。
2014年10月15日
監査委員の主要施設視察 北茂安浄水場(1)
企業団の監査委員として
新しく就任された久保監査委員に
企業団の主要施設を視察していただきました。
【監査委員とは?】
予算の執行や財産の管理等の企業団経営について
公正で効率的な運営が確保されているかどうかを
点検する委員。
東部水道企業団では、企業長が議会の同意を得て
事業の経営管理について専門の知識又は経験を
有する2名の方を選任しています。

(写真:計画最大給水量 94,000m3/日の北茂安浄水場)
北茂安浄水場から視察を開始
先ずは中央操作室で、運転管理の概略を説明。

(写真:久保監査委員(左)と説明する大串浄水課長)

(写真:屋上の展望室からの浄水場全体)
取水口や筑後大堰との位置関係を確認してもらいました。
次は一階の水質試験室。

(写真:野田浄水課長補佐から水質試験の概要説明)
それぞれの工程での処理水をここで分析しています
その都度、外の沈殿池等に出向く必要はありません。

(写真:見学者の方が試飲できるスペースも設けています)
「筑後川のめぐみ のんでんしゃい」と名付けたボトル水を
危機管理の一環として浄水場にも備蓄しています。
地下の各種施設にもご案内しました。

(写真:次亜塩素酸注入設備)

(写真:苛性ソーダやPAC注入設備もここ管理本館の下にあります)
他には、万が一の停電に備えた自家発電設備もあります。
次は屋外の浄水施設に続きます。
新しく就任された久保監査委員に
企業団の主要施設を視察していただきました。
【監査委員とは?】
予算の執行や財産の管理等の企業団経営について
公正で効率的な運営が確保されているかどうかを
点検する委員。
東部水道企業団では、企業長が議会の同意を得て
事業の経営管理について専門の知識又は経験を
有する2名の方を選任しています。

(写真:計画最大給水量 94,000m3/日の北茂安浄水場)
北茂安浄水場から視察を開始
先ずは中央操作室で、運転管理の概略を説明。
(写真:久保監査委員(左)と説明する大串浄水課長)
(写真:屋上の展望室からの浄水場全体)
取水口や筑後大堰との位置関係を確認してもらいました。
次は一階の水質試験室。
(写真:野田浄水課長補佐から水質試験の概要説明)
それぞれの工程での処理水をここで分析しています
その都度、外の沈殿池等に出向く必要はありません。
(写真:見学者の方が試飲できるスペースも設けています)
「筑後川のめぐみ のんでんしゃい」と名付けたボトル水を
危機管理の一環として浄水場にも備蓄しています。
地下の各種施設にもご案内しました。
(写真:次亜塩素酸注入設備)
(写真:苛性ソーダやPAC注入設備もここ管理本館の下にあります)
他には、万が一の停電に備えた自家発電設備もあります。
次は屋外の浄水施設に続きます。
2014年10月14日
年度の半分が終了「課題等の状況」
今年度の課題は大きくは3点
1点目は「長期展望とその課題の克服」
「20年間の長期計画」は策定しました。
課題はありますが「経営はやっていけます」
しかし40~50年後をみたらどうか?
大きな課題があります。
40年後の人口は現在の7割に減少します
一方では、浄水場等の大規模な更新時期を迎えます
これは東部水道企業団に限ったことではありません。
その解決のためのシナリオは
周辺事業体との連携以外には考えられません
「話し合い」が始まりました。
2点目は「技術・経営の継承」です
すでに日常的な継承作業が行われています。
ここでの視点は
継承を受ける若手職員の意識が特に重要です。
継承なくしては
自分が困るし企業団を背負うことはできません
「日頃の議論」しか方法はありません。
3点目は、企業団の「強みをさらに磨く」です。
その強みとは
「用水供給事業」「水道事業」の両方の事業を
行っている全国でも稀な企業団。
当然、職員は「水道事業一筋」
ここに最大の強みがあり
それをもっと磨く必要があります。
そのためには
全員で課題を議論して「全員で事にあたる」
成果は、いろんなところで出ていると思っています。
今年度も残り半分
私も気を引き締めなおして課題の克服にあたります。
1点目は「長期展望とその課題の克服」
「20年間の長期計画」は策定しました。
課題はありますが「経営はやっていけます」
しかし40~50年後をみたらどうか?
大きな課題があります。
40年後の人口は現在の7割に減少します
一方では、浄水場等の大規模な更新時期を迎えます
これは東部水道企業団に限ったことではありません。
その解決のためのシナリオは
周辺事業体との連携以外には考えられません
「話し合い」が始まりました。
2点目は「技術・経営の継承」です
すでに日常的な継承作業が行われています。
ここでの視点は
継承を受ける若手職員の意識が特に重要です。
継承なくしては
自分が困るし企業団を背負うことはできません
「日頃の議論」しか方法はありません。
3点目は、企業団の「強みをさらに磨く」です。
その強みとは
「用水供給事業」「水道事業」の両方の事業を
行っている全国でも稀な企業団。
当然、職員は「水道事業一筋」
ここに最大の強みがあり
それをもっと磨く必要があります。
そのためには
全員で課題を議論して「全員で事にあたる」
成果は、いろんなところで出ていると思っています。
今年度も残り半分
私も気を引き締めなおして課題の克服にあたります。
2014年10月10日
財政課へ異動して
平成26年4月、財政課を発足させました
業務の流れを円滑にすることを目指した機構改革です。
現在、財政課財政係という
一係の布陣で業務にあたっています。
財政課発足と同時に、人事異動で
財政課に異動してきた職員に感想を聞きました。
------------------------------
4月に財政課に異動してきて、早くも半年が過ぎました
以前、経理課(平成23年度廃止)にいたものの
離れて6年、浦島太郎です。
また、今年度から新会計制度へ移行しており
ますますパニックです。

(写真:新会計制度についての研修会の様子)
以前の経理課は、予算を作り執行する経理係と
支払・決算業務を行う出納係の二つの係に分かれており
別々の業務を行っていました。
今回、一つの係になったことで予算から決算までの
業務の円滑化を図る意図があります。
しかし、業務の流れが確立しておらず
効率性を求める工夫が必要と感じます。
先日参加した研修のおかげで
新会計制度に対する理解度も高まってきました。
まだまだ、他の方に頼ることが多いですが
学び、経験して、レベルアップを目指します。
業務の流れを円滑にすることを目指した機構改革です。
現在、財政課財政係という
一係の布陣で業務にあたっています。
財政課発足と同時に、人事異動で
財政課に異動してきた職員に感想を聞きました。
------------------------------
4月に財政課に異動してきて、早くも半年が過ぎました
以前、経理課(平成23年度廃止)にいたものの
離れて6年、浦島太郎です。
また、今年度から新会計制度へ移行しており
ますますパニックです。

(写真:新会計制度についての研修会の様子)
以前の経理課は、予算を作り執行する経理係と
支払・決算業務を行う出納係の二つの係に分かれており
別々の業務を行っていました。
今回、一つの係になったことで予算から決算までの
業務の円滑化を図る意図があります。
しかし、業務の流れが確立しておらず
効率性を求める工夫が必要と感じます。
先日参加した研修のおかげで
新会計制度に対する理解度も高まってきました。
まだまだ、他の方に頼ることが多いですが
学び、経験して、レベルアップを目指します。
2014年10月09日
「水道水の白濁」事故の顛末(2)
昨日の続きです
工事によって送水管に空気が混入し
「水道水が白濁」するという事態が生じました。
神埼市神埼町石井ヶ里や神埼駅通り他の皆様には
ご迷惑をおかけしました、申し訳ありませんでした。
このことの経過と状況は、昨日お知らせしました
このことについて何点かの課題がありました。
1点目は「空気を混入させたままで家庭に送水」した
この原因は、昨日の説明どおりに
「空気が混入している」状態を見抜けませんでした。
今後も同じような工事はあります
万全を図るためには、その真の原因究明が重要です。
担当はある一定期間で異動し変わります
「原因究明」とその「継承」が大事です、十分議論し
特に失敗事例の継承ルールを確立するように指示しました。
2点目は「原因究明」に絡むことですが
今回のような状況をなくすためには
設備等の設置も必要ですが
しかし、投資は最小限にも大事なことです。
そこで維持・管理を考えた
「再構築の案」提出も指示しました。
3点目はお恥ずかしい話ですが、この報告が
事故発生から10日後の課長会の報告事項で聞きました。
このような事項は「即・報告」です
厳しく指摘をしました。
まだまだ課題がある東部水道企業団ですが
「利用者のために」を肝に銘じ、今後も経営・運営していきます。
工事によって送水管に空気が混入し
「水道水が白濁」するという事態が生じました。
神埼市神埼町石井ヶ里や神埼駅通り他の皆様には
ご迷惑をおかけしました、申し訳ありませんでした。
このことの経過と状況は、昨日お知らせしました
このことについて何点かの課題がありました。
1点目は「空気を混入させたままで家庭に送水」した
この原因は、昨日の説明どおりに
「空気が混入している」状態を見抜けませんでした。
今後も同じような工事はあります
万全を図るためには、その真の原因究明が重要です。
担当はある一定期間で異動し変わります
「原因究明」とその「継承」が大事です、十分議論し
特に失敗事例の継承ルールを確立するように指示しました。
2点目は「原因究明」に絡むことですが
今回のような状況をなくすためには
設備等の設置も必要ですが
しかし、投資は最小限にも大事なことです。
そこで維持・管理を考えた
「再構築の案」提出も指示しました。
3点目はお恥ずかしい話ですが、この報告が
事故発生から10日後の課長会の報告事項で聞きました。
このような事項は「即・報告」です
厳しく指摘をしました。
まだまだ課題がある東部水道企業団ですが
「利用者のために」を肝に銘じ、今後も経営・運営していきます。
2014年10月08日
「水道水の白濁」事故の顛末(1)
水道工事に伴って一部の地域にご迷惑をおかけしました。
概要は、送水管の仕切弁設置工事の際に発生しました
送水管とは各市町に水道水を送る「主要な水道管」で
その送水管の途中に仕切弁を設置するのが工事の目的でした。
仕切弁とは、水道管に事故があった場合に
影響を最小限度に抑えるための設備です。
この工事は、一時「水を止め(断水)」
管を切断し、切断した管の間に仕切弁を設置します。
工事の間は、管内に水道水が入っていない状態
工事完了後(仕切弁設置後)は速やかに水を流しますが
その時に注意することは、空になった部分の空気を
全て管外に排出する必要があることです。
しかし、その排出しなければならない空気の一部が
管内に残り、流域の方々の家庭内の水道水に
一時「白濁」した水を供給してしまいました。
------------------------------
【水道水が白く濁っているが?(対処法)】
白い濁りの主な原因は、空気の混入によるものです
しばらく置いておくと濁りが消える場合は
空気の混入が原因ですので普段どおりにご使用頂けます。
放置しても濁りが取れない場合は
他の原因が考えられますので
エリア内の営業所までご連絡ください。
------------------------------
影響を与えました
神埼市神埼町石井ヶ里の全戸
及び駅通り・本堀・鶴・西小津ヶ里・田道ヶ里・枝ヶ里地区
それに神埼市千代田町姉地区の方々
皆様方にはご迷惑をおかけしました。
「白濁」解消のために
「捨て水(蛇口から排出)」をお願いしましたので
相当分の水道使用量は減免をいたします。
以上が水道水の「白濁」の顛末ですが
工事にまつわる問題や維持管理上の課題がみえました
このことは明日に報告します。
概要は、送水管の仕切弁設置工事の際に発生しました
送水管とは各市町に水道水を送る「主要な水道管」で
その送水管の途中に仕切弁を設置するのが工事の目的でした。
仕切弁とは、水道管に事故があった場合に
影響を最小限度に抑えるための設備です。
この工事は、一時「水を止め(断水)」
管を切断し、切断した管の間に仕切弁を設置します。
工事の間は、管内に水道水が入っていない状態
工事完了後(仕切弁設置後)は速やかに水を流しますが
その時に注意することは、空になった部分の空気を
全て管外に排出する必要があることです。
しかし、その排出しなければならない空気の一部が
管内に残り、流域の方々の家庭内の水道水に
一時「白濁」した水を供給してしまいました。
------------------------------
【水道水が白く濁っているが?(対処法)】
白い濁りの主な原因は、空気の混入によるものです
しばらく置いておくと濁りが消える場合は
空気の混入が原因ですので普段どおりにご使用頂けます。
放置しても濁りが取れない場合は
他の原因が考えられますので
エリア内の営業所までご連絡ください。
------------------------------
影響を与えました
神埼市神埼町石井ヶ里の全戸
及び駅通り・本堀・鶴・西小津ヶ里・田道ヶ里・枝ヶ里地区
それに神埼市千代田町姉地区の方々
皆様方にはご迷惑をおかけしました。
「白濁」解消のために
「捨て水(蛇口から排出)」をお願いしましたので
相当分の水道使用量は減免をいたします。
以上が水道水の「白濁」の顛末ですが
工事にまつわる問題や維持管理上の課題がみえました
このことは明日に報告します。
2014年10月07日
給水訓練への派遣依頼
先日、佐賀市諸富町の自主防災活動本部より
給水車と職員の派遣依頼がありました。
【諸富町自主防災活動本部とは?】
佐賀市諸富校区では「諸富町まちづくり協議会」を
設立し、子育て部会・暮らし部会・安心部会・
産業部会・交流部会の5部会を設け、まちづくりを
推進されています。
安心部会では、効率的事業推進を図るため
「諸富町自主防災活動本部」を設立し、活動が
行われています。
今回、諸富町産業祭が開催されるに当たり
自主防災広報活動のなかの一つの訓練として
被災時の給水活動訓練を行うというものです。

(写真:諸富町産業祭開会式の様子)
昨年度に新規配備した「給水車」の
住民の方を対象とした初めての訓練使用となります。

(写真:給水車と応急給水器具を設置)
今回、被災時に使用する「給水袋」の
使い方を説明し、実際に使用してもらいました。

(写真:訓練の様子1)

(写真:訓練の様子2)
企業団で使用している「給水袋」は
6リットルの背負い式となっています。
災害時には、1人1日最低3 リットルの水が必要と
いわれていますので、2人で使用する1日分の水が
この袋に入ります。

(写真:訓練の様子3)
「給水袋」を初めて使用した方も多く
「タメになった」との声もいただき、訓練の甲斐がありました。
災害が無い事が一番ですが
もし起こった際にできるだけ困らないように
今後も訓練を行っていきます。
給水車と職員の派遣依頼がありました。
【諸富町自主防災活動本部とは?】
佐賀市諸富校区では「諸富町まちづくり協議会」を
設立し、子育て部会・暮らし部会・安心部会・
産業部会・交流部会の5部会を設け、まちづくりを
推進されています。
安心部会では、効率的事業推進を図るため
「諸富町自主防災活動本部」を設立し、活動が
行われています。
今回、諸富町産業祭が開催されるに当たり
自主防災広報活動のなかの一つの訓練として
被災時の給水活動訓練を行うというものです。
(写真:諸富町産業祭開会式の様子)
昨年度に新規配備した「給水車」の
住民の方を対象とした初めての訓練使用となります。
(写真:給水車と応急給水器具を設置)
今回、被災時に使用する「給水袋」の
使い方を説明し、実際に使用してもらいました。
(写真:訓練の様子1)
(写真:訓練の様子2)
企業団で使用している「給水袋」は
6リットルの背負い式となっています。
災害時には、1人1日最低3 リットルの水が必要と
いわれていますので、2人で使用する1日分の水が
この袋に入ります。
(写真:訓練の様子3)
「給水袋」を初めて使用した方も多く
「タメになった」との声もいただき、訓練の甲斐がありました。
災害が無い事が一番ですが
もし起こった際にできるだけ困らないように
今後も訓練を行っていきます。
2014年10月06日
課長会の報告
東部水道企業団では、月初めに定例の課長会を開き
業務上の課題等の確認や情報の共有化を図っています
今回、10月の課長会の報告を行います。
1点目は、神埼市の下水道使用料の賦課漏れ
ニュースで流れ、ご存知の方も多いと思います。
今年の4月から下水道使用料の徴収事務を
神埼市より東部水道企業団が受託しました
水道料金と併せての一括徴収を行っています。
この一括徴収システムの
統合を図るためのデータの突合せ作業により
一部の方々に「下水道使用料が賦課されていない」ことが
判明しました。
その概要は、過去5年分の件数は205件
総金額は1532万5千円となっているようです。
この原因は
アパート等への入居の際に異動手続きが行われず
チェックができなかったことや
下水道使用開始届を受理したのに
登録処理を行っていなかったことのようです。
今後の対応は、早急に市役所の方で戸別訪問や調査がされ
過年度分の納付をお願いすることになると思います
市としても再発防止に向けた取り組みや
信頼回復に努められるものと思います。
東部水道企業団が下水道使用料の徴収を受託して
問題が明らかになり、結果的には良かったと思います。
2点目は、これも神埼市での問題ですが
水道工事によって送水管に空気が混入し
「水道水が白濁」するという事態が生じました。
石井ヶ里や神埼駅通りの一部の皆さんには
ご迷惑をおかけしました、申し訳ありませんでした
このことの経過と状況は別途ご報告させて頂きます。
このほかにも
「問題がある水質の井戸水」からの水道への転換の考え方
等々たくさんの議論がありましたので
テーマごとに改めてご報告します。
業務上の課題等の確認や情報の共有化を図っています
今回、10月の課長会の報告を行います。
1点目は、神埼市の下水道使用料の賦課漏れ
ニュースで流れ、ご存知の方も多いと思います。
今年の4月から下水道使用料の徴収事務を
神埼市より東部水道企業団が受託しました
水道料金と併せての一括徴収を行っています。
この一括徴収システムの
統合を図るためのデータの突合せ作業により
一部の方々に「下水道使用料が賦課されていない」ことが
判明しました。
その概要は、過去5年分の件数は205件
総金額は1532万5千円となっているようです。
この原因は
アパート等への入居の際に異動手続きが行われず
チェックができなかったことや
下水道使用開始届を受理したのに
登録処理を行っていなかったことのようです。
今後の対応は、早急に市役所の方で戸別訪問や調査がされ
過年度分の納付をお願いすることになると思います
市としても再発防止に向けた取り組みや
信頼回復に努められるものと思います。
東部水道企業団が下水道使用料の徴収を受託して
問題が明らかになり、結果的には良かったと思います。
2点目は、これも神埼市での問題ですが
水道工事によって送水管に空気が混入し
「水道水が白濁」するという事態が生じました。
石井ヶ里や神埼駅通りの一部の皆さんには
ご迷惑をおかけしました、申し訳ありませんでした
このことの経過と状況は別途ご報告させて頂きます。
このほかにも
「問題がある水質の井戸水」からの水道への転換の考え方
等々たくさんの議論がありましたので
テーマごとに改めてご報告します。
2014年10月03日
職場のスポーツ大会(ボウリング)
先日、毎年恒例のスポーツ大会で
ボウリングを行いました
大会に参加した職員からその時の様子を紹介します。

(写真:職場のボウリング大会)
-------------------------------
年に一回のスポーツ大会は
企業団の設立時から、職員の親睦が目的で行っています。
以前は、ソフトボールやミニバレーを行っていましたが
職員の年齢が上がるとともに、怪我が増えてくることもあり
ここ10年くらいは
体に負担の少ないボウリングに落ち着いています。

(写真:企業長の「金色のボール」で始球式の後、皆さんプレイ開始)

(写真:ボウリング大会の様子1)
和気藹々とプレイを始めたものの
投げるときはみんなやはり真剣な面持ちでの投球になります。

(写真:ボウリング大会の様子2)
けれども
この大会がないとボウリングをしない職員も多いはず・・・(笑)。
ストライクやスペアに喜び
スプリットやガターで悔しがり、みんながいい笑顔に。

(写真:ボウリング大会の様子3)
気になる結果は
企業長を除けば、参加者の中では最年長の方が優勝!。
TOP3は皆さんボウリング世代の職員
勢いよりも技術がやはり結果につながるみたいです。
今年の大会も、怪我なく楽しい時間を過ごせました
ただ、次の日は、やはり体が筋肉痛の方もいた様です・・・(笑)。
ボウリングを行いました
大会に参加した職員からその時の様子を紹介します。

(写真:職場のボウリング大会)
-------------------------------
年に一回のスポーツ大会は
企業団の設立時から、職員の親睦が目的で行っています。
以前は、ソフトボールやミニバレーを行っていましたが
職員の年齢が上がるとともに、怪我が増えてくることもあり
ここ10年くらいは
体に負担の少ないボウリングに落ち着いています。

(写真:企業長の「金色のボール」で始球式の後、皆さんプレイ開始)

(写真:ボウリング大会の様子1)
和気藹々とプレイを始めたものの
投げるときはみんなやはり真剣な面持ちでの投球になります。

(写真:ボウリング大会の様子2)
けれども
この大会がないとボウリングをしない職員も多いはず・・・(笑)。
ストライクやスペアに喜び
スプリットやガターで悔しがり、みんながいい笑顔に。

(写真:ボウリング大会の様子3)
気になる結果は
企業長を除けば、参加者の中では最年長の方が優勝!。
TOP3は皆さんボウリング世代の職員
勢いよりも技術がやはり結果につながるみたいです。
今年の大会も、怪我なく楽しい時間を過ごせました
ただ、次の日は、やはり体が筋肉痛の方もいた様です・・・(笑)。